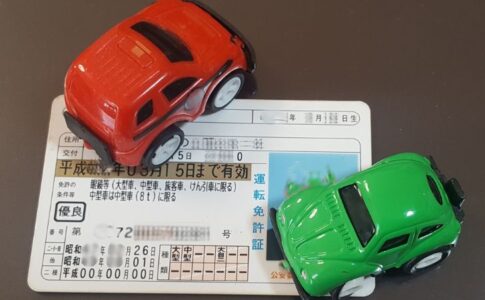近年、地震や台風などの自然災害に加え、サイバー攻撃や情報漏えい、パンデミックなど、企業を取り巻くリスクが高まっています。
こうした『もしも』に備え、迅速かつ的確に対応するために欠かせないのが『危機管理マニュアル』です。
この記事では、企業が危機に直面した際の損害を可能な限り軽減するため、危機管理マニュアルを作成する上で重要なポイントをわかりやすく解説しています。
自社の信頼と事業の継続性を守るため、ぜひ参考にしてください。
もし、社用車で事故を起こしたら?
目次
なぜ今、危機管理マニュアルが必要なのか?
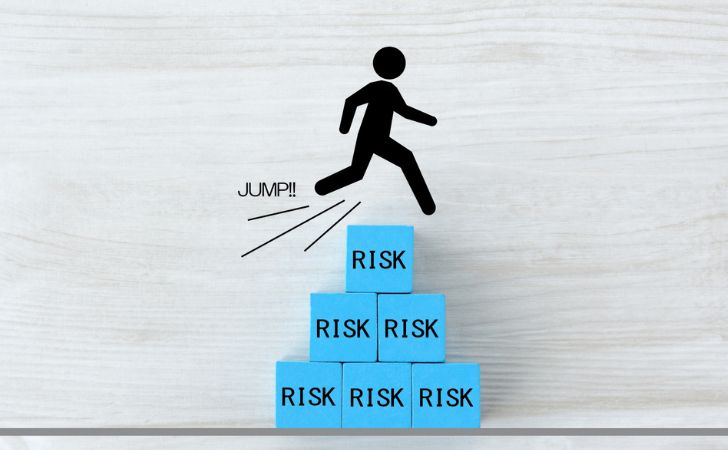
危機管理マニュアルは、企業が突発的なトラブルや緊急の状況に直面したときに、的確でスピーディな対応をおこなうための手順や行動方針をまとめた文書です。
いざというとき、対応手順が記載されたマニュアルがあれば従業員全体が足並みを揃えて行動できるようになり、被害を最小限に抑えながら業務の早期復旧を支援する役割を果たします。
自然災害やサイバー攻撃など多様化するリスク
近年、企業が直面するリスクは多様化し、自然災害やサイバー攻撃、テロ、風評被害など、さまざまな脅威が企業活動に影響を及ぼす可能性があります。
経団連が公表している『企業行動憲章』では、次のように述べられています。
市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動やテロ、サイバー攻撃、自然災害等に備え、組織的な危機管理を徹底する。
自然災害に関しては、地震、台風、豪雨、洪水、津波、感染症などが挙げられ、損壊や従業員の安全確保、サプライチェーンの寸断、風評被害など、企業活動に多大な影響を与える可能性があります。
サイバー攻撃も、企業にとって重大な脅威です。
ランサムウェア攻撃、標的型攻撃、DDoS攻撃、情報漏えいなどが発生すると、システム停止や顧客情報の漏洩、金銭的損失、企業のイメージダウンなど、深刻な被害をもたらす可能性があります。
また、テロや犯罪、風評被害、製品事故、品質問題、ハラスメント、内部不正など、その他リスクも企業活動に影響を与える可能性があり、組織的な危機管理体制の整備が不可欠です。
情報開示と対応スピードが信頼を左右する
企業が危機的な状況に直面した際、迅速かつ適切な対応は、社会からの信頼を維持する上で極めて重要です。
情報が瞬時に拡散される現代において企業の対応が遅れたり情報が不正確であったりすると、社会から批判を招き、企業の信用を大きく損なう可能性があります。
企業は危機発生時においても、事実に基づいた正確な情報を迅速に提供し、透明性を持った対応が必要です。
誠実な対応は顧客や社会からの信頼を維持し、風評被害軽減や企業の信頼性を高めることにもつながります。
危機管理マニュアルの基本構成と目的

企業にとって、予期せぬ危機はいつ起こるかわかりません。
自然災害、サイバー攻撃、内部不祥事など、さまざまなリスクが存在する中で、組織として適切に対応するため『危機管理マニュアル』の整備が欠かせません。
危機管理マニュアルは、非常時に従業員が迷わず行動できるようにするための指針であり、混乱を防ぎ、被害を最小限に抑えることを目的としています。
危機管理マニュアルの定義と役割
危機管理マニュアルとは、企業活動を脅かす可能性のある緊急事態を想定し、それに対してどう対応すべきかを整理した文書です。
対象となるのは事故や自然災害、情報漏えい、風評被害など多岐にわたります。
あらかじめ行動基準や責任分担、社内外への連絡体制を定めておくことで実際に危機が発生した際にも全社員が一貫した対応を取りやすくなり、万が一の事態においても混乱を防ぎ、迅速な対応ができます。
マニュアルに盛り込むべき基本要素
効果的な危機管理マニュアルには、明確な構成が求められます。
まず、目的と対象範囲を明記し、どのような危機に対応するものかを示します。
次に、リスク洗い出しと評価、初動対応手順、対策本部の設置方法や役割分担、情報開示ルールなど、具体的かつ実践的な内容を網羅することが重要です。
さらに、BCP(事業継続計画)策定やマニュアルの定期的な見直し、従業員向けの教育・訓練計画も欠かせません。
経団連によると、危機管理マニュアルに記載すべき事項には、次のようなものが挙げられます。
a.会社の危機管理に関する方針、基本理念
b.緊急事態発生時の経営トップの役割
c.緊急事態発生時の管理体制、関連組織の業務と権限
d.連絡体制
e.基盤インフラの確保
f.従業員一人ひとりの行動マニュアル
g.その他、自社の業容・業態に即した対応要領
引用元:経団連 企業行動憲章 実行の手引き(第8版)第9章 危機管理の徹底
企業が直面する主なリスクと対策

企業活動には常にリスクが伴います。
地震や台風といった自然災害、システム障害やサイバー攻撃、取引先のトラブルや法令違反などは企業の存続に直結する可能性があり、日頃からリスクに応じた対策を講じておかなければなりません。
危機管理マニュアルには、それぞれのリスクに対して具体的な行動計画と対策を盛り込むことが必要です。
取引先への影響を軽減する情報共有の工夫
取引先との連携が密接である企業にとって、自社トラブルが相手企業の業務にも波及するリスクは避けられません。
迅速で正確な情報共有を整えるためにも緊急連絡窓口を明確にし、連絡の手順や情報の内容をルール化しておく必要があります。
主要取引先の業務が停止すると自社生産や納品にも支障が出るため、代替サプライヤー確保や専用システム導入など、多角的な対策が有効です。
顧客データ・機密情報の漏洩リスクへの備え
顧客情報や機密データの漏洩は、企業にとって大きな打撃になる可能性があります。
その原因はサイバー攻撃だけでなく、内部不正や人為的ミスによるものです。
不測の事態に備えるには、アクセス制限強化やセキュリティソフト導入、従業員教育の徹底、データ暗号化、インシデント対応計画策定などが必要です。
外部委託先がある場合は、その管理体制の確認も忘れてはなりません。
情報保護の徹底は、企業の信用を守る第一歩です。
供給停止や納期遅延への対応フロー
自然災害や感染症拡大などの影響で、製品やサービスの供給が止まる、あるいは納期が大幅に遅れることもあります。
このような事態による損失を軽減するには、さまざまなリスクに備え、対応フローを整備しておくことが重要です。
在庫管理の見直しや代替生産拠点の確保、サプライチェーン多様化、顧客に向けた迅速な情報提供など、現実的な対応策を事前に検討しておくことで事業継続への影響を抑えられます。
企業の危機対応指針となる危機管理マニュアルは、緊急時にも対応できる精度の高さが重要です。
企業の危機管理を成功させる3つのポイント

企業が危機に直面した際、対応の迅速さと情報発信の適切さが被害拡大を防ぎます。
ここでは、危機管理を成功させるための2つの重要なポイントについて解説します。
スピーディでスムーズな初動対応
危機が発生した際、スピーディでスムーズな初動対応は、その後の被害を軽減する上で極めて重要です。
初期対応が遅れると状況が悪化し、企業ブランドへのダメージや事業継続の困難を招いてしまう恐れがあります。
的確な初動対応を実施するには、対応手順をマニュアルに明記して日頃から担当者が迷わず行動できるよう、環境を整えておくことも大切です。
マルチチャネルでの情報発信
正確な情報を素早く発信するには、マルチチャネルでの情報発信の整備が重要です。
社内向けにはメールや社内ポータルサイト、社外向けにはプレスリリースやSNSなど、複数のチャネルを活用し、関係者全員に迅速かつ正確な情報を届けられる環境を整えておきましょう。
適切なタイミングで事実に基づいた情報をわかりやすく伝えることで、誤解や混乱を防ぎ、企業の信頼性を維持できます。
社用車における危機管理マニュアル

社用車を業務で使用する企業にとって、事故や災害時に備えた危機管理マニュアルの整備は欠かせません。
万一の事態にも的確に対応できるよう、明確な手順をあらかじめ定めておく必要があります。
日頃からドライバーや管理者が内容を十分に理解し、有事の際にも落ち着いて行動できる体制を整えることが大切です。
社用車の危機管理マニュアルに必要な要素
社用車を業務に活用する企業では、運転中の緊急事態を想定した明確な対応指針が必要です。
JAFは、台風・火災などの災害時や悪天候などによる注意・避難方法を公開しています。
社用車の危機管理マニュアルに盛り込む内容を決める際は、これらの情報も参考にすると良いでしょう。
社用車の危機管理マニュアルに主に必要な要素は以下のとおりです。
- 一般的な事故発生時の対応手順
社用車を使用中に事故が発生した場合、冷静かつ迅速な対応が求められます。けが人の救助や会社への連絡など、事故時の対応について社内での共有が重要です。
- 車両水没時の脱出方法
豪雨による道路冠水や水没に遭遇した場合、電動ウィンドウが作動せず車外に出られないケースがあるため、ガラス破砕の手順や脱出経路を明文化します。 - 災害発生時の対応フロー
地震や豪雪などによって社用車が立ち往生した際、エンジンの停止、排気ガスの確認、車内待機の基準などをマニュアルに記載します。排気口の確保や定期換気などの明文化が重要です。 - 緊急時の連絡体制
事故やトラブル発生時には、社内外への迅速な連絡が必要です。ドライバー、管理者、保険会社、整備業者への連絡手順と優先順位を明確にし、従業員全体に共有します。
参考:地震・台風・大雪時の運転は危険!知っておくべき注意点 | JAF
社用車の事故リスク
企業活動において社用車の使用は日常的な業務の一環であり、営業、配送、出張など多岐にわたる場面で運用されています。
しかし、社用車を利用する際の事故は、ドライバー個人の責任にとどまらず、企業全体の法的・社会的責任に発展する可能性があります。
社用車の事故が発生した場合、被害者・加害者の対応だけでなく、企業ブランドの毀損、社会的信用の低下、報道対応、損害賠償、保険料の増加など、複数の損失が同時に発生します。
これらを未然に防ぐためには、ドライバーへの安全運転講習の定期実施、アルコールチェックの徹底、安全運転管理者の配置、運行前点検記録の管理など、明確なルール整備と運用が必要です。
危機管理マニュアルには、事故発生時の連絡体制や報告手順、再発防止策の提示とともに、事故の未然防止を目的とした日常管理項目の具体的な記載が求められます。
ドライバーの判断任せにせず、組織としての安全意識を共有する取り組みが重要です。
社用車の危機管理と周知徹底
企業の社用車に関する危機管理は、事故や災害発生時の安全確保において重要な役割を担います。
社用車の使用ルールや安全運転の基準を明文化し、ドライバー全員への周知は基本的な対策です。
具体的には、定期的な点検と整備の実施、緊急連絡先の共有、そして事故発生時の対応手順を明確にしておく必要があります。
また、災害時の車両管理や緊急避難方法も策定し、万が一の際の混乱を防ぐ工夫が求められます。
さらに、ドライバーに対する安全教育や危機対応訓練の定期的な実施、取り組みを社内全体に浸透させるため、定期的な説明会や周知文書の配布も欠かせません。
社用車を使用する全員が正しい知識を持ち、緊急時に冷静な対応ができる環境づくりが重要です。
まとめ|危機管理マニュアルを作成して企業の信頼を守ろう

危機管理マニュアルは、企業が予期せぬトラブルや事故に対応するための大切な指針です。
マニュアルを整備しておけば、問題発生時に迅速かつ適切な対応ができるので、被害の拡大を防げます。
作成にあたっては、日々の業務の中で想定されるリスクを把握し、現場の状況に合わせた実践的な内容を盛り込みます。
完成後も定期的に内容を見直し、社員への周知や訓練を継続していけば、変化する環境や新たな課題にも対応できる体制が維持できます。
JAFのeラーニングでは、実践的な危険予知・事故回避が学べます。
危険予知や安全運転に役立つ実験映像なども公開しているので、いざという時に役立つマニュアル作りにも役立ちます。
企業の信頼を守る第一歩として、今こそ危機管理マニュアルの整備と教育に取り組んでみてください。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /