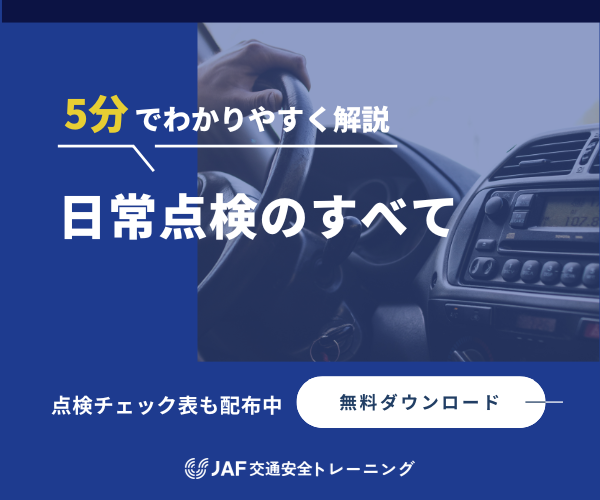業務で自動車を利用する企業にとって、運転中のトラブルは避けたいものです。
交通事故を防ぎ、従業員の人命を守るためにも、企業は日常点検整備を適切におこない、自動車の状態や整備不良の有無を確認する必要があります。
しかし、実践しようにも日常点検整備の正しい手順がよくわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。
実際に、日常点検整備はチェックすべき項目や実施する上で意識すべきポイントが多くあります。
本記事では、日常点検整備の実施頻度やチェック項目などについて解説します。
日常点検整備を実施する際の参考にしてください。
若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因
目次
日常点検整備とは

最初に、日常点検整備の概要について確認しましょう。
日常点検整備は国土交通省で定義が決められており、道路交通法でも実施について記載があります。
実施する際は、事前に必ず確認しましょう。
日常点検整備の概要
日常点検整備は、日常的に自動車を運転する者が、自身でおこなう点検整備です。
一般的に、自動車の点検整備は整備工場でおこなわれるイメージがありますが、日常点検整備は誰でも実施できる簡単なものです。
なお、日常点検整備は個人・企業を問わず、自動車のユーザーであれば実施すべき義務となっています。
自動車の安全性を確保するためにも、適切な頻度で実施しましょう。
日常点検整備を実施する目的
日常点検整備は、エンジンルーム・車周り・運転席の3つの観点から、自動車の状態を確認し、安全に走行できるか確認し、少しでも異常や違和感があれば整備工場に相談することが目的です。
そもそも自動車には使用する度に消耗する部品があり、性能が低下するリスクがあります。
もし自動車の部品や機器に故障や不良があれば、交通事故を引き起こす原因になるでしょう。
日常的に自動車を利用する企業にとって、交通事故は人命を脅かす重大なリスクです。
従業員の安全を守る上でも、日常点検整備は重要です。
車検や定期点検整備のような点検もありますが、適切な頻度で日常点検整備を実施すれば、ブレーキ・ハンドルなどの異常を早期発見でき、消耗品の交換時期も判断できます。
なお、点検整備の過程で異常や違和感があった際は、整備工場に相談しましょう。
日常点検整備は義務
日常点検整備は、道路運送車両法において以下のように定められています。
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
引用:道路運送車両法第四十七条の二
他方で、日常点検整備の未実施に罰則は設けられていません。
企業・個人に関わらず、日常点検整備は自動車のユーザーであれば、実施しなければならない義務です。
しかし、日常点検整備を怠った結果、自動車の整備不良によって交通事故が発生した場合、人命が脅かされる事態になるリスクがあります。
また、灯火やブレーキに整備不良があった際も、交通違反として扱われるため注意が必要です。
加えて、日常点検整備を適切に実施していないことが発覚すれば、社会的な非難は免れないでしょう。
罰則こそありませんが、日常点検整備は企業の社会的信頼を維持したり、安全に自動車を運行する安全意識の醸成を目指す上でも、重要な意義を持つ取り組みです。
日常点検整備の実施頻度

自家用自動車の社用車における日常点検整備の実施は義務ではあるものの、実施頻度は決められていません。
各自で最適な頻度を判断し、おこなう必要があります。
自家用自動車の社用車における日常点検整備の適切な実施頻度と、通常時以外に日常点検整備をするべきタイミングについて紹介します。
日常点検整備の頻度は最低月1回が適切
自家用自動車の日常点検整備は、走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に実施するよう、国土交通省により提示されています。
1つの目安として、最低1カ月に1回は実施するのが適切です。
自家用自動車の日常点検整備にかかる時間は、全項目確認しても10〜15分程度です。
必要に応じてエンジンルームだけ確認するなど、項目を分けてこまめに実施しても良いでしょう。
定期点検整備が12カ月、あるいは24カ月ごとなので、その間の自己管理と考え、自動車の使用状況に合わせて頻度を決めましょう。
月1回以外で日常点検整備をするべきタイミング
日常点検整備は1カ月に1回と限らず、長距離運転の前や高速道路の走行前なども実施しましょう。
例えば、長距離運転や高速道路を走行する場合は、特にエンジンルームとタイヤの確認が大切です。
点検整備を怠ってオーバーヒートを起こしたり、タイヤが破裂・パンクしたりすれば、大事故になりかねません。
また、暑さや厳しい寒さでも不具合が起きる場合があるため、天候に合わせての実施も検討しましょう。
冷暖房の酷使でバッテリが上がったり、凍結によりゴム製品が破損したりするケースもあります。
自然災害や異常気象による故障は、車両保険がおりる場合があります。
また、外傷はすぐに気づくことができますが、内部破損は見過ごすこともあるでしょう。
適切な日常点検整備の実施により早期発見につながります。
自家用自動車の日常点検整備で確認する15項目

日常点検整備でチェックする項目は、国土交通省で細かく定められています。
以下は、自家用自動車における日常点検整備の確認項目です。
| エンジンルーム | ブレーキ液の量は規定の範囲内である 冷却水の量が規定の範囲内である エンジン・オイルの量が規定の範囲内である バッテリ液の量規定の範囲内である ウインド・ウォッシャ液の量が適当である |
| 車の周り | ランプ類の点灯・点滅具合が適当である タイヤに亀裂や損傷がない タイヤの空気圧が規定の範囲内である タイヤの溝の深さが十分である |
| 運転席 | エンジンのかかり具合はスムーズで、異音がない ウインド・ウォッシャ液の噴射状態は適当である ワイパーの拭き取りが良好である ブレーキの踏み残りしろと効き具合は十分である 駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)は十分である エンジンの低速・加速状態に異常がない |
ここからは、各項目における確認時のポイントについて解説します。
1.ブレーキ液の量
ブレーキ液の量は、自動車の安全性を確保するための重要な点検項目です。
ブレーキ液はブレーキシステムの圧力を伝える役割を担っており、その量が不足するとブレーキが効かなくなり、制動距離が長くなる恐れがあります。
点検方法としては、エンジンルーム内のブレーキ液リザーバータンクを確認し、液面が「UPPER」と「LOWER」の間にあることを確認します。
液面が低い場合は、適切なブレーキ液を補充し、同時に漏れがないかも確認してください。
2.冷却水の量
冷却水は、エンジンの温度を適切に保つために必要不可欠な要素です。
冷却水の量が不足すると、エンジンが過熱し、重大な損傷を引き起こす可能性があります。
点検の際は、ラジエーターのリザーバ・タンクを確認し、液面が「FULL」と「LOW」の間にあるかを確認します。
冷却水が不足している場合は、適切な割合で希釈された冷却水を補充してください。
また、冷却系統に漏れがないか、ホースや接続部もあわせて点検することが重要です。
3.エンジン・オイルの量
エンジン・オイルの量は、エンジンの潤滑や冷却、清浄作用を維持するために不可欠です。
オイル量が不足すると、エンジンが適切に作動せず、重大な損傷を引き起こすことがあります。
点検方法は、エンジンを停止してオイルレベルゲージを引き抜き、付着しているオイルを拭き取ります。
その後ゲージを再度差し込み、再び引き抜いてオイル液面が「L」と「F」の間にあることを確認してください。
オイル量が不足している場合は、指定されたオイルを適量補充します。
ただし、エンジンオイルは不足や異常がなくても、適切な時期に交換しましょう。
4.バッテリ液の量
バッテリ液の量は、エンジンの始動や自動車の電気系統が正常に機能するために重要です。
バッテリ液が不足すると、バッテリの性能が低下し、最悪の場合、エンジンの始動ができなくなるほか、バッテリーが爆発する危険もあります。
点検方法としては、車を揺らすなどしてバッテリの液量が「UPPER」と「LOWER」の間にあるかを確認してください。
液面が低い場合は、蒸留水を補充します。
バッテリ端子の腐食もあわせて点検・清掃をおこなうことで電気系統のトラブルを防ぐことができます。
5.ウインド・ウォッシャー液の量
ウインド・ウォッシャー液は、フロントガラスを清潔に保つために必要な液体です。
ウォッシャー液が不足すると、汚れや虫などが付着した際に除去できず、視界が悪化して運転支障をきたすことがあります。
点検方法は、ウォッシャー液リザーバータンクの液面を確認し、必要に応じて補充しましょう。
ウォッシャー液には、専用の洗浄剤を使用してください。
特に冬季には凍結防止剤が含まれているものを使用すると、寒冷地でも安心して運転できます。
6.ランプ類の点灯・点滅
ランプ類の点灯・点滅は、安全運転のために欠かせないチェック項目です。
ヘッドライト、ブレーキ・ランプ、ウインカ・ランプ、テール・ランプなどが正常に作動しているか確認しましょう。
「電球が切れた」「ヒューズの断絶」「リレー・スイッチの不良」などが原因でヘッドライトが点灯しないことがあります。
例えば、電球の寿命が切れている場合は新品を購入し付け替えることで解決します。
また、ランプのレンズが汚れている場合は清掃し、視認性を確保してください。
ランプの点灯状態を定期的に確認することで、夜間走行時や悪天候時の安全性を高めることができます。
7.タイヤの亀裂や損傷の有無
タイヤの亀裂や損傷有無の点検は、走行中のトラブルを未然に防ぐために重要なポイントです。
タイヤの表面や側面に亀裂や切れ目、膨らみがないかをチェックします。
これらの異常が見られる場合は、早急にタイヤを交換する必要があります。
また、異物が刺さっていないかも確認してください。
タイヤの状態を定期的に点検することで、パンクやバーストのリスクを減らし、安全な走行を維持が可能です。
8.タイヤの空気圧
タイヤの空気圧は、走行性能や燃費、タイヤの寿命に影響を与えます。
適正な空気圧の維持は、安全運転の基本です。
空気圧は、タイヤ接地部のたわみ面積や、タイヤゲージを使って自動車の取扱説明書に記載された推奨値を基準にチェックしましょう。
タイヤの空気圧が低すぎると、タイヤの摩耗が早くなり、燃費も悪化します。
逆に高すぎると、乗り心地が悪化したり、タイヤがバーストしたりするリスクが高まります。
定期的に空気圧を測定し、適正な値に調整することが大切です。
9.タイヤの溝の深さ
タイヤの溝の深さは、雨天時の排水性を確保し、安全なブレーキングを可能にします。
溝が浅くなると、特に雨天時にハイドロプレーニング現象(タイヤと路面の間に水の膜ができて、ハンドルやブレーキなどが制御できなくなる状態)が起こりやすくなり、自動車の制御が難しくなります。
タイヤの溝の深さは、スリップサインや専用の測定器で定期的に確認し、1.6mm未満になった場合は交換が必要です。
安全な走行を維持するためにも、タイヤの状態を常にチェックする習慣をつけましょう。
10.エンジンのかかり具合・異音
エンジンのかかり具合や異音は、自動車の健康状態を示す重要な指標です。
エンジンを始動する際にスムーズにかかるか、また異常な音がしないかを確認します。
異音がする場合、ベルトの緩みやオイル不足、部品の劣化などのトラブルも考えられます。
トラブルを放置すると事故や大きな故障にもつながるため、早期に点検し、必要に応じて修理や部品の交換をしてください。
11.ウインド・ウォッシャー液の噴射状態
ウインド・ウォッシャー液の噴射状態は、視界を確保するために重要な点検項目です。
ウォッシャーノズルから適切に液が噴射されているかを確認します。
噴射が不十分な場合や方向がずれている場合は、ノズルの詰まりやホースの劣化が考えられます。
詰まりがある場合はノズルを清掃し、ホースの劣化が見られる場合は交換が必要です。
12.ワイパーの拭き取り能力
ワイパーの拭き取り能力は、雨天時や雪の日の視界を確保するために重要です。
ワイパーブレードが劣化していると、ガラス面に線が残ったり、拭き取りが不十分になります。
ワイパーブレードのゴム部分にひび割れや硬化が見られる場合は交換が必要です。
また、ワイパーの動き(高速・低速)がスムーズかどうかも確認し、異常がある場合は点検・修理を依頼しましょう。
13.ブレーキの踏み残りしろと効き具合
ブレーキの踏み残りしろと効き具合の点検は、自動車の安全性を確保するために極めて重要です。
踏み残りしろとは、ブレーキをいっぱいに踏んだときのペダルと床との隙間です。
この部分が適切でない場合、ブレーキの効きが悪くなり、緊急時の制動距離が長くなる恐れがあります。
適切な踏み残りしろは、ペダルが遊び部分を超えてしっかりと抵抗を感じる位置です。
また、実際に走行し、ブレーキを踏んだ際の反応や制動力を確認します。
ブレーキの効きが悪いと感じた場合は、ブレーキパッドやディスク、ブレーキ液の状態などをチェックし、必要に応じて交換や補充をおこなってください。
14.駐車ブレーキの引きしろ
駐車ブレーキの引きしろは、自動車を安全に停車させるために必要な点検項目です。
引きしろが多過ぎる場合、駐車ブレーキが十分に作動せず、自動車が動いてしまうリスクがあります。
点検方法は、駐車ブレーキを引き、レバーの動き具合と引きしろの長さを確認します(ペダル式の場合は踏みしろ)。
適切な引きしろは、レバーがしっかりと固定され、自動車が動かない状態です。
引きしろが適切でない場合は、ブレーキワイヤーの調整が必要です。
また、駐車ブレーキの効き具合を実際に確認し、傾斜のある場所で自動車がしっかりと固定されるかをチェックします。
15.エンジンの低速・加速状態
エンジンの低速・加速状態の点検は、自動車のパフォーマンスと燃費に直接影響を与えます。
エンジンがスムーズに始動し、アイドリング時に安定しているかを確認しましょう。
また、アクセルを踏んだ際の加速具合や異音がないかもチェックポイントです。
点検方法としては、エンジンを始動し、アイドリング時の回転数やエンジン音を観察します。
次に、走行中にアクセルを踏み込み、エンジンの反応と加速具合を確認します。
異常がある場合、燃料システムや点火プラグ、エアフィルターなどのトラブルがあるかもしれません。
これらの異常は、エンジンのパフォーマンス低下、予期せぬ故障や燃料悪化にもつながります。
事業用自動車における日常点検整備

事業用自動車は、利用目的や事故発生時の影響度が異なることから、自家用自動車とは日常点検整備の頻度や点検項目に違いがあります。
ここでは、事業用自動車における日常点検整備の実施頻度や確認項目について解説します。
事業用自動車における日常点検整備の実施頻度
バスやトラックなどの事業用自動車は自家用自動車とは異なり、1日1回、運行前に必ず日常点検整備をしなければなりません。
多くの人や物を運搬する公共性の高さや、ひとたび交通事故を起こすと社会的に大きな影響を及ぼすことから、「1日1回」と頻度が決められています。
事業用自動車の日常点検整備で確認する項目
事業用自動車における日常点検整備の項目は以下のとおりです。
| ブレーキ | ペダルの踏みしろが適当である ブレーキの効きが十分である ブレーキ液の量が適当である |
| タイヤ | 空気圧が規定値である 亀裂・損傷・異常摩耗がない ディスク・ホイールの取り付け状態が適当である |
| バッテリ | バッテリ液の量が適当である |
| エンジン | 冷却水の量が適当である エンジン・オイルの量が適当である ファンベルトの張り具合が適当である |
| 灯火装置・方向指示器 | 点灯・点滅具合が適当である 汚れや変色、損傷がない |
| ウインド・ウォッシャ液 | 噴射の向きや高さ、量が適当である |
| ワイパー | 拭き取りが良好である |
| エアタンク | 凝水がない |
| 運行において異常が認められた箇所 | 前回の運行で異常を認めた箇所について、これからの運行に支障がないか |
自家用自動車における日常点検整備の実施方法

自家用自動車の日常点検整備では、エンジンルーム・車周り・運転席の3カ所をチェックしますが、注目すべき箇所が異なります。
確実に安全を確保するためにも、点検箇所は正確に把握しましょう。
ここでは、自家用自動車における日常点検整備の実施方法について解説します。
エンジンルーム
エンジンルームの日常点検整備は、ブレーキ液・冷却水・エンジンオイルなど、消耗品の確認が中心です。
エンジンルームの点検は、必ずエンジンが停止している状態で実施しましょう。
ブレーキリザーバータンクや、ラジエーターリザーバータンクなどに記載されている目盛りを参考に、適切な量が残っているかをチェックしましょう。
消耗品が不足している際は、適宜補充をおこないます。
もし、消耗品が減少するスピードが速い際は、部品の損壊によって液漏れが発生している恐れがあります。
液漏れが疑われる場合は、すぐに整備工場で点検・修理してもらいましょう。
なお、走行直後のエンジンルームの点検は避けてください。
走行直後のエンジンルームは、まだ熱を持っている可能性が高く、危険な状態です。
必ずエンジンが冷えるのを待ってから点検しましょう。
車周り
車周りの点検では、タイヤやランプに注目します。
タイヤを点検する際は、亀裂・損傷の有無・空気圧や溝の深さに問題がないかをチェックしてください。
タイヤの異常は、パンクやスリップを引き起こすリスクを高めるため、目視するだけでなく、実際に触って感触に問題がないか確認しましょう。
タイヤの空気圧はユーザー自身で調整も可能ですが、自信がなければ整備工場に任せる方法もおすすめです。
多くのガソリンスタンドやカー用品店では、無料で空気圧の確認や調整をしてくれます。
ランプを点検する際は、以下のランプをチェックします。
- ヘッドランプ
- テールランプ
- ライセンスランプ
- ブレーキランプ
- クリアランスランプ
- バックランプ
- フォグランプ
- ウインカーランプ
それぞれのランプが問題なく点灯・点滅するか、明るさや点滅速度に問題がないかを確認しましょう。
運転席
運転席は、実際に着席して点検をおこないましょう。
運転席ではワイパーの拭き取り能力・ブレーキの踏みしろや効き具合などを確認します。
実際にエンジンをかけ、かかり具合や低速・加速状態をチェックしてください。
もし、エンジンをかけた際や、アイドリング状態になった際に異音が発生するようであれば、整備工場に確認してもらいましょう。
エンジンの異常を放置すると、安全に運転できなかったり、走行中に突然停止し、追突事故を起こしたりする恐れがあります。
日常点検整備を怠ることによるリスク

日常点検整備を怠ると、車両トラブルや交通事故などのリスクがあります。
安全に自家用自動車を使用するためにも、日頃から日常点検整備を習慣付けておくことが大切です。
バッテリが上がる
日常点検整備を怠るとバッテリ液量の状態に気づかず、バッテリが上がってエンジンがかからなくなる恐れがあります。
バッテリが上がる前兆や上がっていることに気づくためには、日常点検整備が重要です。
バッテリが上がる原因はさまざまですが、日常点検整備で防げるのはライトのつけっぱなしとバッテリ液量の減少の把握です。
ライトのつけっぱなしは、エンジンを切ったあとに車両まわりを点検することで気づけます。
バッテリ液が少なかったり、なくなった状態で走行を続けると、バッテリが破裂することもあります。
また、使用状況により大きく変化しますがバッテリの寿命は2〜5年なので、エンジンルーム内の日常点検整備で状態を確認するとともに、年数にも気をつけてトラブルが発生する前に交換しましょう。
タイヤがパンクする
道路を走っているとタイヤに釘が刺さるなどして、タイヤがパンクすることもあり得ます。
自動車まわりの日常点検整備で、タイヤの亀裂・損傷・摩耗状態と空気圧を確認しましょう。
外傷は見てわかるものもありますが、目視では気づけないものもあるため、タイヤの空気圧のチェックも必須です。
空気を入れてもすぐに空気圧が低下する場合は、目に見えない亀裂や損傷がある可能性があります。
また、縁石に乗り上げることもパンクの原因です。
タイヤの側面は薄いため、擦ったりぶつけたりするだけで傷つきます。
縁石に乗り上げた場合は、タイヤの状態を点検しましょう。
オーバーヒートを起こす
オーバーヒートとは、エンジンが異常に熱くなり、冷却機能を上回ってしまうエンジントラブルです。
オーバーヒートが起こると、走行時にいつもよりスピードが出なかったり、甘い匂いや焦げた臭いがしたり、ボンネットから煙が出たりします。
オーバーヒートの原因の一つは、冷却水やエンジンオイルの不足です。
日常点検整備で、エンジンルーム内の各液量の確認や、運転席に座ってエンジンのかかり具合やエンジン音を確認することで、異常の有無をチェックしましょう。
オーバーヒートすると最悪の場合はエンジンが破損し、エンジンごと取り替えが必要になることもあります。
もし走行中に違和感を覚えたら、すぐに安全な場所に停車し、必要であればロードサービスや整備工場に連絡して対処してください。
オーバーヒートについての詳しい症状や対処法は以下の記事をご覧ください。
▼オーバーヒートの症状(マイカー点検ノート トラブル対処法)‐JAF
整備不良による罰則に当たる
自家用自動車の場合、日常点検整備を実施していなくても明確な罰則はありません。
しかし、整備不良の自動車を運転することは、違反行為に該当します。
もし自家用自動車が整備不良と認定された場合、ドライバーには違反点数が加算されます。
また、ドライバーだけでなく、運行管理車や整備管理者、企業も車両管理責任を問われます。
違反点数と反則金の詳細は以下のとおりです。
| 内容 | 違反点数 | 反則金 |
|---|---|---|
| ライトの整備不良 | 1点 | 普通車:7,000円 大型車:9,000円 |
| ブレーキの整備不良 | 2点 | 普通車:9,000円 大型車:12,000円 |
社会的信用を失う
日常点検整備を怠ったことで故障や車両トラブルが起き、それが原因で交通事故が発生してしまうと、整備不良の自家用自動車を運転させたとして、企業の信頼喪失のリスクがあります。
同時に、企業および車両管理責任者が責任を問われる可能性もあります。
最悪の場合、企業の存続すら危ぶまれる事態に陥るかもしれません。
日常的な点検を怠ると交通安全を脅かす上に、企業全体に関わる大きな問題に発展するリスクがあることを覚えておきましょう。
日常点検整備で異常が見つかった場合の対応

日常点検整備を適切に実施して安全運転を心がけていても、自動車の部品は摩耗・劣化していくため、異常や不具合が見つかることがあります。
異常が見つかった場合は、状況に合わせて速やかに整備工場や販売店に連絡してください。
日常点検整備で見つかった異常や不具合には、基本的に車両保険の対象にはなりません。
修理費用や消耗品の交換費用がかかります。
ただし、新車の場合は、不具合の原因によってメーカー保証が受けられる可能性があります。
日常点検整備を効果的に実施するためのポイント

日常点検整備は、ただ漫然と実施しても効果はありません。
ここでは、日常点検整備を効果的に実施する上で、意識すべきポイントについて解説します。
実施する意義を共有する
日常点検整備に取り組む際は、安全運転管理者が中心となり、従業員に実施する意義を共有しましょう。
日常点検整備は自動車を常に安全な状態で維持することにより、運転中のトラブルを防ぎ、交通事故を防ぐための取り組みです。
しかし、従業員が日常点検整備の意義を理解していないと、適切に実施されないリスクが発生しかねません。
そのため、必ず日常点検整備や社用車の管理に関する研修をおこなうなど、日常点検整備を実施する意義を学ぶ機会を設けましょう。
研修をおこなう際は、「JAF交通安全トレーニング」の活用がおすすめです。
JAF交通安全トレーニングなら、日常点検整備の必要性など、安全意識の醸成に役立つ知識を効率的に学べます。
必要があれば整備工場で点検整備を受ける
日常点検整備は、基本的に素人でも実施できる内容ですが、異常や違和感があった場合は整備工場で点検を受けましょう。
特に異常があった際は、適切な対応ができなければ、自動車の状態を悪化させる恐れがあります。
自社での対応が難しい状況なら、整備工場へ点検・修理を依頼しましょう。
また、整備工場からアドバイスを受ければ、より効果的な日常点検整備を実現できるでしょう。
日常点検を管理しよう

日常点検整備後は、必ず結果を記録しましょう。
異常の有無に関わらず、日常点検整備の記録は自動車の状態を把握する上で欠かせないものです。
とりわけ異常や整備不良があった際は、前日の状態を参照することで、異常が発生した原因や経緯を把握しやすくなります。
なお、点検結果はデータでの運用がおすすめです。
JAFや国土交通省のチェックシートを活用し、見落としや長期にわたる未実施を防ぎましょう。
また、点検項目と頻度をデジタルで管理できるツールもあります。
点検内容の分析ができたり、入力の手間を省けたりするため、必要に応じて検討しましょう。
日常点検整備だけでなく、定期点検整備や車検も忘れずに実施する

日常点検整備だけでなく、定期点検整備や車検も忘れずに実施しなければなりません。
定期点検整備とは、故障や車両トラブルが発生しないように、自動車の各所を点検し、必要に応じて部品の交換や修理などをおこなう点検のことです。
自家用自動車の場合は1年に1回実施することが、法律で定められています。
出典:道路運送車両法第四十八条
また、車検も忘れてはいけません。
車検とは、ブレーキや照明器具、警報装置などが法律で定められた保安基準を満たしているか検査する制度です。
自家用自動車の場合、新車登録から初回の車検までは3年、以降は2年ごとに受ける必要があります。
なお、車検を受けているからといって、定期点検整備を怠ってはいけません。
なぜなら、定期点検整備では自動車を安全かつ快適に使用するために、車検のときより多くの項目を検査するからです。
車検に通ったからといって、必ずしも次の車検までトラブルなく乗れるわけではありません。
そのため、日々の点検だけでなく、定期点検整備や車検も確実に実施しましょう。
うっかり忘れてしまわないように、定期点検整備・車検の頻度や実施時期は運転日報などに書いておくのがおすすめです。
まとめ:日常点検整備の目的と必要性を理解して最低月1回は実施しよう
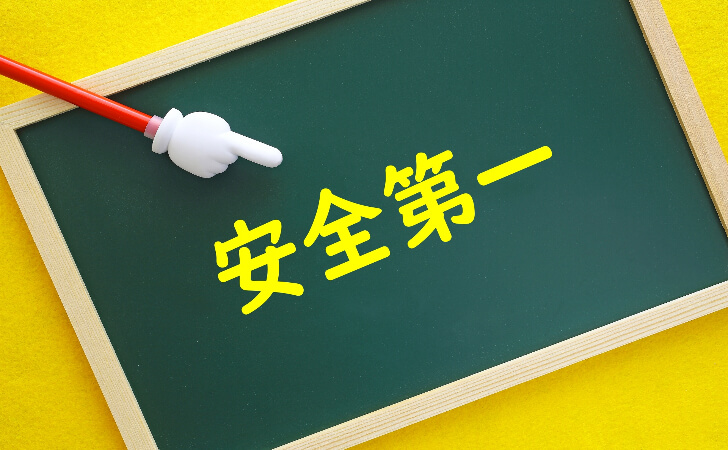
日常点検整備とは、自動車を良好な状態で保ち、日頃の運転を安全におこなうための点検整備です。
全15項目をドライバー自身で点検します。
自家用自動車の日常点検整備の頻度は定められていませんが、最低でも1カ月に1回、状況に応じて適切なタイミングで実施しましょう。
日常点検整備を怠ると、未然に防げた事故やトラブルが発生し、人命を脅かすだけでなく、経済的損失や社会的信用の喪失につながりかねません。
日常点検整備は、自動車の所有者またはドライバーの義務であることを忘れないようにしましょう。