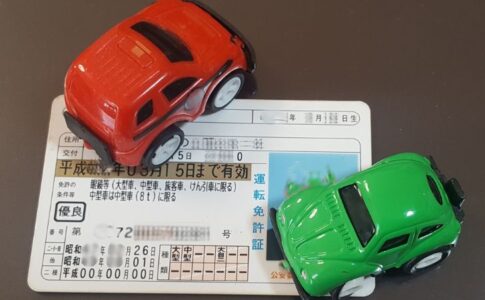人が安全を感じるあまり、危険な行動を取ってしまう『リスクホメオスタシス』という心理的な現象をご存じですか。
この記事では、リスクホメオスタシス理論から、心理学的な対策方法やリスク補償理論との違いについて詳しく解説しています。
実生活でどのようにリスクホメオスタシスを意識し、安全対策に活かせば良いかなども紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /
目次
リスクホメオスタシスとは

リスクホメオスタシスとは、人が潜在的に抱えるリスク水準を一定に保とうとする人間の考え方のことです。
安全対策が進み安全性が高まったとしても、その分だけ人は無意識にリスクの高い行動を取り、結果として事故や災害発生率が変わらない、あるいは増加する場合もあります。
「安全だから大丈夫」などの過信が、かえって危険を招く逆説的な現象です。
リスクホメオスタシスの理論
リスクホメオスタシスは、1982年にカナダの交通心理学者ジェラルド・ワイルド氏によって提案された理論です。
リスクホメオスタシス理論によると『自動車の安全技術が進化しても、ドライバーはその分リスクを取るような行動をする傾向があり、最終的な事故発生率はあまり変わらない』とされています。
車両に最新の安全装置が搭載された場合、ドライバーは「安全になった」と感じることで警戒心が薄れ、スピードを上げたり注意を怠ったりしてしまう場合があります。
結果として、事故リスクが減るどころか、元の水準に戻ってしまうこともあるのです。
リスクホメオスタシスの理論は、結果的に、安全装備が充実しても事故リスクの全体的な水準はほとんど変わらないという考え方です。
実際に、冬道でノーマルタイヤを履いたまま運転している人は慎重に、ゆっくりと運転する傾向があります。
しかし、スタッドレスタイヤに交換した途端、安心感からスピードを上げて走行するようになる場面は少なくありません。
こうした行動は、まさにリスクホメオスタシス理論を裏付ける一例と言えます。
リスクホメオスタシスの主旨
リスクホメオスタシスの本質は、単に安全対策が無意味だということではありません。
むしろ、安全対策の効果を引き出すためには、人々の意識改革が不可欠であることを示唆しています。
技術的な安全対策と同時に、リスクに対する認識を高め、安全行動を促すための教育や啓発活動が重要です。
リスクホメオスタシスのメカニズム
人は許容できるリスクの目標水準を持っており、たとえ安全対策が施されても、従来のリスク水準を保つように行動する傾向があります。
リスクホメオスタシス理論を理解すれば、安全対策がどのように影響を与えるか、そしてドライバーの意識がどれほど重要かが再認識できます。
安全技術だけに頼るのではなく、行動や意識変化も大切であることを知っておくことが、より安全な社会を築くための第一歩です。
リスクホメオスタシスへの対策

リスクホメオスタシスは人間の心理に根ざした現象であるため、完全に排除することは困難です。
しかし、心理学的な対策を講じることで影響を軽減し、より安全な行動を促すことはできます。
リスク認知を高める
リスクホメオスタシスを克服するためには、まず自分が置かれている環境や状況を正しく理解し、リスクを的確に認識する力が欠かせません。
『リスク認知』を高めるには、日々の情報収集とアップデートが重要です。
冬道の運転であれば、路面状況や天気予報をこまめにチェックし、スタッドレスタイヤの性能を過信しないように心がけること、リスクに関する情報共有が有効です。
家族や同僚と安全運転に関する情報を交換したり、事故の事例を共有したりすることでリスクに対する意識を高められます。
さらに、航空業界におけるCRM(Crew Resource Management)のように、チーム内で情報を共有し、互いにサポートし合う体制を構築することも効果的です。
CRMは、航空機の安全運航を確保するために、乗員が持つ知識や経験、周囲の情報など、利用可能なすべてのリソースを有効活用し、チーム全体のパフォーマンスを向上させるマネジメント手法です。
CRMの導入により、乗員間のコミュニケーションや意思決定、状況認識などのノンテクニカルスキルが強化され、ヒューマンエラーの防止につながっています。
この考え方は医療や鉄道など他の高リスク産業にも応用されており、チーム全体でリスクを認識・共有し、対処する文化を育むことの重要性が示されています。
私たちの日常生活においても家族や職場の仲間とリスクに関する情報を共有し、互いにサポートし合う体制を築き、リスク認知を高めることが重要です。
目標設定を見直す
リスクホメオスタシスの悪影響を防ぐには、人間の行動に働きかける必要があります。
特に重要なのが、目標リスクの見直しです。
例えば、目的地に急ごうとするあまり、ついスピードを出しすぎてしまうケースは、時間を守る目標が安全に運転する目標を上回ってしまった結果です。
こうした危険を防ぐには、あらかじめ時間に余裕を持った行動計画を立ててみましょう。
また、リスク許容度(=目標リスク)は、体調や環境によって変化する点にも注意が必要です。
疲れているときや体調がすぐれないときは普段よりも注意力が落ち、リスクに対する耐性も低下しているため、無理をせず休憩を取る・運転を控えるなどが重要な行動です。
行動の振り返り
過去の安全運転の経験や事故を起こしたことがない事実は、自信につながる一方で、リスクホメオスタシスを助長する要因にもなり得ます。
「自分は運転が上手いから大丈夫」「今まで事故を起こしたことがないから今回も大丈夫」といった過信は禁物です。
定期的に自身の運転行動を振り返り、改善点を見つけるように心がけましょう。
客観的に自身の運転を見つめ直すには、ドライブレコーダーの映像分析や安全運転に関する講習会に参加する、家族や同乗者から運転に関するフィードバックをもらうなどが有効です。
安全行動を過信せず、常に謙虚な気持ちで運転に臨むことがリスクホメオスタシスを克服し、安全運転を継続するための重要なポイントです。
リスク補償理論との違いとは|誤解しやすいポイントを解説

リスクホメオスタシスと似た概念に『リスク補償理論』があります。
どちらも安全対策が事故の減少につながらない点で共通していますが、リスク補償理論のメカニズムには重要な違いがあるので注意が必要です。
ここでは、それぞれの理論を詳しく解説し、混同しやすいポイントを明確にしていきます。
リスク補償理論とは
リスク補償理論は安全対策によってリスクが減少した分、ほかの行動においてリスクを取るようになるなど、安全性向上によって生まれた「余裕」を別の形で消費してしまうことです。
例えば、以下のような例が挙げられます。
- 慣れ・習慣:運転免許を取得したばかりの頃や初めて通る道路では安全運転を心がけるが、運転への慣れや毎日通る道路では、安全確認を怠ってしまいがちになる。
- 車の安全機能:衝突軽減ブレーキや車線逸脱警報などの安全機能が搭載された車を運転するようになると、ドライバーは「もしもの場合は安全機能が作動する」と安心し、注意力が散漫になったり無理な運転をしたりするようになる。
安全対策が施されたにもかかわらず、かえって危険な行動を誘発し、事故のリスクを高めてしまう可能性があります。
リスクホメオスタシスとリスク補償理論
リスクホメオスタシスとリスク補償理論は、どちらも人がリスクに対して何らかの行動変化を起こす点で共通していますが、それぞれ理由が異なります。
リスクホメオスタシスは人が『目標とするリスク水準』を維持しようとする心理に基づいており、安全性が向上するとその分だけリスクを取る行動を増やし、結果的にリスク水準を一定に保とうとします。
一方、リスク補償理論の考え方は、人が安全対策によって得られた余裕をほかの目的のために使うのが特徴です。
混同しやすいポイント
リスクホメオスタシスとリスク補償理論は、どちらも安全対策が必ずしも事故の減少につながらない点で共通していますが、その背景にあるリスクに対する意識には大きな違いがあります。
| リスクに対する意識 | 有効な対策 | |
| リスクホメオスタシス | 安全対策によって生まれた余裕をリスクを取る行動で埋め合わせようとする | リスク認知を高める教育やトレーニング |
| リスク補償理論 | 安全対策によって得られた余裕を意識的に別の目的に使い、リスク低減よりも時間短縮や快適性を優先する | 安全機能への過信を防ぐため、注意喚起やドライバーの意識改革 |
それぞれの違いを理解し、より効果的な安全対策を実施しましょう。
日常生活で活かせるリスクホメオスタシスとの付き合い方

リスクホメオスタシスを理解することは、日常生活における安全意識の向上に不可欠です。
ここでは具体的な対策を通じて、リスクホメオスタシスとうまく付き合い、より安全な生活を送るための方法を解説します。
安全運転支援機能を過信しない
自動車に搭載されている、さまざまな安全運転支援機能への過信は、リスクホメオスタシスにつながる可能性があります。
アダプティブクルーズコントロール(ACC)は、前の車との車間距離を自動で保ってくれる便利な機能です。
しかし、運転中に機能に頼りすぎてしまい、自分の目で前方の状況をしっかり確認しないと思わぬ危険につながることがあります。
急に別の車が割り込んできたり前の車が急ブレーキをかけたりした場合、ACCだけでは対応しきれず事故になってしまうおそれがあるため、機能に頼りすぎないことが重要です。
安全態度を改善する
安全な環境に慣れると、人は無意識のうちにリスクを冒す行動を取る傾向があります。
そのため、定期的に安全に関する知識を学び直し、安全に対する意識を高く保つことが重要です。
安全運転講習会への参加や、交通安全に関する情報を積極的に収集するなど、安全態度を改善する努力を続けましょう。
具体的には『運転前に必ず車両点検を実施する』『運転中はスマートフォンを操作しない』『疲労を感じたら休憩を取る』など、基本的な安全運転ルールの徹底が重要です。
一人ひとりが教育者になる
リスクホメオスタシスは、単に個人の習慣や意識の問題にとどまらず、社会全体で取り組むべき安全課題です。
自動車の運転では、安全機能の充実だけでは不十分であり、人の行動や心理に働きかけるアプローチが欠かせません。
そのためには、私たち一人ひとりが『安全の教育者=伝え手』として、日常の中で安全意識を育て合うことが大切です。
定期的に安全運転に関する研修を実施したり、従業員同士でヒヤリハット体験を共有する時間を設けたりしましょう。
実例を通じて『どのようなときに注意が必要か』『なぜその行動が危険だったか』といった情報をわかち合うことで、知識が行動に結びつく安全文化が育ちます。
技術と心理の両面で安全対策をする
安全な社会を実現するには、技術的な対策だけでなく、心理的な側面からのアプローチが重要です。
<技術面での対策>
近年普及している自動運転支援機能やドライバーの状態を監視するシステムは、運転中のリスクをリアルタイムで察知し、事故を未然に防ぐ効果が期待されています。
- ドライバー異常検知システム:注意力やまばたきの頻度をモニタリングし、疲労や集中力の低下を感知すると警告を出す。
- 感情認識型インタフェース:ドライバーの表情や声のトーンなどからストレス状態を読み取り、運転行動の改善を促す。
<心理面での対策>
ドライバーの安全意識を育てるための心理的なアプローチには、安全運転に関する啓発活動や教育プログラムの充実などがあります。
- 継続的な意識づけキャンペーン:テレビCMやSNS、地域イベントなどを通じて、日常的に安全を意識する仕組みを作る。
- VR(仮想現実)を活用した危険予測トレーニング:実際の交通場面を再現し、危険を事前に察知する力を養う。
- 交通心理学に基づく講習:自分の運転傾向やリスク感覚を見つめ直すことで、無意識のリスク行動を抑える。
ドライバーの意識向上が不可欠

リスクホメオスタシスを防ぐには、安全運転を心がけるだけでなく運転技術を見直し、安全への過信を避けるドライバー自身の意識を高めることが何より重要です。
定期的に安全運転講習を受けることで、自分では気づけなかった運転の癖や危険への備えを再確認でき、危険予測能力を高められます。
また、自分の運転記録を振り返ったり、ヒヤリハット体験や事故事例をほかのドライバーと共有したりなどは、日常的に安全意識を高める有効な方法です。
安全運転に対する意識低下は、乱暴な運転や交通マナー悪化を招き、業務中の事故によって企業の信頼を損なう可能性があります。
企業はドライバーが安心して働ける職場環境を整え、疲労やストレス軽減や休憩の確保、整備された車両提供など環境面からのサポートも忘れてはなりません。
ドライバーの意識向上と継続的な取り組みによって、リスクホメオスタシスの影響を抑え、より安全な社会づくりに貢献できます。
まとめ:リスクホメオスタシスを理解して安全な社会へ

リスクホメオスタシス理論は、人が感じるリスクのレベルに応じて行動を調整するといった考え方で、安全対策が進むと逆にリスクを求める行動を取る可能性があることを示しています。
自動車の安全性能が向上してもドライバーが機能に頼りすぎて危険な運転をすれば、事故のリスクは変わらないため、技術的な対策だけでなく人々の安全意識を高めることが欠かせません。
リスクホメオスタシス理論を社会全体で共有し、教育や啓発活動を通じてリスクに対する正しい認識を持つことが重要です。
リスクホメオスタシス理論を日常生活や仕事に取り入れ、一人ひとりがリスクを意識して適切な行動を取ることで、より安全で安心な社会を実現していきましょう。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /