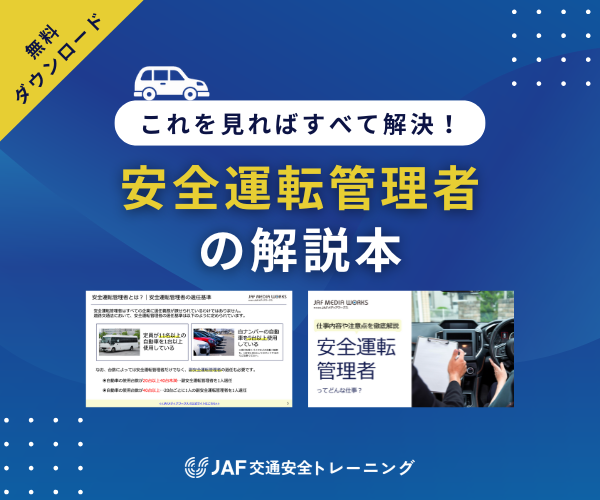ヒヤリハットとは、交通事故に至らないものの、もし対処が間違っていたら大きな事故につながりかねない状況のことを指します。
この記事では、ヒヤリハット事例の具体例や主な原因を詳しく解説し、企業が車両管理を通じてどのようにこれらのリスクを減らせるかを探ります。
安全対策を実施することで、事故を未然に防ぎ、従業員の安全を守る方法について考えていきましょう。
若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因
目次
交通ヒヤリハットとは?

ヒヤリハットとは、事故には至らなかったものの、何らかの危険な状況が発生し、事故になりうる可能性があった場面を指します。
急なできごとに「ヒヤリ」とする、「ハッ」とすることが名称の由来です。
ヒヤリハットの概念は、ハインリッヒの法則にもとづいています。
ハインリッヒの法則は、一つの重大事故の背後には29の軽微な事故と300のヒヤリハットが存在すると説明しています。
ヒヤリハットを適切に管理し学ぶことは、重大な事故を防ぐことにつながります。
出典:ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)職場のあんぜんサイト│厚生労働省
よくある交通ヒヤリハット事例

ヒヤリハットはさまざまな状況で発生します。
ここでは、日常的に遭遇する可能性のある一般的な事例をいくつか紹介し、それぞれの状況を回避するための対策を解説します。
見通しの悪い交差点で他車と接触しそうになった

住宅街を走行中、見通しの悪い交差点に差しかかったため、ドライバーは標識に従い、停止線の手前で一時停止をおこないました。
左右を確認した時点では車両や歩行者の姿は確認できなかったことから直進を開始しますが、発進直後に交差する優先道路を走る車が視界に入り、急ブレーキで接触を回避する事態となりました。
このヒヤリハット事例が起きた背景には、停止位置からの確認だけでは、交差する道路の状況を完全に把握できなかったことなどが考えられます。
見通しの悪い交差点では、停止線での一時停止だけではなく「多段階停止」を活用した、複数回にわたる安全確認が必要です。
車線変更時に隣の車と接触しそうになった

片側2車線の幹線道路を走行中、先の交差点で右折するため、ドライバーはあらかじめ右側車線への車線変更を試みました。
サイドミラーには後続車の姿が映っていなかったため、ウインカーを出してハンドルを切り始めたところ、真横に並走していた車両に気付き、あわててハンドルを戻して接触を回避する事態となりました。
このヒヤリハット事例が起きた背景には、サイドミラーの死角に隣車線の車が入り込んでいたことが考えられます。
サイドミラーやバックミラーには構造上映し出せない範囲が存在するため、必ず目視で直接安全を確認しなくてはなりません。
車に存在する「死角」を理解し、常に意識した運転が求められます。
路面が凍結してスリップ

12月の冷え込む時期、ドライバーは出勤のため早朝から車を運転していたところ、前日の雨の影響か前方の交差点付近の路面の一部が濡れており、黒っぽく見える箇所を見つけます。
交差点に差し掛かったところで信号が赤に変わり、前方の車に続いて停止しようとブレーキを踏んだものの、タイヤがスリップし、車は思ったように減速しません。
最終的には、前の車にあと数十センチという位置でようやく停止し、接触事故は免れました。
このヒヤリハット事例が起きた背景には、「ブラックアイスバーン」と呼ばれる薄い氷の膜が、交差点手前の路面に発生していたことが関係しています。
ブラックアイスバーンは一見濡れているだけの路面のように見えるため気付きにくく、ブレーキやハンドル操作が効かなくなることで、停止位置を超えて進んでしまうなどの危険を引き起こします。
あらかじめブラックアイスバーンが発生しやすい場所や条件を知り、速度を落とす、車間距離を取るといった対策が必要です。
参考:路面は黒いけど、止まれない!「ブラックアイスバーン」とは…?|一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
居眠り運転

高速道路を走行中、長い直線区間に差し掛かりました。
周囲の交通量は少なく、一定の速度での走行が続いていたこともあり、次第に眠気を感じ始めてしまいます。
ドライバーはラジオを流すなどして眠気を覚まそうとしたものの、それでも一瞬目を閉じてしまっていたことに気づき、ハッと慌てて姿勢を立て直しました。
幸い、車線逸脱などには至らず事故は防げましたが、あと数秒反応が遅れていたら重大事故につながっていた可能性もありました。
このヒヤリハット事例の背景には、高速道路特有の単調な運転環境が関係しています。
高速道路は信号や交差点もなく、景色の変化にも乏しいことから、注意力が散漫になりやすい環境です。
眠気や集中力の低下を感じた時は、無理をせずサービスエリアやパーキングエリアで早めに休憩を取り、その際には車外に出て体を動かすなどの対策が必要です。
ブレーキペダルから足が離れて前進

コインパーキングから出庫する際、ドライバーは精算機の位置に車を寄せ、シフトをドライブに入れたままブレーキを踏んで停車しました。
窓を開けて駐車券を差し込み、料金を支払った後、お釣りを取ろうと体を前に動かした瞬間、無意識にブレーキから足が離れ、車がゆっくりと前進。
すぐに異変に気付き、ブレーキを踏み直したことで、接触事故には至りませんでしたが、ゲートバーなどへ衝突寸前となる状況となりました。
このヒヤリハット事例の背景には、精算操作に集中するあまり、ブレーキ操作への意識が一時的に途切れてしまったことや、ペダルを踏んだまま無理な体勢を取ったことなどが関係しています。
精算機での操作中は、シフトを必ず「P(パーキング)」または「N(ニュートラル)」に入れ、サイドブレーキをかけるようにしましょう。
悪天候による視界不良

ある日の夕方、業務を終えて帰社する途中、雨脚が強まってきたため、ドライバーはワイパーを作動させながら走行していました。
前方の視界が悪化する中、運転を続けていたところ、視界の端に動く気配を感じ、反射的に急ブレーキを踏んで停車します。
停止後によく見ると、そこには信号機の無い横断歩道があり、傘を差した歩行者がすでに渡り始めていたのです。
幸い、ブレーキが間に合い接触には至りませんでしたが、状況次第では重大事故に発展しかねない、危険な場面でした。
このヒヤリハット事例の背景には、強い雨と夕方の薄暗さによる視界の悪化などが関係しています。
雨天・薄暮時は、速度を抑えたり、早めにヘッドライトを点灯させたりして、歩行者の存在はもちろん、道路標識や路面表示を見落とさないようにすることが重要です。
JAF交通安全トレーニングでは、このようなヒヤリハット事例をケーススタディ形式で学べる教材を多数ご用意しています。
従業員に実践的な交通安全教育を実施したいとお考えの方は、JAF交通安全トレーニングの利用を検討してみてください。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /
交通ヒヤリハット事例の主な原因とは

ヒヤリハットを引き起こす3つの要因
ヒヤリハット事例は、さまざまな要因によって引き起こされます。
大きく分けると、「人的要因」「車両・設備の要因」「環境要因」の3つに分類されます。それぞれの要因を詳しく理解することで、より的確で効果的な予防策を講じることが可能になります。
- 人的要因
人的要因は、ヒヤリハット事例の中で一般的な原因の一つです。
運転中の注意散漫が原因で反応が遅れる事例、疲労が蓄積された状態での運転による判断ミス、そして自身の運転技能への過信から生じる危険な運転が含まれます。
また、心身の不調も運転に大きく影響するため、健康状態に気を配ることもヒヤリハット対策の一つといえます。 - 車両・設備の要因
ドライバーだけでなく、車の状態もヒヤリハットに大きく影響します。
車両の定期的な点検を怠ると、ブレーキの不良やタイヤの摩耗など、安全性に直結する問題を見過ごすことになりかねません。
事故のリスクを避けるためにも、日常的に車両の点検をおこないましょう。 - 環境要因
雨、霧、雪などの悪天候時は視界が悪化し、ドライバーがほかの車両や障害物を見落としやすくなるため、ヒヤリハット事例につながりやすい状況です。
また、滑りやすい路面など、路面の悪条件は車両のコントロールを困難にし、予期せぬ動作を引き起こすことがあります。
さらに、渋滞や交通の混雑はドライバーにストレスを与え、乱雑な運転や危険な追い越しを促し、衝突や事故のリスクを高めます。
悪条件での運転を極力避けられるよう、ゆとりを持った運行計画を立てることが大切です。
企業が取り組むべき従業員への交通ヒヤリハット防止対策
企業においてヒヤリハットを最小限に抑えるためには、具体的な対策の実施が不可欠です。
ここでは、効果的な対策方法をいくつか紹介します。
社内での仕組みづくり
- ヒヤリハット事例を集めて共有する
社内で発生したヒヤリハット事例を収集・共有し、全社的な安全対策に活かすことが重要です。その際、報告者に責任を問わない姿勢を明確にすることで、安心して情報を共有できる環境を整えることが必要です。
- 社内制度の整備
ヒヤリハット報告を促進する社内制度の整備も欠かせません。報告書の簡素化や定期的な共有の時間を設けることで、情報共有が活性化し、安全意識の向上につながります。
ドライバーに対する施策
- 安全運転教育
安全運転教育は、ヒヤリハット事例の予防に不可欠な取り組みです。
外部の講習や最新の学習教材を活用して、従業員に対して定期的な安全運転教育を提供しましょう。
交通安全に関する知識を深めるためには、JAFが提供するeラーニング教材JAF交通安全トレーニングなどの外部学習リソースを活用するのもおすすめです。
従業員が自分のペースで学習を進められるため、忙しい業務の中でも継続的に受講が可能です。
定期的に安全運転教育を受けることで、従業員の安全意識を持続的に向上させ、結果として交通事故のリスクを効果的に減らすことが期待できます。 - ドライバーの健康管理とメンタルケア
従業員の健康管理とメンタルケアも重要な要素です。定期的な健康診断や適切な休息の確保を通じて、ドライバーが常に万全な状態で業務にあたれる環境を整えることが、事故の未然防止につながります。
車両に関する施策
- 安全に配慮した社用車の選定
ヒヤリハット事例を減らすためには、社用車を選定する際も安全性を十分に考慮したいところです。
自動ブレーキシステムや車線維持支援システムなど、先進の安全技術を備えた車両を企業が導入することで、運転中の潜在的なリスクを大幅に軽減できます。
安全技術を備えた車両の選定は、企業の安全対策の一環として極めて有効です。 - 定期的な車両の点検
最後に、車両の定期点検も忘れてはなりません。ブレーキなどに不具合があると、どれだけ注意していても事故につながる可能性があります。安全な運行のために、日常的な点検を徹底しましょう。
日常点検整備の手順やポイントをまとめた資料を無料で配布しています。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
\ 今すぐ使えるチェックシート付 /
ヒヤリハット発生防止のためドライバーが気を付けるべきポイントとは

ヒヤリハットは、いつどこで起こるかわかりません。
特に、日常的に運転をしていると、慣れによって注意が散漫になることがあります。
ヒヤリハットを防ぐための気をつけるべきポイントをご紹介します。
ながら運転をしない
ながら運転は非常に危険で、事故のリスクを大幅に高めます。
運転中に他の作業をおこなうと、注意力が分散し道路状況の変化に対応できません。
スマートフォンの操作をはじめ、飲食や書類の整理といったことも運転中はおこなわないようにしましょう。
参考:運転中スマホ利用の罰則強化|違反点数や罰金・事故事例など徹底解説|JAFトレコラム
交通ルールを守る
交通ルールを守ることは、交通安全の基本です。
速度制限や車間距離を守ることで、多くのヒヤリハットを回避できます。
特に信号無視や一時停止違反などは、重大な事故につながります。
ルールを守ることは自分自身だけでなく、他のドライバーや歩行者の安全のためにも不可欠です。
天候や時間帯に応じた運転をする
雨天時や夜間などは視界が悪く、ヒヤリハットも起きやすいため、天候や時間帯に応じた運転が重要です。
視界が悪いときは、車間距離を十分にとったり状況に応じてハイビームを活用したりなど安全に配慮しましょう。
状況に応じた運転が、交通事故のリスクを減らします。
参考:安心安全な冬の運転を実現するために|積雪・凍結路面対策を徹底解説!|JAFトレコラム
時間と心に余裕を持つ
焦りは判断力を鈍らせ、危険な運転につながります。
特に時間に追われると、無理な運転や判断ミスを引き起こしやすくなります。
例えば、急いでいるときに、黄色信号で強引に進行したり、車間距離を詰めすぎたりなどです。
運行計画を立てて出発時間に余裕を持ち、落ち着いた状態で運転しましょう。
もしも事故をおこしてしまったら?対応をおさらい

もしも交通事故を起こしてしまった場合は、冷静かつ適切な対応が求められます。
交通事故発生時の基本的な対応手順をご紹介します。
交通事故発生時の対応手順
- 安全確保
まず最優先すべきは、負傷者の救護です。
負傷者がいる場合は応急処置をおこない、必要に応じて救急車を呼びます。
また、車を安全な場所に移動させハザードランプを点灯させるなどして、二次事故を防ぎましょう。 - 警察への通報
つづいて警察に通報してください。
警察官が事故の状況を確認・記録します。
軽微な事故であっても、警察に通報する必要があるので気をつけましょう。
出典:道路交通法第七十二条|e-GOV法令検索 - 相手方との情報交換
事故の相手がいる場合は、以下の情報を交換しておきます。
・氏名住所
・連絡先
・車両ナンバー
・保険会社
口頭ではなく、免許証などを確認し確実にメモしておきましょう。
また、目撃者がいる場合は、氏名や連絡先を聞いておくことも大事です。 - ロードサービスの手配
車両が走行不能になった場合は、JAFなどのロードサービスを手配します。
ロードサービスではレッカー移動や応急処置などを受けられます。
ロードサービスの連絡先を車内に保管するなど、いつでも連絡できるようにしておきましょう。
参考:JAFを呼ぶ|一般社団法人日本自動車連盟(JAF) - 保険会社への連絡
事故発生後、できるだけ早く自身の加入している保険会社に連絡しましょう。
保険会社は適切な対応方法のアドバイスや、必要な手続きをサポートしてくれます。
事故現場の写真や目撃者の証言など、できるだけ多くの情報があると保険請求がスムーズに進みます。
トラブル防止のために、交渉は個人間でおこなわず、保険会社に任せましょう。
従業員が交通事故を起こした際の企業の責任
従業員が交通事故を起こした際の企業の責任は主に以下の2つがあります。
- 使用者責任:従業員が業務遂行中に起こした事故について、企業が損害賠償責任を負う
- 運行供用者責任:企業が所有する車両による事故の場合に企業が損害賠償責任を負う
企業はこうした責任も負うため、従業員への安全運転教育が欠かせません。
JAF交通安全トレーニングでは、日常の運転で起こりやすいヒヤリハットの場面をケーススタディ化しており、実車を用いたドライバー目線の再現動画などから実践的に学習いただけます。
実際に起こっている状況に近い環境や危険を追体験することで、従業員一人ひとりの危険感受性を高めるとともに、「自分にも起こりうること」として強く認識していただくことが可能です。
出典:民法第七百十五条|e-GOV法令検索
出典:自動車損害賠償保障法第三条|e-GOV法令検索
まとめ:交通ヒヤリハット事例を学び事故防止に活かそう

本記事では、交通におけるヒヤリハット事例の多様な原因と、それに対処するための企業向けの具体的な対策について解説してきました。
企業が主体的にヒヤリハット対策を講じることは、ドライバー一人ひとりの安全意識を高めるだけでなく、組織全体のリスクマネジメントの質を向上させる重要な取り組みです。
安全な企業文化の醸成は、信頼性の高い企業イメージの構築にもつながります。
また、継続的な交通安全教育を実現する手段として、JAF交通安全トレーニングなど、eラーニング教材の活用も効果的です。
自分のペースで学べるeラーニングは、忙しい現場でも取り入れやすく、安全意識の定着と継続に大きく貢献します。
ヒヤリハットを「未然に防げるリスク」として捉え、企業として計画的かつ継続的な安全対策を推進していきましょう。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /