企業における交通安全教育は、従業員と社会全体の安全を守るために不可欠です。
交通事故は、従業員だけでなく企業の社会的信用を大きく損なう可能性があるため、交通安全教育を積極的に導入し、従業員の安全意識を高めなくてはなりません。
この記事では、企業が交通安全教育を実施する理由やメリット、具体的な教育方法、資料・教材の選び方などを詳しく解説します。
eラーニングを活用した効果的な教育方法に焦点を当て、企業が抱える課題についても紹介しているので、ぜひ交通安全教育の導入にお役立てください。
安全運転意識を高める教育手法・教材がわかる!
目次
安全運転のための教育を実施する理由

企業が交通安全教育を実施する理由は業界・業種を問わず、運転免許を持つすべての人を対象に安全運転意識を向上させ、交通事故や交通違反を防ぐためです。
安全運転の教育とは
交通安全教育とは、自動車の運転に対する基礎的な知識に加え、交通マナー・交通ルールの学習と交通安全意識の向上を目的としたものです。
毎年内閣府から発刊されている交通安全白書では、交通安全教育について以下のように記載しています。
交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、他の人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を有している。
一般的に、交通安全教育は子どもや新人ドライバーが対象と考えられがちですが、実際には社会人も含まれています。
実際に自動車を管理する企業やドライバーにとっては、安全運転の教育は安全な社会生活を送る上でも重要です。
企業が交通安全教育をおこなう背景
企業が交通安全教育をおこなう背景には、業務中の交通事故が労働災害の中でも大きな割合を占めている現状があります。
交通事故は運輸業界に限らず、さまざまな業界で死亡事故が発生しており、決して軽視できないリスクです。
第三者を巻き込む可能性もあり、社用車での事故が発生した場合は企業の管理責任が問われ、企業イメージや信頼の低下につながる恐れもあります。
多くの企業では、リスクマネジメントの一環として従業員に対する交通安全教育を積極的に実施し、事故や違反の防止への取り組みが重要視されるようになりました。
企業・団体が実施する交通安全教育の重要性
企業は従業員と道路利用者の安全確保が社会的責任であり、事故減少は企業のリスク軽減にもつながります。
2022年の1年間では約30万件の交通事故と36万人の死傷者が発生しており、そのうち、約40%が業務中や通勤・通学時の事故であると言われています。
政府は交通事故死者数減少を目標とし、企業も交通安全教育を積極的に実施して事故防止と安全意識向上に努めることが重要です。
※1出典:交通安全対策|政策統括官(共生・共助担当) – 内閣府
安全運転の教育で取り組むべき課題

実際に交通安全教育を実施するなら、複数の課題に取り組まなければなりません。
いずれの課題も、交通安全教育において優先的に取り組まれるものです。
効果的な交通安全教育を実践する上でも、しっかりと把握しましょう。
安全運転5則を守る
1980年に警視庁が提唱した安全運転5則は、安全運転の基本的な知識です。
安全運転を徹底するために『安全運転5則』を意識しましょう。
1.安全速度を守る
安全速度は法定速度だけでなく、天候や道路状況に応じた調整が必要です。
人通りの多い場所や見通しの悪い交差点では、速度を落として安全運転を心がけましょう。
2.カーブ手前で減速する
カーブに入る前には十分にスピードを落とし、歩行者の飛び出しや車両の制御不能を防ぎましょう。
3.交差点での安全確認
交差点は、交通事故が発生しやすい場所です。
ヒヤリハットマップを活用して注意すべき交差点を共有し、事故防止に努めましょう。
4.一時停止で歩行者を優先する
信号のない横断歩道で歩行者がいる場合、一時停止が必要です。
JAFの調査によると、信号のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている際に、一時停止した車は全体の53.0%でした。
歩行者がいる場合は一時停止が必要であり、安全運転の意識向上が求められます。
5.飲酒運転をしない
アルコールは判断力を低下させ、重大事故を引き起こす可能性が高まります。
企業は業務中だけでなく、プライベートでも飲酒運転の防止を徹底し、アルコールチェック体制を整えましょう。
運転モラルの向上
運転モラルとは、交通法規を遵守し、事故防止のために慎重な運転を心がける意識です。
交通安全教育において、運転モラルの向上は交通法規や安全運転の重要性を再認識する重要な課題として扱われます。
どれだけ優れた運転技術を有していても、ルールを守り、安全を重視する意識がなければ事故を起こすリスクが生じるため、ドライバーが安全運転の意義を理解し、事故防止の取り組みを継続する上でも、運転モラルの向上・維持は欠かせません。
運転モラルの向上・維持は、従業員が安全運転の重要性や、危険運転のリスクなどをより深く理解する上で役立つ課題であり、継続的な取り組みが必要です。
とりわけマイカー通勤をおこなっている企業にとって、運転モラルの向上は事故や違法行為のリスクを回避する上で重要です。
交通安全教育を通じ、ルールやモラルを啓発しましょう。
ヒューマンエラーの防止
ヒューマンエラーの防止も交通安全教育で取り組むべき課題です。
ヒューマンエラーの定義はさまざまありますが、国土交通省によると以下のように定義されています。
人と機械が協同して目的を達成するためのシステム(ヒューマンマシンシステム)の中で、人が自分に割当てられた仕事あるいは人(運転者)に期待されたパフォーマンスの水準を満たすことに失敗したため、システム全体がトラブルを起こしたり、システムダウンになったもの
同ガイドラインによると、交通事故には何らかの形でヒューマンエラーが関与していることが少なくないとしています。
最近の自動車は優れた安全機能が搭載されていますが、人間が運転する以上、ヒューマンエラーはつきものです。
ヒューマンエラーは運転技術の優劣にかかわらず、ドライバーの精神状態や状況によって発生します。
ヒューマンエラーを防止するためには、ヒューマンエラーが発生する原因や、運転中の危険を予測し回避する方法を学ぶことが重要です。
また、「ヒヤリハット」と呼ばれる運転中のアクシデントに対し、シミュレーションしながら対処方法を学ぶ取り組みも定番です。
交通安全教育を継続する体制の構築
交通安全教育は、実施したとしても時間の経過とともに効果が薄れるため、継続して実施しなければ効果はありません。
したがって、企業側の体制の構築も、取り組まなければならない課題です。
一方で、担当者個人だけでは体制の構築・維持は困難なため、企業が一丸となって交通安全教育を実施する組織やルールを作る必要があります。
さらに企業全体で取り組めば、より効果的な交通安全教育の実施が可能です。
企業で交通安全教育を実施するメリット

企業で交通安全教育を実施すれば、さまざまなメリットが得られます。
交通安全教育は従業員本人の安全はもちろん、さまざまなリスク対策にも有効です。
交通事故が発生するリスクの低減
企業で交通安全教育を実施することで、交通事故の発生リスクを抑えられるようになります。
交通事故の要因には、前方不注意や安全不確認などのヒューマンエラーによるものも含まれます。
交通安全教育を通じて従業員の安全運転に対する意識が向上すれば、要因の一つを改善できるため、交通事故の低減につながるでしょう。
ただし、従業員の意識向上はすぐに効果が出るものではありません。
そのため、しっかりと効果を得るために、長い時間をかけて定期的に実施し続ける必要があります。
事故処理で発生するコストや損害の削減
事故が発生すると修理代や損害賠償、調査委員会の発足、再発防止案の策定など、企業にとって多大なコストと労力がかかります。
交通安全教育の実施により事故を未然に防ぎ、交通事故による不要なコストや損害を削減できます。
企業のイメージアップ
交通安全教育の実施は、ステークホルダーからの評価や企業のブランドイメージの向上などの企業のイメージアップにも効果的です。
近年の企業は、「業績を上げているか」だけでなく、「社会的責任(CSR)を果たしているかどうか」も評価軸の一つとなっています。
そのため、交通安全教育の実施を通して、従業員の安全や健康を大切にしている点や地域の安全にも配慮している点を周囲に示すことで、企業イメージの向上につながります。
運転マナー違反のSNS拡散の防止
近年は、SNSによって運転マナー違反が拡散されるリスクが高まっています。
業務中の運転マナー違反が第三者に撮影される可能性は決して低くありません。
万が一、スピード違反や交通違反がSNSに拡散される事態になれば、企業のブランドや信頼を毀損する事態を招きます。
交通安全教育を実施する際は、勤務中はもちろん、プライベートでも運転マナー違反を防ぐように呼びかけましょう。
交通安全教育の種類とeラーニング効果

交通安全教育は対象者によって種類が変わります。
交通安全教育は受講対象者によって重視するポイントが異なるので、それぞれの違いについて正確な理解が重要です。
一般社員研修
一般社員研修は、日常的に運転する従業員を対象とした交通安全教育です。
主な目的は運転技術の見直しと安全確認の徹底で、運転のクセを修正し、死角や危険ポイントの確認を習慣化させることを目指します。
雨天や雪道など特定の環境を想定した実践的なトレーニングや、企業の業務内容に応じて研修内容をカスタマイズできるのが特長です。
例えば、「JAF交通安全トレーニング」では、安全運転の知識やドライバーの社会的責任について学べる教材が用意されており、企業の安全意識向上に役立ちます。
新入社員研修
新入社員研修は、運転経験の浅い新入社員を対象とした研修です。
免許を取得して間もないため、運転技術や危険予知能力が十分でないことが多く、基礎的な運転技術や交通ルールを重点的に学びます。
新入社員研修は、適切な研修で業務中の運転には責任が伴うことを理解し、事故を防止するだけでなく社会人としての自覚を育む機会にもなります。
事故惹起者研修
事故惹起者研修は、過去に交通事故を起こした従業員を対象とした研修です。
事故の原因は運転技術だけでなく、運転のクセや心理的な要因にもあるため、研修では事故の振り返りやカウンセリングを実施しています。
交通事故の再発防止には自身の運転傾向を把握し、注意すべき点の改善が重要です。
管理者研修
管理者研修は、社用車の管理や従業員の指導を担当する管理者向けの研修です。
安全運転指導の方法や交通安全に関する知識を学び、企業全体の安全意識を高めることを目的としています。
企業によっては、交通安全を推進するための組織体制の構築方法を学ぶ研修もあります。
e-ラーニングと効果
近年、eラーニングはパソコンやスマートフォンを活用し、時間や場所を選ばずに学習できる手軽な方法として注目されています。
従来の集合研修と比べ、以下のようなメリットがあります。
- 教育機会の拡大:業務の合間など、好きなタイミングで学習できる
- コスト削減:講師の派遣や会場手配が不要
- 教育の均一化:すべての従業員が同じ内容を学べる
繰り返し学習が可能で理解度が深まり学習意欲の維持にもつながるため、多くの企業がeラーニングを導入し、効果的な交通安全教育を実施しています。
交通安全教育の指導方法とeラーニング効果
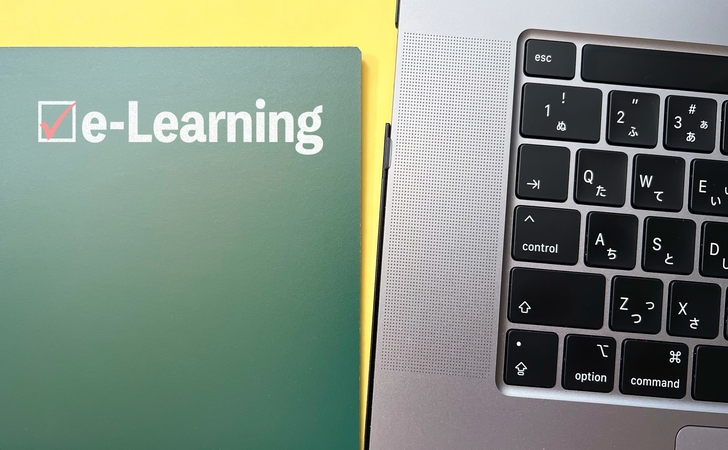
企業が実施できる交通安全教育にはさまざまな方法があるので、それぞれの特性を理解し、企業の状況に合わせて活用しましょう。
集合講座
集合講座はスタンダードな指導方法です。
複数の対象者を集め、管理者や外部から招いた講師が指導するケースが多い一方、企業によっては従業員だけでグループディスカッションをおこなう場合もあります。
集合講座は複数の対象者に交通安全への共通認識を持たせやすいうえに、従業員を多数集めれば緊張感のある講座を実践できます。
ただし、複数の従業員を対象にするため、スケジュール調整が難しい点に注意しましょう。
また、集合講座は効果が一過性になりやすいため、定期的に開催する必要があります。
マンツーマンの運転指導
より実践的な交通安全教育を実施するなら、現場でおこなうマンツーマンの運転指導がおすすめです。
外部の講師やベテランの従業員による指導なら、より質の高い研修が実現します。
マンツーマンによる指導は、職業ドライバーを抱える企業で多く実践されています。
実際の走行ルートや社用車を使った研修もできるため、普段と変わらない感覚で指導を受けられる点もメリットです。
しかし、マンツーマンは指導内容が担当者によって変わるなど、属人化しやすい傾向があるため、指導内容の均一化が難しくバラつきが出るリスクがある点には注意しましょう。
加えて、マンツーマンだと複数人を対象にできないため、従業員数が多い企業だと実施しにくい傾向があります。
警察や教習所での講習と実技演習
教習所が実施する交通安全教育なら、実際に教習所で実技演習を受けられる場合があります。
運転のプロである教習所の教官であれば、より専門的な内容の研修を受けられます。
教習所が所有する設備を活用できたり、さまざまなプランで対応できたりするため、企業の実情に合わせた研修が可能です。
ただし、教習所での実技演習は多人数での受講には不向きであり、スケジュールの調整に手間がかかる可能性があります。
警察署で実施している安全運転管理者等講習の費用は、5,100円分の収入証紙が必要です。
また、教習所で実施されている企業安全運転研修の費用相場は、次の通りです。
| 時間・コース | 費用相場(1名あたり) |
| 2時限コース | 12,000円〜15,000円 |
| 3時限コース | 20,000円〜25,000円 |
| 4時限コース | 25,000円〜30,000円 |
| 6時限コース | 50,000円〜 |
| 8時限コース | 70,000円〜 |
ヒヤリハットの周知
ヒヤリハットの周知はグループディスカッションに近い指導方法です。
従業員同士で過去の経験や、業務で使うルートの危険情報などを共有し、意識の向上を目指します。
ヒヤリハットを周知する際は、共有した情報を報告書に記載したり、情報を網羅したマップを作成したりすると有効です。
ヒヤリハットの周知では交通安全意識を共有し、管理者が現状を把握できるので、新たな課題を発見できる可能性もあります。
資料の配布
企業が加入している保険会社や、教習所などから配布された交通安全に関する資料の配布も交通安全教育に役立てられます。
手元に資料があれば、任意のタイミングで読み返せるため、業務の合間で知識を学べる点がメリットです。
しかし、企業側から学習状況をコントロールできないため、従業員によって習得度にバラつきが生じるリスクがあります。
eラーニング効果
eラーニングはオンラインで自発的に研修を受講させる指導方法です。
eラーニングなら時間・場所を選ばないため、効率よく継続的な交通安全教育を実現できます。
交通安全教育の担当者にとっても、進捗状況を可視化できるeラーニングなら管理が簡単です。
eラーニングのおすすめ教材として、「JAF交通安全トレーニング」があります。
JAFが長年培った交通安全ノウハウを配信しており、社用車を運用する企業はもちろん、通勤に車を使用している方が多い企業にもおすすめです。
安全運転意識を高める教育手法・教材がわかる!
交通安全教育を実施する際のポイント

交通安全教育をより効果的にするには、いくつかのポイントがあります。
ここでは、安全運転を心がけるために必要なポイントを確認しましょう。
運転に集中できる環境を整える
交通安全教育では、運転に集中できる環境を整える重要性をしっかりと伝えましょう。
業務中の運転では進捗確認や取引先との連絡など、予期せぬ業務が発生する場合があり、対応に気を取られて運転ミスや交通違反のリスクが高まります。
従業員には以下の対策を徹底するよう指導しましょう。
- スマートフォンはドライブモードに設定し、運転中の通知や着信を防ぐ
- 必要な作業は安全な場所に停車してからおこなう
新入社員や運転経験の少ない従業員は、リスク管理が不十分な場合が多いため、より丁寧な指導が必要です。
実際の運転シミュレーションや具体的な事例を交えた研修を実施し、安全意識の向上を図りましょう。
実際の走行ルートを利用する
交通安全教育で自動車を運転するなら、実際の走行ルートを利用しましょう。
実際に利用する走行ルートで運転すれば業務中の運転をイメージしやすくなり、ポイントを体験しながら、リスクをより強く意識できます。
実際の走行ルートで実技演習を重ねれば、業務への適応も早く進められます。
従業員の運転特性に合わせた内容にする
従業員の運転特性に合わせた、交通安全教育の内容調整が重要です。
同じ従業員でも、新入社員・ベテランドライバー・事故惹起者では運転の技量や経験が大きく異なります。
従業員の技量や経験に合わせて、交通安全教育の内容を適宜調整すれば、より効果的な指導を実現できます。
また、マンツーマンの指導などをおこなう際は、従業員の性格や傾向に合わせましょう。
「運転中だと焦りやすい性格」「運転に不慣れで緊張しやすい性格」など、従業員のパーソナリティに合わせた指導で、技量の向上につながります。
定期的に実施する
交通安全教育は一過性で終わらせるべきものではありません。
一時的に交通安全教育を実施しても、従業員に交通安全意識を定着させることは困難です。
定期的に実施し続けることで、従業員の意識や運転技術の向上を実現できます。
JAFトレが毎月配信している教材を活用し、毎日少しずつでも受講して安全意識の向上と維持を継続しましょう。
身体能力や判断力の変動に合わせた交通安全教育をおこなえば、加齢に伴う運転ミスのリスクを予防できます。
マニュアルを作成する
交通安全教育を効果的に実施するためには、マニュアルの作成も重要です。
マニュアルを作成することで、教育内容の均一化と質の担保が可能となり、誰が担当しても一定水準の教育ができるようになります。
具体的に記載する内容としては、以下のような内容が考えられます。
- 社用車の取り扱い
- 運転中のNG行動
- 運転中に特に注意すべきポイント
- 日常点検整備・定期点検整備の実施方法
- 事故発生時の対応
また、過去の事故事例や危険カ所の情報なども記載しておくと、従業員はより具体的な危険を認識できるためおすすめです。
使いやすい教材や資料を用意する
自社の業務内容や従業員数に合わせて、使いやすい教材や資料を用意することも重要なポイントです。
例えば、実際の事故事例を再現した映像を教材として用いれば、危険性をよりリアルに実感し、安全意識の向上につながります。
また、イラストや図を多用していたり、テストが用意されていたりする教材であれば、従業員の理解度を高めるのに役立ちます。
以上のように、使いやすい教材や資料を用意することで、従業員は学習に集中でき、交通安全に関する知識や意識を効果的に定着させられるでしょう。
安全運転意識を高める教育手法・教材がわかる!
実技講習の環境を整える
実技講習をおこなう際は、安全で適切な環境の確保が重要です。
- 業務で使用するルートを活用する
- 受講者の運転特性に合わせた指導をおこなう
- 危険を回避できるようシミュレーションを取り入れる
おすすめの安全運転教材とeラーニング効果

交通安全教育には、実際の運転環境に合わせた教材が不可欠です。
JAFは、実際の運転シーンに基づいた教材動画や資料を提供し、駐車場から高速道路まで、さまざまな場面に対応しています。
| 場所別 | ・駐車場:バックや出発時の事故防止 ・生活道路:歩行者への注意、狭い道での運転 ・幹線道路:車間距離、車線変更の注意 ・高速道路:速度管理、疲労対策 |
| 利用者別 | ・バイク:視認性向上、安全装備 ・自転車:車道走行、夜間ライト ・歩行者:横断歩道、歩行者優先 |
| 環境別 | ・夜間:ライト使用、疲労対策 ・雨天:タイヤ管理、速度調整 ・降雪:チェーン装着、雪道運転 |
JAF交通安全トレーニング(法人向け)
「JAF交通安全トレーニング」は、パソコンやスマートフォン、タブレットでの受講が可能なeラーニング形式の教材です。
JAFの交通安全ノウハウが毎月配信されるため、継続的に学べます。
リアルな運転シミュレーションやケーススタディを通じて、従業員は危険予知や事故回避のスキルを深められます。
一般的な3分間のトレーニング教材には管理機能が備わっていない場合が多く、受講者の学習状況を把握することが難しいです。
一方、JAFが提供する「JAF交通安全トレーニング(JAFトレ)」は、管理者が受講者ごとの学習履歴や学習傾向を確認できる高度な管理機能を搭載しています。
従業員一人ひとりの進捗状況を可視化し、適切なフィードバックや追加指導が可能です。
また、JAFトレは毎月新しい交通安全教材をeラーニング形式で配信し、継続的な学習をサポートします。
JAFトレは企業の交通安全教育において、従業員の安全運転意識を高め、事故防止に寄与する効果的なツールとして活用されています。
JAFのeラーニング効果
JAFのeラーニングプログラムは、JAFが長年培ってきた交通安全の知見とノウハウを活かし、オリジナル教材をeラーニング形式で提供しています。
受講者は隙間時間を利用して学習でき、教材は毎月配信されるため、継続的な学習が可能です。
管理者は受講者の学習状況を可視化し、効果的な指導で企業や団体の安全運転管理を強力にサポートしています。
安全運転意識を高める教育手法・教材がわかる!
eラーニングを活用した安全運転教育の取り組み例

JAFは長年にわたり交通安全啓発に取り組んできたため、豊富な知見を活かした多彩なコンテンツを提供しています。
『JAF交通安全トレーニング』は、管理機能を備え、受講者の学習状況を把握しやすいため、企業の交通安全教育に最適です。
継続的な学習を支援する教材も充実しており、従業員の安全意識向上に貢献します。
詳しくは、こちらの記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。 Diamondオンライン
まとめ:安全運転の教育とeラーニング効果で事故から企業を守ろう

交通安全教育は、交通安全意識を高め、将来の事故を防ぐ上で有効な手段です。
交通事故は、従業員の生命を脅かすだけでなく、企業の社会的信用や経済的損失にもつながりかねないため、交通安全教育を徹底する必要があります。
交通安全教育は、従業員の交通安全意識を高め、事故リスクを低減する効果的な手段です。
特に、eラーニングを活用すれば、時間や場所を選ばずに効率的な教育が可能となり、従業員の理解度向上や定期的な学習にも役立ちます。
運送・運輸業界に限らず、業務で自動車を使用するすべての企業にとって、交通安全教育の実施は不可欠です。
交通安全教育を実施するには、eラーニングの活用や、定期的な教育プログラムの見直し、JAFのような専門機関の教材を活用すれば、効果的な対策が講じられます。
積極的に取り入れ、安全な企業文化を築いていきましょう。
安全運転意識を高める教育手法・教材がわかる!




















