近年、交通ルールの法改正ついての話題が増えています。
しかし、「具体的に何が変わるのか」「いつから施行されるのか」など、詳しい情報がわかりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2026年の法改正によってどのように交通ルールが変わるのか、その背景や目的を解説します。
事前に交通ルールの変更点を知り、社内への周知を徹底し、適切に対応できるようにしておきましょう。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /
目次
2026年法改正1:生活道路での法定速度引き下げ

2026年の法改正では、生活道路での法定速度が大きく変わります。
生活道路での制限速度が30km/hに引き下げられる
「生活道路」とは、センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5m以下の狭い道路のことです。
2026年9月から、生活道路の法定速度を30km/hに引き下げる改正道路交通法が施行される予定です。
これは、従来の法定速度である60km/hからの大幅な引き下げとなります。
なお、生活道路においては、これまでも「ゾーン30/ゾーン30プラス」の取り組みがおこなわれてきました。
「ゾーン30/ゾーン30プラス」とは、生活道路における歩行者などの安全な通行を確保するために、区域を定めて30km/hの制限速度を設ける取り組みです。
2026年9月の法改正は、「ゾーン30/ゾーン30プラス」とは異なり、一般道路の多くで制限速度が30km/hに引き下げられます。
法改正の背景
今回の法改正の背景は、生活道路における交通事故のリスクが高いことです。
警察庁のデータによると、交通事故死者数全体の約半数が歩行中または自転車乗車中に発生しており、そのうち約半数が自宅から500m以内の身近な場所で発生しています。
また、生活道路における歩行者・自転車乗用中の死傷者数が占める割合は、道路幅5.5m以上の道路の約1.8倍というデータもあります。
幅員別・状態別死傷者数のデータは以下のとおりです。
| 幅員5.5m未満(生活道路) | 幅員5.5以上 | |
|---|---|---|
| 自動車乗車中 | 41.9% | 64.2% |
| 自動二輪車乗車中 | 6.4% | 6.7% |
| 原動機付自転車乗車中 | 6.4% | 3.9% |
| 自転車乗用中 | 32.0% | 15.9% |
| 歩行中 | 13.3% | 9.2% |
状態別・自宅からの距離別死者数は以下のとおりです。
| 歩行中 | 自転車乗用中 | |
|---|---|---|
| 50m以内 | 13% | 2% |
| 100m以内 | 9% | 2% |
| 500m以内 | 30% | 21% |
| 1km以内 | 15% | 22% |
| 2kim以内 | 8% | 23% |
| 2km超 | 25% | 29% |
| 調査不能 | 0% | 1% |
そのため、生活道路における安全性の向上が求められているのです。
制限速度を30km/hにした理由
生活道路の制限速度を30km/hにした理由は、自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者との衝突時に致死率が急上昇するというデータがあるからです。
具体的には以下のとおりです。
| 自動車の速度(km/h) | 歩行者の致死率(%) |
|---|---|
| 0〜20 | 0.4 |
| 20〜30 | 0.9 |
| 30〜40 | 2.7 |
| 40〜50 | 7.8 |
| 50〜60 | 17.4 |
一般的に、速度が速いほど必要な停止距離が長くなり、運転中の視野角も狭くなります。
また、事故発生時の被害も大きくなる傾向があります。
そのため、生活道路における制限速度の引き下げは、人命を守るための重要な対策と言えるでしょう。
2026年法改正2:車が自転車などの右側を通過する際のルール新設

2026年5月23日までに施行される改正道路交通法では、自動車が特定小型原動機付自転車などの右側を通過する際のルールが新設されます。
自動車が自転車などの右側を通過する際、両者の間に十分な間隔がない場合は、以下のようにしなければなりません。
| 運転者 | 取るべき対応 | 罰則 |
|---|---|---|
| 自動車 | 自転車などとの間隔に応じた安全な速度で走行しなければならない | 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 ※交通の危険を生じるさせるおそれがある場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 自転車など | できる限り道路の左端に寄って走行しなければならない | 5万円以下の罰金 |
自動車対自転車の交通事故で、自転車の右側に自動車が接触するケースが増えていることが、法改正の理由です。
2026年法改正3:普通仮免許などの年齢要件引き下げ

現行の道路交通法では、準中型と普通の仮免許・運転免許試験受験の年齢要件は、いずれも18歳以上です。
しかし、2026年5月23日までに施行される改正道路交通法により、準中型仮免許と普通仮免許の年齢要件が、17歳6カ月に引き下げられます。
引き下げの理由は、早生まれの人も高校卒業までに普通免許などを取得できるようにするためです。
18歳になる前に運転免許試験に合格しても、実際に準中型免許または普通免許が与えられるのは18歳になってからですが、就職や進学など、新生活が始まる4月以降はすぐに運転ができるようになります。
出典:事業評価方式による評価規制の事前評価書(要旨)│国家公安委員会・警察庁
2026年法改正4:自転車の交通違反に対する青切符の導入

2026年の法改正では、自動車だけでなく、自転車の交通ルールにも大きな変更が予定されています。
特に注目すべきは、自転車の交通違反に対する「青切符」制度の導入です。
これにより、これまで警告や指導にとどまっていた違反行為に対して、反則金が科せられるようになります。
そもそも「青切符」とは
「青切符」とは、正式には「交通反則告知書」と呼ばれるもので、比較的軽微な交通違反に対して交付される告知書のことです。
自動車や自動二輪車、自転車などのドライバーが交通違反をした際に警察官から交付され、反則金を納付することで刑事処分や裁判をしないこととする制度です。
従来は、自転車などの軽車両は対象外でした。
しかし、2026年の法改正により、この青切符が自転車の交通違反にも適用されることになります。
普段の生活だけでなく、通勤や業務の移動の際に自転車を使用する方は、今一度自転車のルールを見直しておきましょう。
自転車の交通違反に青切符が導入される理由
自転車の交通違反に青切符が導入される理由には、自転車が関係する交通事故が増加する中で、実効性のある取り締まりをおこなう必要性があったからです。
警察庁のデータによると、自転車が関係する交通事故は、2年連続で増加しています。
| 年度 | 事故件数 |
|---|---|
| 令和2年度 | 67,673件 |
| 令和3年度 | 69,694件 |
| 令和4年度 | 69,985件 |
2022年(令和4年)は、死亡または重傷を伴った事故7,107件のうち、およそ4分の3にあたる5,201件では、自転車側の前方不注意や信号無視、一時停止違反といった交通ルールの違反が確認されました。
現在、自転車による交通違反の多くは、罰則を伴わず指導を目的とした専用カードによる「警告」にとどまっており、2024年は全国でおよそ133万件の指導警告票が発行されています。
こうした背景から、自転車関連の事故が増加する中で、より効果的な対応が求められ、「青切符」の導入による実効性ある取り締まりが必要と判断されました。
参考:自転車関連交通事故の状況|警察庁・自転車は車のなかま〜自転車はルールを守って安全運転〜|警察庁
青切符の対象となる違反行為と罰金
青切符の対象となる自転車の違反行為は、道路交通法で定められたものに準じます。
具体的には、以下のような行為が挙げられます。
- 信号無視
- 指定場所一時不停止
- 通行区分違反(右側通行、歩道通行など)
- 通行禁止違反
- 遮断踏切立入り
- 歩道における通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転
- 携帯やスマートフォンの使用
- 公安委員会遵守事項違反(傘差し)など
出典:自転車の交通違反に対する交通販促通告制度の適用|警察庁
反則金は違反の程度や状況によって異なりますが、5,000円〜12,000円程度が目安です。
違反行為と反則金については今後、詳細が決定される見込みです。
違反した場合、反則金の納付が必要となり、納付しない場合は刑事手続きに移行する可能性もあります。
なお、酒酔い運転や酒気帯び運転などの違反行為は、赤切符(交通切符)が交付され刑事罰の対象です。
青切符の対象は16歳以上
自転車の青切符制度は、16歳以上の自転車利用者が対象となります。
15歳以下は対象外となりますが、交通ルールを守ることは年齢に関わらず重要です。
保護者や学校は子どもたちに対して交通安全教育を徹底し、安全な自転車利用を促す必要があります。
法改正に対して企業に求められる対応

2026年の法改正は、企業においても従業員の通勤や業務中の移動に対して、影響を及ぼす可能性があります。
万が一従業員が交通違反を犯して取り締まられた場合、以下の影響が考えられます。
- 取り締まりの事実が報道された場合、企業の社会的信頼が低下する
- 従業員が警察に止められて、業務が停滞するおそれがある
そのため、企業は法改正の内容について、社内に情報共有することが求められます。
日頃から交通安全に対する意識を高めるために、交通安全教育を取り入れることもおすすめです。
まとめ:2026年法改正を正しく理解し、安全運転を心がけよう
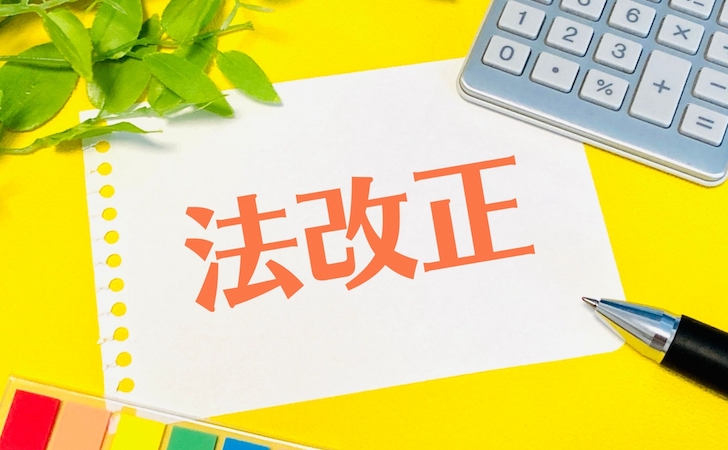
2026年の法改正は、生活道路における法定速度の見直しや車が自転車などの右側を通過する際のルールの新設、自転車の交通ルールの厳格化など、多岐に渡ります。
交通ルールの変更は、交通事故の減少と安全な社会の実現を目的としています。
今回の法改正を正しく理解し、日々の運転において安全運転を心がけることが重要です。
法改正の情報を社内で共有し、従業員一人ひとりが適切に対応できるようにしておきましょう。
なお、JAFメディアワークスでは、JAFが長年培ってきた交通安全のノウハウをeラーニング「JAF交通安全トレーニング」として教材化しました。
社内の交通安全意識の向上に、ぜひお役立てください。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /


















