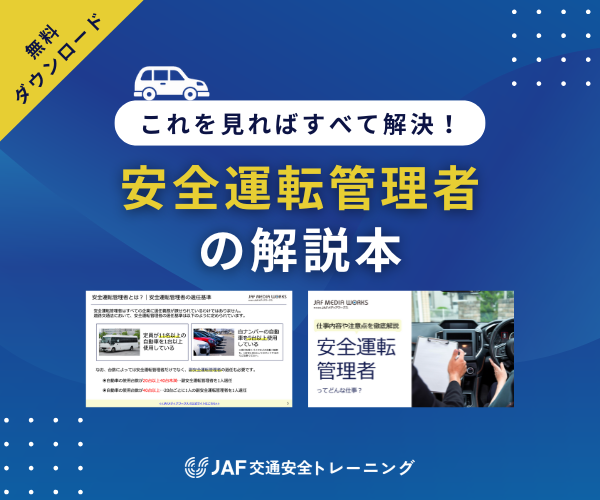2025年4月、軽バンを使った運送事業者は安全管理者を選任することが義務化されました。
対象は、運送事業を営む企業から個人事業主までと広範囲におよびます。
しかし、この「貨物軽自動車安全管理者」という新制度では具体的になにをするのか?と疑問をお持ちの方も多いはずです。
義務化の概要や安全管理者の選任方法、講習の受け方、違反時の罰則内容、現場での実践方法など、新制度に対応するために知っておくべきことは幅広くあります。
この記事では、貨物軽自動車安全管理者を選任しないときのリスクや、選任後に求められる体制づくりなど、実務目線で詳しく解説していきます。
\ これを見ればすべて解決!/
目次
貨物軽自動車安全管理者の概要と施行背景

2025年4月に新設された「貨物軽自動車安全管理者」選任制度は、いわゆる軽バンを保有している運送事業者を対象に、運行の安全確保の徹底を目的としています。
この制度が施行された背景としては、ネット通販やフリマアプリなど、EC(Electronic Commerce:電子商取引)市場が急速に成長している近年の需要拡大にともない、軽貨物ドライバーの交通事故が増加傾向にあることから、国土交通省が安全対策強化の一環として導入を決定しました。
平成28年から令和4年までの6年間で、事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が約5割増加(保有台数1万台あたり)した状況に対策がなされた格好です。
出典:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について|国土交通省
今後の軽貨物運送業界への影響

この制度が施行されることによって期待できる効果は、「軽貨物運送事業における事故防止」と「安全意識の向上」です。
従来の大型・中型トラック(普通貨物)と比較すると規制の緩かった軽貨物の分野ですが、これによって普通貨物に近い、より厳格な安全管理体制が求められることになります。
今後、軽貨物事業者の具体的な業務として、ドライバーへの監督・指導や点呼、安全計画の策定と実施、業務記録の保存など、幅広い安全管理業務が義務付けられます。
法令遵守と安全管理体制が強化されることで、事故リスクの低減が期待できます。
引いては、軽貨物業界全体の信頼性向上・生産性向上につながることでしょう。
義務化の対象となる事業者・個人事業主の範囲
新制度の義務化対象は、貨物軽自動車運送事業を営むすべての事業者・個人事業主です。
最低1名以上の安全管理者を選任する必要があり、事業規模や従業員数に関わらず適用されます。
また、複数の営業所を持つ場合は、それぞれの拠点で安全管理者を選任する必要があるので、講習受講や届出などの手続きには注意が必要です。
ただし、バイク便事業者など一部例外もあるため、詳細は国土交通省のガイドラインを確認しましょう。
| 対象 | 業務内容 |
|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業者(法人) | 営業所ごとに安全管理者選任・講習受講・届出 |
| 個人事業主 | 自身または従業員から選任・講習受講・届出 |
| バイク便事業者 | 原則対象外 |
参考:貨物軽自動車運送事業における安全規制について|国土交通省
貨物軽自動車安全管理者の「選任」とは何か?

貨物軽自動車安全管理者の選任義務は、2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法および関連省令に基づきます。
選任された貨物軽自動車安全管理者は、事業所の安全を管理する上で、運行の安全に関する知識を身に付けなければならない重要なポジションになります。
前項で説明した通り、営業所ごとに1名以上の安全管理者を選任後、国土交通大臣への届出が必要です。
もし、安全管理者の選任や届出を怠った場合は、行政指導や罰則の対象となりますので、確実におこないましょう。
選任に必要な資格・適正と要件
安全管理者に選任される者は、事業所の交通安全に対する責任を負う立場であることから、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 選任の日前2年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を修了した者
- 過去に講習を修了し、かつ選任の日前2年以内に貨物軽自動車安全管理者定期講習を修了した者
- 当該事業者が一般または特定貨物自動車運送事業を経営し、その営業所で運行管理者として選任されている者
上記の①は初回の講習となり受講時間5時間以上、②は2年ごとに受講が義務付けられていますが、受講時間は2時間以上となっています。
③のように運行管理者の資格保有者であれば講習は免除されますが、営業所内で運行管理者として選任され実務に携わっていることが条件となります。
個人事業主は、原則事業主本人を選任しますが、家族従業員を選ぶことも可能とされています。
軽貨物運送事業者に求められる対応

事業者に求められる対応としてまずおこなうべきは、自社の安全管理者を選任することです。
もし営業所が複数ある場合はそれぞれ選任し、選任された者は所定の講習を受講する必要があります。
選任後は、国道交通省への届出や業務マニュアル・記録簿の整備、運転者への定期的な指導・点呼の実施など、日常的な安全管理体制を構築することが求められます。
万が一事故が発生した際には、再発防止策や対応マニュアルを作成することも重要になります。
これらの対応を怠ると行政指導や罰則の対象となるため、早めの準備が不可欠です。
出典:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました|国土交通省
貨物軽自動車安全管理者の選任と届出期限
安全管理者の選任と届出期限は、新規事業者か既存事業者によって異なります。
新規事業者(2025年4月1日以降に経営届出している事業者)は、安全管理者の候補者に「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講させ、修了後は速やかに選任し、管轄の運輸支局等に届出しなければいけません。
一方、既存事業者(2025年3月31日までに経営届出を済ませている事業者)には、安全管理者の選任期限に2027年3月31日までの猶予が設けられています。また、「貨物軽自動車安全管理者講習」は2028年3月31日までに受講する必要があります。
選任を怠った場合の罰則と実務リスク

今回の規制強化にともない、貨物軽自動車安全管理者の選任を怠った場合には罰則が科せられます。ポイントは次の3つです。
- 選任義務違反:安全管理者の選任をしなかった場合
→100万円以下の罰金 - 届出義務違反:安全管理者の選任・解任を届出しない/虚偽届出
→100万円以下の罰金 - 事故報告義務違反:一定以上の事故を報告しない/虚偽報告
→50万円以下の過料
また、監査で違反が確認されると行政処分の対象となり、違反点数に応じて文書での警告や自動車の使用停止、事業停止などが科せられます。
なお、行政処分歴は過去5年間分が国土交通省のWEBサイト上で公開されてしまいます。
重大な違反を起こせば、継続取引・入札・委託審査などへ悪影響を及ぼす可能性が高くなるリスクがあります。
出典:行政処分情報|国土交通省
貨物軽自動車安全管理者の主な役割・業務

貨物軽自動車安全管理者の業務は多岐に渡り、その役割というのも事故を防止する上では大変重要です。
以下は、法令で定められている安全業務を13項目にまとめた表です。参考にしてみてください。
| 新制度 | 法令で定められている事項 | 概要 | 実施タイミング | ||
| 乗務前 | 乗務中 | 乗務後 | |||
| ○ | 貨物軽自動車安全管理者講習の受講 | ・貨物軽自動車安全管理者は選任前に加えて、選任後も2年ごとに受講しなけれければならない | – | ||
| ○ | 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出 | ・営業所ごとに選任し、選任時には法令で定められた事項について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出しなければならない | – | ||
| ○ | 初任運転者等への指導及び適性診断の受診 | ・法令で定められた初任運転者等の特定の運転者に対して、特別な指導をしなければ、また、適正診断を受診させなければならない ・運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを営業所に備え置かなければならない | – | ||
| 健康状態の把握 | ・運転者に対し、雇い入れる際や1年に1回、健康診断を受診させ、受診結果を事業者に提出させなければならない | – | |||
| 運転者に対する指導及び監督 | ・運転者に対して、運行の安全確保のために必要な運転の技術や関係法令の遵守事項の指導・監督を毎年実施しなけれればならない | – | |||
| 点呼 | ・運転者に対して、乗務の前後に必要事項を確認し、運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない | ○ | – | ○ | |
| 運転者の勤務時間の遵守 | ・運転者の勤務時間は、法令で定められた時間の範回内に収めなければならない | ○ | ○ | ○ | |
| 異常気象時における措置 | ・台風接近時に必要に応じて運行を中止したり、雪道では冬用タイヤを装着するといった、輸送の安全を確保するための措置を講じなければならない | ○ | ○ | – | |
| ○ | 業務の記録 | ・法令で定められた項目について記録を作成し、1年間保存しなければいけません | ○ | – | ○ |
| 過積載の防止 | ・過積載による運送を前提とする運行計画の作成や運送の引き受け、指示をしてはならない | ○ | – | – | |
| 貨物の適正な積載 | ・貨物の重さが、前後や左右で偏らないようにしなければならない ・荷崩れして貨物が落下しないよう、ロープやシートを掛けなければならない | ○ | ○ | – | |
| ○ | 事故の記録 | ・事故が発生した場合、その既要や原因、再発防止対策等を記録し、3年間保存しなければならない | – | – | ○ |
| ○ | 国土交通大臣への事故報告 | ・死傷者を生じた事故等の重大事故について、運輸支局等を通じ、所定の様式によって国土交通大臣へ報告しなければならない | – | – | ○ |
出典:貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました|国道交通省
まとめ:安全管理者を強化する意義と今後の備え方
この記事では、貨物軽自動車安全管理者を選任しないリスクや、選任後に求められる体制づくりなど、実務目線で解説しました。
2025年4月から施行されたこの新制度は、運送業界全体の安全性向上と事故防止を目的とした重要な施策です。
小規模の事業者も多い軽貨物事業では、日々の業務に追われ、なかなか選任や届出まで手が回らないという声も聞こえてきます。
しかし、罰則回避を目的として、安全管理者の選任をおざなりにおこなってしまっては元も子もありません。
新制度へ真摯に向き合い、安全管理業務を実直にこなすことで、事業所としての信頼性向上や顧客満足度獲得はもちろん、事故・賠償・営業機会損失・信用失墜を回避する手段向き合ってみてください。
さて、記事内で解説したように、軽貨物事業者には「教育・指導」「記録」「継続的な安全意識の醸成」「運転者に対する指導や監督業務」などがより厳格に求められることになりました。
社内での安全管理意識が高まることを機に、JAF交通安全トレーニング(通称JAFトレ)を活用を検討してみてはいかがでしょうか。
法令で定められている安全業務13項目のうち、「運転者に対する指導や監督業務」に関して、教材受講状況の管理機能が備わるJAFトレを利用することで補完可能です。
JAFトレは、長年、JAFのロードサービスで培われた交通安全ノウハウの詰まった、短時間で反復学習ができる交通安全教材として好評を得ている交通安全教材です。
数多くの企業で採用され、従業員あるいは事業所全体の安全意識向上・定着に十分な効果があるといったお声を多くいただいています。
教材を活用し、事故を少しでも減らすことで、今後のEC業界を発展させることにもつながるはずですので、ぜひご検討ください。
年齢別に見る事故傾向とその対策を解説します!