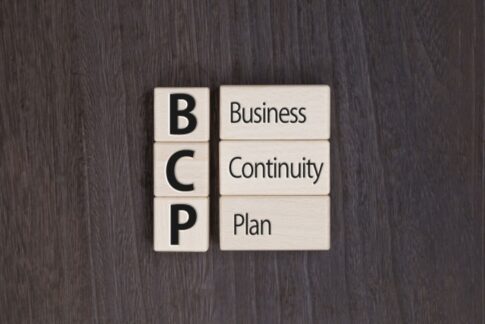リース社用車で万が一のトラブルに遭遇した際は、適切に対応する必要があります。
しかし、法律や契約に関する知識がないと、対処方法がわからずパニックに陥ってしまうこともあるでしょう。
本記事では、企業の車両管理担当者や、実際に運転している従業員に向けて、リース社用車の事故やトラブルにおける責任の所在を解説します。
リース社用車による事故に適切に対処するためにも、ぜひ参考にしてください。
安全運転意識を高める教育手法・教材がわかる!
目次
リース社用車とは

リース社用車とは、企業がリース会社から月々の定額料金で借り受けて使用する車両のことです。
自社で購入する「社有車」とは異なり、車両の所有権はリース会社にあります。
リース社用車は車両購入にかかる多額の初期費用を抑えられる上に、必要な台数の車両を確保できる点がメリットです。
リース契約には、主に以下の2種類があります。
契約内容によって、車両の維持管理に関する責任の所在が異なるため、自社の契約がどちらに該当するか把握しておくことが重要です。
| 契約の種類 | ファイナンス・リース | オペレーティング・リース |
|---|---|---|
| 概要 | 原則、中途解約不可の契約。実質的に車両を購入するのと近い。 | 期間満了後に車両を返却する前提の契約。一般的なレンタルに近い。 |
| 所有権 | リース会社 | リース会社 |
| 維持管理責任 | リース利用者(会社) | リース会社(契約による) |
| 契約満了後 | 車両の買取や再リースが一般的 | 車両をリース会社に返却 |
特に、車検やメンテナンスの費用がリース料金に含まれている「メンテナンスリース」は、オペレーティング・リースの一種であり、多くの企業で採用されています。
リース社用車の事故における責任の所在

リース社用車で事故を起こした場合、その責任は「会社」「従業員(ドライバー)」に分散されます。
しかし、従業員が業務中に起こした事故であれば、原則として会社が使用者として最も大きな責任を負うことになります。
まずは、誰にどのような責任が問われるのか、以下の表で基本的な関係性を理解しましょう。
| 対象者 | 主な責任内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社(使用者) | 使用者責任・運行供用者責任 | 従業員の業務上の行為に対し、外部の被害者への損害賠償責任を負う。 |
| 従業員(ドライバー) | 不法行為責任 | 直接の加害者として、被害者への損害賠償責任を負う。重大な過失がある場合は、会社からも損害賠償を請求される可能性がある。 |
※参考:民法 第七百十五条| e-Gov 法令検索,自動車損害賠償保障法第三条 | e-Gov 法令検索,民法第七百九条 | e-Gov 法令検索
法律上、会社は従業員の起こした事故に対して重い責任を負う立場にあります。
そのため、従業員個人がすべての修理費用や賠償金を背負うケースは稀です。
リース社用車であっても、責任が問われる主体は会社と使用者(従業員)が中心となります。
会社が負う2つの法的責任

社用車事故において、会社が負うことになる法的責任には、大きく分けて「使用者責任」と「運行供用者責任」の2つがあります。
どちらも、企業が事業活動で車を使う以上、避けては通れない重要な責任です。
使用者責任
使用者責任とは、「従業員が、その事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任」のことを指し、民法第七百十五条に定められています。
簡単に言えば、「事業のために従業員を働かせている以上、その従業員が仕事中に与えた損害の責任も、会社が負いなさい」とするのが、使用者責任の考え方です。
この責任は、物損事故・人身事故を問わず適用されますが、ポイントは以下のとおりです。
| 成立要件 | 1.会社と従業員の間に使用関係があること 2.従業員が「事業の執行」において事故を起こしたこと 3.従業員の行為が不法行為にあたること |
| 会社の免責 | 会社が従業員の選任・監督について相当の注意を払っていたことを証明できれば免責されるが、実務上、認められるのは極めて困難。 |
「事業の執行」の範囲は広く解釈されており、業務時間外であっても、業務との関連性が認められれば適用される場合があります。
参照:民法第七百十五条
運行供用者責任
運行供用者責任とは、「自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合において、自己のために自動車を運行の用に供する者が負う責任」のことです。
こちらは自動車損害賠償保障法(自賠法)第三条に定められています。
「車を動かして利益を得ている以上、その車が起こした人身事故の責任も負いなさい」とするのが、運行供用者責任です。
使用者責任と異なり、運行供用者責任の対象は人身事故に限定されます。
| 成立要件 | 1.会社が「運行供用者」であること 2.自動車の運行によって人の生命・身体が害されたこと |
| 会社の免責 | 以下の3点すべての証明が必要 1.会社およびドライバーが注意を怠らなかったこと 2.被害者または第三者に故意・過失があったこと 3.車両に構造上の欠陥や機能障害がなかったこと |
従業員(ドライバー)が責任を問われるケース

リース社用車による交通事故は、会社が重い責任を負う一方で、事故を起こした従業員(ドライバー)の責任が完全になくなるわけではありません。
特に、従業員に「故意」または「重大な過失」があった場合、会社は支払った賠償金を従業員に請求する(求償する)ことがあります。
従業員個人の責任が重く問われるのは、主に以下のようなケースです。
- 飲酒運転、無免許運転
- 著しい速度超過や信号無視など、悪質な交通違反
- 居眠り運転
- 会社に無断での私的利用中の事故
- 事故の不報告(隠蔽)
ただし、会社が従業員に損害の全額を請求できるわけではありません。
判例(大隈鐵工所事件)では、会社も従業員を使って利益を上げている以上、その過程で発生した損害のリスクを負担すべきとされています。
そのため、請求できる範囲は、信義則上、損害の公平な分担という観点から、かなり制限されるのが一般的です。
リース社用車での事故発生時の対応

万が一、事故に遭遇してしまったら、パニックにならず冷静に行動することが何よりも重要です。
ここでは、運転していた従業員と、報告を受けた会社(管理者)がそれぞれ「何をすべきか」を時系列で解説します。
従業員(ドライバー)の対応
ドライバーである従業員は、以下の優先順位で行動してください。
| 対応事項 | 詳細 |
|---|---|
| 負傷者の救護と安全確保 | 真っ先に負傷者がいないか確認し、必要であれば救急車(119番)を呼びます。 車を安全な場所に移動させ、後続車への注意喚起のためにハザードランプを点灯し、発煙筒や停止表示器材を設置します。 |
| 警察への連絡(110番) | 軽微な事故でも、必ず警察に連絡します。 警察への届出を怠ると、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。 |
| 関係各所への連絡 | 警察の現場検証が終わったら、速やかに会社(上司や車両管理者)に報告します。 その後、会社の指示に従い各所へ連絡します。 |
事故を起こした際は、事故の日時・場所・状況・相手方の情報・車両の損傷具合などを報告しましょう。
なお、責任の所在は保険会社などが判断するため、その場で示談の約束をすることは厳禁です。
社用車での事故における独断での示談交渉は、会社に重大なリスクをもたらします。
まず、事故状況の正確な把握や法的な責任範囲の判断が困難となり、会社にとって不利な条件で示談してしまう可能性があります。
また、示談内容によっては、保険金が支払われなくなる、あるいは会社が加入している保険の更新に影響が出かねません。
さらに、会社としての賠償責任や社会的信用を損なうリスクもあるため、必ず会社に報告し、指示を仰いでください。
会社の対応
従業員から事故の報告を受けたら、管理者は以下の対応を進めます。
| 対応事項 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員の安全確認と状況把握 | まずは従業員の心身の状態を気遣い、冷静に事故状況のヒアリングをおこないます。 警察への届出や負傷者の救護が済んでいるかを確認します。 |
| リース会社・保険会社への連絡 | 契約内容を確認し、リース会社と保険会社に事故の第一報を入れます。 今後の手続き(修理、代車の手配など)について指示を仰ぎます。 |
| 事故報告書の作成と保管 | 従業員に詳細な事故報告書を作成させ、ドライブレコーダーの映像などと共に保管します。 これは再発防止策を検討する上での重要な資料となります。 |
| 再発防止策の検討 | 事故原因を分析し、同じような事故が二度と起きないよう、具体的な対策を講じます。 |
社用車による事故が発生した場合、迅速かつ適切な対応を取る必要があります。
主なポイントは以下の3点です。
| 初動対応の徹底 | 事故発生直後の負傷者の救護・警察への連絡・事故状況の記録を迅速におこないます。二次的な事故を防ぐための安全確保も重要です。 |
| 事実関係の正確な把握 | 事故当事者(ドライバー)からの詳細なヒアリング・ドライブレコーダーの映像確認・目撃者の証言収集などを通じて、事故の原因や責任の所在を明確にします。客観的な証拠に基づいた事実確認が不可欠です。 |
| 関係者への適切な情報開示とサポート | 被害者への誠実な謝罪と賠償・保険会社との連携・必要に応じて弁護士への相談をおこないます。また、事故を起こした従業員への精神的なケアとともに、再発防止に向けた指導・研修を実施します。情報公開は迅速かつ正確におこない、関係者との信頼関係を維持することが重要です。 |
これらの対応を通じて、会社は社会的責任を果たし、リスクを最小限に抑えることが求められます。
社用車による事故を防ぐ対策

事故対応も重要ですが、最も大切なのは事故を未然に防ぐことです。
日ごろから以下の対策を徹底し、事故のリスクを最小限に抑えましょう。
点検やメンテナンスの実施
車両の不具合が事故に直結することもあります。
法律で定められた定期点検整備はもちろん、運転前の日常的な点検を習慣づけることが重要です。
| 点検の種類 | 内容 |
|---|---|
| 日常点検整備 | ドライバーが始業前におこなう基本的なチェック。 (例:タイヤの空気圧・ライトの点灯・ブレーキの効き具合など) |
| 定期点検整備 | 法律で定められた期間ごとに、専門の整備工場でおこなう詳細な点検。 |
メンテナンスリース契約であれば、点検時期になるとリース会社から案内が来ることが多いですが、日常点検整備はドライバーの義務として社内ルールで徹底させる必要があります。
安全運転教育を実施する
ヒューマンエラーによる事故を防ぐには、継続的な安全運転教育が不可欠です。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| 社内ルールの策定と周知 | 社用車の使用目的・ドライバーの条件・私的利用の禁止・事故時の報告フローなどを明記した「車両管理規程」を作成し、全従業員に周知します。 |
| 定期的な研修の実施 | 危険予知トレーニング(KYT)や、ドライブレコーダーの映像を使ったヒヤリハット事例の共有会などを定期的に開催し、安全意識を高めます。 |
| ドライブレコーダーの導入 | 事故時の証拠保全だけでなく、自身の運転を客観的に見返すことができるため、安全運転意識の向上にもつながります。 |
以上の対策以外にも、安全運転教育に役立つ教材の導入もおすすめです。
特にJAF交通安全トレーニングは交通安全意識を醸成する上で不可欠な知識を学べる教材として、多くの企業が導入しています。
さらにJAF交通安全トレーニングはeラーニング教材であるため、業務の合間に受講しやすく、進捗の管理も容易です。
受講した個々の従業員に向けた指導もできるため、より効果的な安全運転教育が実現します。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /
まとめ:リース社用車による事故の責任を正しく理解しよう

リース社用車で事故を起こした場合、業務中の事故であれば、基本的には会社が使用者として重い責任を負いますが、社員の悪質な違反などによっては社員の責任も問われます。
万が一事故が発生してしまった場合は、パニックにならず、本記事でお伝えした対応を冷静に実施しましょう。
もちろん、何よりも大切なのは、事故を未然に防ぐための日頃からの取り組みです。
車両の点検・メンテナンスや、継続的な安全運転教育といったリスク管理を徹底することが、会社とそこで働く大切な従業員を守ることにつながります。
本記事を参考に、自社の車両管理体制・安全運転教育体制を今一度見直してみてください。
安全運転意識を高める教育手法・教材がわかる!