従業員の通勤や出張時に、「私用車の業務使用」をしている企業もあるでしょう。
しかし、私用車の業務使用には法律や企業の規定に違反するリスクが存在し、適切なルールを守らなければ、重大なトラブルを引き起こす可能性があります。
本記事では、企業が知っておくべき私用車の業務使用に関する基本ルールや注意点を徹底解説し、リスク回避のための対策についても詳しくご紹介します。
従業員の安全を守り、適切に運用するためのポイントを押さえましょう。
\ これを見ればすべて解決!/
目次
私用車を業務で使用する際の基礎知識

私用車を業務で使用する場合、つまり従業員が所有する車両を仕事に利用する場合、企業と従業員双方に注意すべき点が多く存在します。
例えば、適切な保険の加入や安全運転の徹底はもちろん、労働時間の管理や経費精算のルールも明確にしておかなければなりません。
また、私用車を業務で使用する際のリスクとその対策についても理解しておく必要があります。
ここでは、私用車の業務使用に関する基礎知識を学び、トラブル回避のために必要なポイントを詳しく解説します。
私用車と社用車の違いとは?
私用車と社用車の違いは、主に所有者・用途・維持費・管理方法の4点が挙げられます。
| 項目 | 私用車 | 社用車 |
|---|---|---|
| 所有者(使用者) | 個人 | 会社 |
| 使用目的 | 私生活 | 業務 |
| 維持費 | 自己負担 | 会社負担 |
| 管理責任 | 個人 | 会社 |
社用車は業務に使用する車で、保険やメンテナンス費用などは企業負担です。
一方、私用車を業務利用する際には、経費や保険の扱いが異なります。
例えば、私用車を業務で使用する際は、通常の保険ではカバーされないことが多く、業務用の保険加入が必要になります。
また、私用車の使用におけるガソリン代やメンテナンス費用の精算についても明確なルールを設けなければなりません。
業務使用の範囲と定義
業務使用とは、従業員が私用車を業務の一環として使用する際の範囲を指しますが、その範囲は明確に定義される必要があります。
例えば、通勤時の車両使用は通常、業務使用には含まれない場合が多いですが、営業活動や出張などでの移動は業務使用に該当します。
企業は、業務使用に該当する具体的な状況を規定し、従業員がどのような場合に私用車を使用できるかを明確に示すことが重要です。
また、業務使用の範囲に応じて適切な保険や安全対策を講じることも、企業の責任となります。
私用車を業務使用するメリットとデメリット
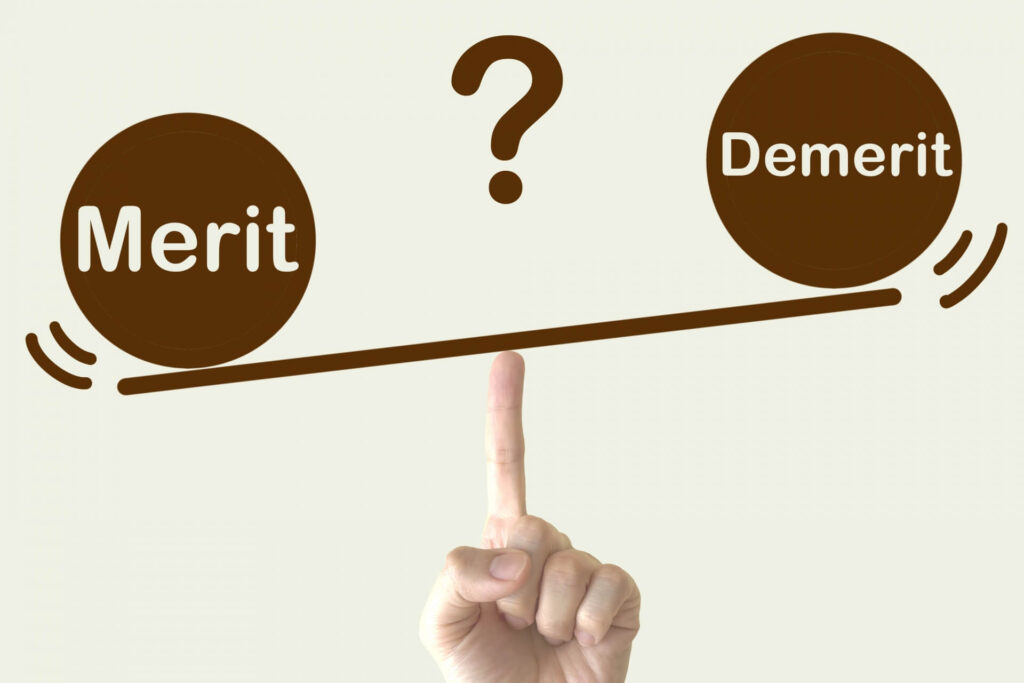
私用車を業務で使用することには、企業や従業員にとってさまざまなメリットとデメリットが存在します。
コスト削減や利便性の向上などがメリットとして挙げられますが、一方で、事故や故障時のリスク、保険の適用範囲の問題なども無視できません。
ここでは、私用車を業務に活用することの利点とその裏に潜むリスクについて、企業が注意すべきポイントを整理し、具体的な対策も含めてご紹介します。
企業におけるコスト削減のメリット
私用車を業務使用する大きなメリットは、企業が社用車を保有するコストを削減できる点です。
社用車を用意する場合、車両の購入やリース、保険、メンテナンス費用が発生しますが、私用車を活用すればこれらのコストを抑えることが可能です。
また、従業員が所有している車両を使用するため、特別な管理コストもいりません。
特に中小企業にとっては、初期投資を抑えつつ効率的な業務運営が期待できるため、私用車の業務使用はコスト削減に有効な選択肢となるでしょう。
交通事故や故障といったトラブル発生時のリスク
一方で、私用車を業務で使用する際には、事故や故障が発生した場合のリスクが大きな課題となります。
社用車と異なり、私用車の自動車保険は、業務中の事故をカバーしていないことが多く、万が一の場合、従業員や企業が多額の賠償責任を負う可能性があります。
自動車保険には、「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務使用」などの区分があり、一般的に私用車は、プライベートでしか使わないなら「日常・レジャー」、通勤にも利用しているなら「通勤・通学」を選択しています。
そのため、業務で使うことが多いとなると、使用目的区分を「業務使用」に切り替える必要があります。
また、その私用車を他の従業員が運転する場合には、自動車保険の「運転者の範囲」も合わせて確認しましょう。
万が一に備えて、使用状況に応じた適切な保険加入や、明確な社内規定の整備が重要になります。
参考:社員が通勤時、または業務でマイカーを使用する場合の注意点は? | JAF クルマ何でも質問箱
私用車の業務使用に必要な手続きと条件

私用車を業務で使用する際には、従業員や企業が適切な手続きをおこない、必要な条件を満たすことが求められます。
具体的には、任意保険の加入や企業との契約書の取り交わし、書類提出など、業務使用に伴うリスクを最小限に抑えるための準備が必要です。
ここでは、私用車の業務使用に関する手続きや条件について、企業と従業員が共に理解しておくべきポイントを詳しく解説します。
任意保険の加入条件と補償範囲
私用車を業務で使用する場合、任意保険への加入は必須です。
通常のマイカー保険では業務中の事故が補償対象外となることが多いため、業務使用に対応した特約や商用車向けの保険に加入する必要があります。
企業は、従業員が適切な保険に加入しているかどうかを確認し、業務に支障が出ないよう努めなければなりません。
また、保険料も企業が一部負担するケースもあるため、契約時に条件を明確にすることが求められます。
企業との契約や書類提出の流れ
私用車を業務で使用する際には、従業員と企業の間で明確な契約を結ぶ必要があります。
この契約には、車両使用に関する条件や経費精算、保険の適用範囲など、業務使用に関連するすべての事項を記載します。
また、車両の保険証書や定期点検整備記録などの書類提出も必要です。
企業は、これらの書類を適切に管理し、従業員が安全かつ適法に私用車を使用できる体制を整えることが求められます。
手続きの流れを明確にし、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
私用車を業務で使用する際の注意点と法的リスク

私用車を業務で使用する場合、従業員や企業には多くの法的リスクが伴います。
特に事故やトラブルが発生した際には、適切な対応を怠ると重大な責任問題が生じる可能性があります。
また、労災認定や保険の適用範囲にも注意が必要です。
ここでは、私用車を業務で使用する際に考慮すべき法的リスクや注意点について詳しく解説します。
業務使用での事故がもたらす法的責任
私用車を業務で使用中に事故が発生した場合、その法的責任は複雑です。
まず、運転していた従業員には民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。
また、事故が業務遂行中であった場合、企業にも使用者責任が問われ、被害者への賠償義務が発生することがあります。
さらに、保険適用の有無や事故原因によっては、法的責任を負うこともあり得るでしょう。
例えば、ドライバー個人の民事責任、ドライバー個人の刑事責任、会社の使用者責任、安全配慮義務違反などが挙げられます。
このため、企業は事前に従業員と明確な契約を交わし、事故発生時の対応手順を整備しておくことが重要です。
労災認定の対象とならないケース
私用車の業務使用中に発生した事故が、必ずしも労災認定の対象となるわけではありません。
例えば、通勤災害は労災の対象になりますが、私用で移動してる最中に発生した事故は労災認定の対象外となることがあります。
また、業務中であっても、企業が事前に定めたルールを逸脱していた場合なども労災認定が困難になるケースもあるでしょう。
例えば、業務中に会社が明確に禁止している行為(例:寄り道や飲酒運転など)をしていた場合や、自宅以外の一時的な住居から通勤した際など、その行為が原因で事故が起きた時は、労災認定が難しくなる可能性があります。
これは、会社のルールや通勤上の届出に沿わない行為が事故につながったと判断されるためです。
企業は労災認定の基準を明確にし、従業員に適切な指導をおこなうことで、トラブルを未然に回避することが求められます。
参考:勝手にマイカー通勤して通勤災害に遭遇したら|東京歯科保険医協会
マイカーの業務使用に強制力はあるのか?
マイカーの使用は個人財産の利用にあたるため、原則として一方的な義務付けはできません。
会社が従業員に対してマイカーの業務使用を求める場合、雇用契約や就業規則に則り、使用条件や補償範囲を明確にして本人同意を取ることが必須です。
制度化と条件明示でトラブルや不満を防ぎ、同意を得られなかった場合の代替手段も確保するのが望ましいです。
私用車使用時にかかる経費の精算方法

私用車を業務で使用する場合、ガソリン代やメンテナンス費などの経費が発生します。
これらの経費はどのように精算するか、また企業と従業員のどちらが負担するのかを明確に定めることが重要です。
経費精算のルールや税務処理の正確な理解は、トラブルを未然に防ぐために不可欠です。
ここでは、私用車使用時にかかる経費の精算方法について詳しく解説します。
ガソリン代やメンテナンス費の負担
私用車を業務で使用する際には、ガソリン代やメンテナンス費の負担が問題となります。
通常、業務使用に伴うガソリン代は企業が負担するケースが一般的ですが、メンテナンス費用については事前に企業と従業員の間で合意が必要です。
例えば、日常的な点検や修理費用は従業員が負担し、業務使用による車両の損耗に関しては企業が一定額を負担する方法が取られることがあります。
明確な費用負担のルールを決めることで、経費精算時のトラブルを防げます。
経費精算のルールと税務処理
私用車の業務使用にかかる経費の精算には、明確なルールと正確な税務処理が求められます。
まず、経費精算に際しては、従業員が提出する領収書や走行距離の記録が必要です。
ガソリン代やメンテナンス費用を企業負担とする場合、それらを経費として適切に計上し、税務処理することが重要です。
また、業務使用の頻度や使用範囲に応じて、経費の一部が個人使用と見なされることがあるため、税務上の扱いに注意してください。
正確な記録とルールの整備が不可欠です。
まとめ:私用車の業務使用はリスク管理と同意が重要!正しい手続きと対応を心がけよう

私用車を業務で使用する際には、リスク管理が不可欠です。
適切な保険加入や契約手続き、経費精算のルールを整備することで、法的リスクやトラブルを最小限に抑えられますが、会社は従業員に対して丁寧に説明し、必ず同意を取ることが大切です。
また、私用車で業務にあたる場合も、従業員への安全運転指導が必須となります。
緊張感が薄れやすい私用車での業務は、漫然運転につながる恐れがあるためです。
スキマ時間を使って交通安全を学べるe-ラーニング教材「JAF交通安全トレーニング」を利用し、安全意識を高めれば事故リスクが減ります。
リスク管理を徹底して安全な業務環境を目指しましょう。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /


















