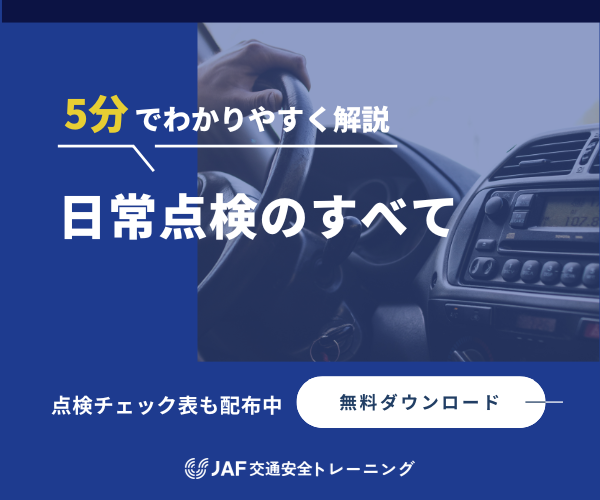「今のETCが使えなくなるかもしれない」という噂を聞いたことはありますか?
この話には、ETCの2030年問題、そして新型コロナウイルスの影響によって延期中の2022年問題が深く関係しています。
本記事では、差し迫るETCの2030年問題について解説し、使えなくなるETCや新規格に移行する方法などを紹介。
また、現在も延期され続けている2022年問題についても簡単に触れていきます。
現在使っているETC車載器が今後も問題なく使えるのか気になる方や、車やETC車載器の買い替えを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因
目次
そもそもETCとは

ETCの問題について解説する前に、まずは従来のETCと次世代のシステムであるETC2.0について解説します。
ETCとは
ETC(Electronic Toll Collection System)とは、高速道路や有料道路の料金所ゲートを通過する際に、車両に取り付けられた車載器と無線通信をおこない、車両の種類や通行した区間を特定して、認証や支払い処理をおこなうシステムのことです。
ETCを利用することで、実際に現金等のやり取りをすることなく通行料金を支払うことが可能です。
便利である上に渋滞緩和につながるなど享受できるメリットが多いことから、2025年7月現在の利用率は95.4%(※)にのぼります。
※ETC2.0利用台数も含めたETC全体利用率の集計
出典:ETCの利用状況|国土交通省
ETC2.0とは
一方、ETC2.0とは、料金収受のみであった従来のETCをバージョンアップさせたシステムを指します。
従来のETCと比較すると、以下のような違いがあります。
- 高速道路の出入り情報だけでなく、経路情報も把握できる
- 規制情報や災害情報など、さまざまな情報を送受信できる
つまり従来の認証や決済自動化だけでなく、自車位置をもとにした進行方向の詳細な道路情報を活用して渋滞迂回ルートを提示したり、進路上の落下物や事故情報を提供することが可能になるのがETC2.0ということです。
また、ETC2.0の利用者を対象とした割引が各地で実施されているなどコスト的なメリットも多く、利用率は徐々に増加しており、2025年7月現在のETC2.0の利用率は37.8%となっています。
なお、ETC2.0については以下の記事で詳しく解説しているので、仕組みを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
ETCを利用するために必要なもの
ETCを利用するために必要なものは以下のとおりです。
- 車載器:料金所のアンテナと無線通信するための装置
- ETCカード:ETC決済専用のICカード
ETCカードを車載器に挿入した状態で、各料金所に設置されたETCレーンを通過することで通行料金の電子決済をおこない、高速・有料道路の利用料金を支払うことが可能になります。
なお、車載器単体では支払い・精算機能が備わっていないため、ETCカードを挿入しなければETCを利用できない点に注意してください。
ETCは廃止されるのか?

結論から言えば、ETCというシステム自体が廃止されるといった予定は今のところありません。
しかし、ETCの2030年問題、または2022年問題によって、現在使用しているETCが使えなくなる可能性があります。
2030年問題は、セキュリティ機能向上のための規格変更によるもの。2022年問題は電波法関連法案の改正によるものです。
2030年問題では多くの機種が使えなくなること、2022年問題ではごくわずかであるものの一部の機種が使えなくなることが想定されています。
両問題に対して自車の車載器が該当するかどうか確認をおこなわなければなりません。
この機会に、現在使用しているETC車載器が問題の対象であるかどうか、一度確認してみましょう。
ここからは、2030年問題と2022年問題について詳しく解説していきます。
ETCの2030年問題とは

ETCの「2030年問題」とは、ETCシステムのセキュリティ機能向上のための規格変更に伴って発生する問題です。
サイバー攻撃などの脅威に備えるために、2030年までには現行のセキュリティ規格のETC車載器が使えなくなる予定です。
2022年問題と比べて多くの機種が対象となるため、早急に車載器を確認し、必要があれば購入等の対応をとりましょう。
対象となるETCの確実な見分け方
使用中のETCが2030年問題の対象であるかどうかは、19桁の車載器管理番号で確認できます。
具体的には以下のとおりです。
- 左から1文字目の数字が「1」=新セキュリティ規格対応モデル
- 左から1文字目の数字が「0」=旧セキュリティ規格モデル
車載器管理番号は、取扱説明書や保証書、車載器セットアップ申込書、車載器セットアップ証明書で確認できます。
車載器管理番号がわからない場合の見分け方
もし車載器管理番号がわからない場合は、ETC車載器に記されたセキュリティ情報を表す「識別マーク」を見ることでも新旧判別できます。
以下に代表例を紹介しますので参考にしてみてください。
- カード挿入口付近などに◼︎マークがある=旧セキュリティ規格
- カード挿入口付近などに●●●マークがある=新セキュリティ規格
- 車載器表面などに「DSRC」の文字が印字されている=旧セキュリティ規格
※1 車載器の型式により識別マークが描かれていない場合もあります。
※2 上記の方法で識別できない場合は、購入した販売店またはセットアップ店で確認しましょう。
規格変更は「最長で2030年頃まで」
今回の規格変更は、将来的な脅威に備えることが目的です。
現行のセキュリティ規格でこのまま大きな問題が起こらなければ、規格変更は最長で2030年頃の予定です。
しかし、現行(旧)セキュリティに何かしらの脅威が発生した場合には時期が早まり、2030年よりも早い段階でセキュリティ規格が変更される可能性もあります。
さらに変更時期が近づくと対象機種が品薄になることが予想されます。
さまざまな可能性を考慮し、特に社用車を多く所有している場合などには、早急に対応しておくことをおすすめします。
ETCの2022年問題とは

ETCの2022年問題とは、2005年の電波法関連法案改正によって発生した問題です。
2022年12月1日以降、旧スプリアス規格(2007年以前)に基づいて製造されたETC車載器を使用すると、電波法違反にあたるようになりました。
スプリアスとは、無線設備が発する電波のうち、決められた周波数から外れた不要な電波のことで、ほかの機器に電波障害を引き起こす恐れがあるため、電波法によってその強度が規制されています。
この規制基準が改正前のものを、旧スプリアス規格と呼びます。
電波環境に影響を与える旧スプリアス規格を無くすことで電波利用環境の維持・向上を図るため、旧規格のETC車載器は移行期間終了後に使用が禁止されることになりました。
使えなくなったETC車載器はわずか
しかし、2005年の電波法関連法案改正後に発売されたETC車載器の多くは改正後の電波法に対応済みのため、現在使用されているETC車載器のうち、対象機種はわずかと言われています。
詳細は、ETC総合情報ポータルサイトからご確認ください。
ETC車載器の取扱説明書や保証書、車載器セットアップ証明書や機器本体のラベルに記載されている「型式登録番号」で対象製品かどうかわかるため、ぜひチェックしてみてください。
参考:旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器について|国土交通省
移行期間終了後に旧規格のETCを使うと違法になる
2022年12月1日以降使用できなくなる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済情勢を考慮し、旧スプリアス規格の使用期限を「2022年11月30日」から「その使用期限を当分の間、延長する」ことが総務省によって発表されました。
2025年10月現在でも、移行期間の具体的な期日は決まっていません。
移行期間終了後でも旧規格のETC車載器で料金所ゲートを通過することは可能ですが、通電して使用すること自体が電波法違反となるため、以下のような処罰を受ける可能性があります。
・不法設置・運用のみ:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・公共性の高い無線局への妨害:5年以下の懲役または250万円以下の罰金
もしも社用車で違反行為が認められれば、業務上何かしらのペナルティが課される可能性や、社会的地位や信用を損なうこともリスクとして考えられます。
使用期限が延長されていることで余裕を感じてしまいがちですが、事前に社用車に取り付けられている車載器のチェックをおこなうことをおすすめします。
ETCを新規格へ移行する方法

規格を確認した結果、現在使用しているETC車載器が2030年問題・2022年問題の対象機種だった場合、早めに新規格のETC車載器に買い替えましょう。
最後に、ETCを新規格へと移行する方法を紹介します。
車の買い替えに合わせて移行する
車の買い替えをおこなう場合、買い替え時には旧車両に搭載されていたETC車載器は廃棄し、新しい車載器を取り付けることを強くおすすめします。
また買い替えをおこなう時期を確認し、新規格への移行期限が過ぎないように注意しましょう。
最近では車を購入する際、ETC車載器が車両に一体化の状態で搭載されていたり、オプションとしてETC車載器の取り付けを依頼できるケースがほとんどです。
新車を購入する場合、車載器の規格は新規格であることがほぼ間違いないでしょうが、中古車を購入する場合には、その車にETC車載器が備わっているか、備わっていればそれが新規格のものかどうかの確認をおこなうと良いでしょう。
既存の車に後付けする
既存の車のETC車載器のみを付け替えることも可能です。
先述したETC車載器の新旧規格の確認方法を用いてETC2.0車載器にバージョンアップをおこないましょう。その際には「旧機種の取り外し」「新機種取り付け」「セットアップ」という3つの作業が必要となります。
セットアップとは、高速道路や有料道路を利用する際の決済が正確にできるようにしたり、ETC2.0の利用に必要な車両情報を車載器に登録したりする作業のことです。
取り付けのみであれば工具を用いて個人でおこなうことも可能ですが、セットアップは技術や信頼性に関する審査を通過した登録店でしか実施できません。
個人や未登録の店では実施できない作業のため、以下のような登録店に依頼してください。
- ETC車載器を購入した店舗
- ディーラー
- カー用品店
- 中古車専門店
ETC車載器を購入したお店で取り付け・セットアップをおこなうとよりスムーズです。
また、下記参考リンクからお近くのセットアップ店を検索することもできますので、活用してみてください。
まとめ:2030年に向けて、早めに新規格のETCに移行しよう

ETCは、高速道路や有料道路を利用するユーザーにとって利便性が高まるシステムです。
全体利用率が90%を超えるなどETC普及が進む一方で、セキュリティ規格の見直しなどによって車載器の買い替えを行わなければならない場合があります。
以下に、差し迫る2030年問題と期限延期中の2022年問題について簡単にまとめてみました。
- 2022年問題:電波法関連法案改正によって生じた問題。対象機種は少ない。
- 2030年問題:セキュリティ規格の向上によって生じた問題。対象機種は多い。
対象機種は移行期間終了後、使用不可となってしまうため、社用車など多くの車を所有・管理している場合は、自社保有の車両に搭載されているETC車載器がそれぞれ対象となっているかを早急に確認し、対応することが求められます。
もしも社用車で違反行為が認められれば、業務上何かしらのペナルティが課される可能性や、社会的地位や信用を損なうこともリスクとして考えられますので、しっかりと確認し、旧規格に該当するようであれば新機種への買い替えを早急におこなってください。
高速道路でのトラブル対処方法など、交通安全を学びたい方には「JAF交通安全トレーニング(JAFトレ)」の受講をおすすめします。
JAFトレは、長年ロードサービスを提供するJAFが蓄積してきた交通安全ノウハウを結集させた交通安全教材として、企業・団体向けに交通安全意識を高めるコンテンツを配信しています。
時間や場所を選ばず、スマホやパソコンを利用してWEB上で学習できる教材なので、受講者は受講意欲を維持しやすく、受講者それぞれにあったペースで学ぶことができます。
また、パソコン操作に不慣れな方でも直感的に操作できるUI・管理者機能を備えているため、受講者の学習状況の確認を容易におこなうことができ、個別の指導・教育に活かすことも可能です。
継続的な安全運転教育を実現するためにも、JAFトレの導入をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /