交通事故は、誰にでも起こりうる不幸なでき事です。
事故を起こしてしまうと人命を脅かすうえ、刑事罰だけでなく、行政罰に問われる可能性もあります。
しかし、行政罰の種類や点数、罰金、免許停止・取消処分など、複雑な制度に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では「交通事故の行政罰」について、刑事罰との違いや点数、免許停止・取消の基準などを解説します。
事故発生直後に取るべき行動や、弁護士への相談の重要性についても触れているので、万が一の際に役立つ情報が満載です。
若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因
目次
交通事故における行政罰の概要

交通事故における行政罰とは、交通事故加害者に違反点数が加算され、その累積点数に応じて運転免許の停止・取消などの処分が下されることです。
この運転免許の点数制度(累積加算制度)は、原則として過去3年間の違反や事故に対する点数が累積され、その合計点に基づいて処分が決まる仕組みです。
酒酔い運転やあおり運転など、特に悪質な違反については、1回の違反で免許取消の処分が科されることがあります。
行政罰と刑事罰の違い
交通事故を起こした場合、刑事罰と行政罰の両方の責任を負う可能性があります。
どちらも法律に基づいて科せられる罰ですが、その目的や手続き、内容は大きく異なります。
刑事罰は犯罪行為に対する国による制裁で、刑事裁判で有罪判決が下された場合に科せられる処分です。
犯罪の重大性に応じて、懲役や罰金といった重い罰則が科せられます。
交通事故の場合、例えば「危険運転致死傷罪」や「過失運転致死傷罪」などが該当します。
一方の行政罰は、行政上の重大な義務違反に対して、行政機関(警察など)が科す処分です。
行政罰は、刑事罰のように裁判を経ずに、行政処分として科せられます。
交通事故の場合、道路交通法違反に対する罰則が行政罰に該当します。
以上をまとめると、以下の表のとおりです。
| 項目 | 刑事罰 | 行政罰 |
|---|---|---|
| 目的 | 犯罪者への懲罰、犯罪者の更生、社会秩序の維持 | 再罰防止、交通安全の確保 |
| 手続き | 裁判による訴追、有罪判決 | 警察による調査、行政処分 |
| 罰則 | 懲役、罰金、執行猶予 | 免許停止、免許取消、反則金 |
| 科す主体 | 裁判所 | 警察署長など行政機関 |
簡単にいうと、刑事罰は「犯罪に対する罰」、行政罰は「交通ルール違反に対する罰」です。
刑事罰は裁判による有罪判決が必要ですが、行政罰は警察の判断で科せられる点が大きな違いです。
行政罰と刑事罰ではどちらが先に決定されるか
行政罰と刑事罰、どちらが先かはケースバイケースです。
比較的軽微な交通違反・事故の場合は、刑事罰の後に行政罰が下される場合が多いようです。
特に、違反の際に赤切符を受け取っている場合は略式裁判所に出頭する必要があり、行政罰はその後になります。
しかし、複雑な違反や事故であれば、行政罰が先に下される場合もあります。
交通事故における行政罰の種類・点数・罰金

次に、交通事故における行政罰の種類・点数・罰金について解説します。
主な違反と点数一覧
行政罰の点数は、事故の状況や違反内容によって異なります。
具体的には以下の通りです。
ただし、事故の状況や状況証拠によっては、より多くの点数が加算される場合もあるため注意してください。
また、複数の違反が重なった場合は、点数が累積されます。
| 違反内容 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| スピード違反 | 1〜12点 | 速度超過の度合いによって点数が異なる |
| 信号無視 | 2点 | 赤信号、黄信号無視は一律2点 |
| 酒気帯び運転 | 0.25未満:13点 0.25以上:25点 | 25点の場合、免許取消と欠格期間2年 |
| 安全運転義務違反 | 2点 | わき見運転、よそ見運転のこと |
| 救護義務違反 | 35点 | いわゆる「ひき逃げ」のこと 物損事故を起こして措置を怠った場合は5点加算 |
点数と免許停止・取消処分
交通事故や違反で加算された点数が一定数に達すると、免許停止や免許取消といった行政処分が科せられます。
処分の内容は、過去3年間の違反歴と累積違反点数を合計して判断される仕組みです。
免許停止・取消の期間は、違反内容や累積点数、違反歴などによって異なります。
詳細については後述しているので、参考にしてください。
反則金と罰金の違い
交通違反に対しては、反則金と罰金が科される可能性があります。
反則金とは、比較的軽微な違反に対して徴収する制裁金のことです。
警察官がその場で交通反則告知書(青切符)とともに「反則金仮納付書」を交付し、違反者が期日までに指定の金融機関で納付します。
一方の罰金は、より重大な違反や反則金で処理できない違反に対して、裁判所が科す制裁金です。
裁判所に出頭し、判決を受ける必要があります。
交通事故の場合、事故の状況や違反内容によっては、反則金ではなく罰金が科される場合があります。
特に人身事故の場合は、罰金が科される可能性が高いです。
罰金の金額は、違反内容や事故の状況、裁判所の判断によって異なります。
交通事故の行政罰における免許停止・取消の基準と期間

続いて、免許停止・取消の基準と期間について解説します。
免許停止の基準と期間
違反点数が一定の基準を超えた場合、免許停止の行政罰が下されます。
運転免許が一定期間停止され、その間は運転ができません。
停止期間は、違反点数や過去の違反歴によって異なります。
具体的には、点数によって30日、60日、90日、120日、150日、180日の停止期間が設定されています。
また、違反歴があると、同じ点数でも停止期間が長くなる、もしくはより少ない点数で免許停止となる場合があるため注意してください。
例えば、違反歴がない場合であれば6点で免許停止となるケースでも、違反歴があると4点で免許停止となる可能性があります。
具体的な点数と免許停止期間は以下のとおりです。
| 過去3年間の違反歴 | 累積違反点数・免許停止期間 |
|---|---|
| なし | 6〜8点:30日間 9〜11点:60日間 12〜14点:90日間 |
| 1回 | 4〜5点:60日間 6〜7点:90日間 8〜9点:120日間 |
| 2回 | 2点:90日間 3点:120日間 4点:150日間 |
| 3回 | 2点:120日間 3点:150日間 |
| 4回以上 | 2点:150日間 3点:180日間 |
なお、停止期間中には、安全運転に必要な知識や技能の改善を目的とした「停止処分者講習」を受けることが可能です。
交通ルールやモラルの再確認ができる上に、講習内でおこなわれる考査などの結果によっては免許停止期間が短縮される場合があります。
免許取消の基準と期間
免許取消は、重大な違反や累積点数によって科される、運転免許を完全に失う行政罰です。
取消処分が決定した場合、免許を取得できるようになるまで一定期間(欠格期間)が必要になります。
欠格期間は違反内容によって1年、2年、3年、5年と異なり、期間中は運転免許の取得ができません。
免許を取り消された後、再び運転免許を取得するには、欠格期間満了後に改めて試験を受け直す必要があります。
具体的な点数と免許取消期間は以下のとおりです。
| 過去3年間の違反歴 | 累積違反点数・免許取消期間 |
|---|---|
| なし | 15〜24点:1年 25〜34点:2年 35~39点:3年 40~44点:4年 45点以上:5年 |
| 1回 | 10〜19点:1年 20〜29点:2年 30~34点:3年 35~39点:4年 40点以上:5年 |
| 2回 | 5〜14点:1年 15〜24点:2年 25~29点:3年 30~34点:4年 35点以上:5年 |
| 3回以上 | 4〜9点:1年 10〜19点:2年 20~24点:3年 25~29点:4年 30点以上:5年 |
取消処分者講習について
免許取消処分を受けた場合、欠格期間満了後に免許を取得する際に、取消処分者講習の受講が義務付けられる場合があります。
交通ルールや安全運転について再教育を受けるもので、講習を受講することで、免許取得の可能性が高まります。
講習の詳細は、警察署や運転免許試験場でご確認ください。
交通事故による行政罰の流れ
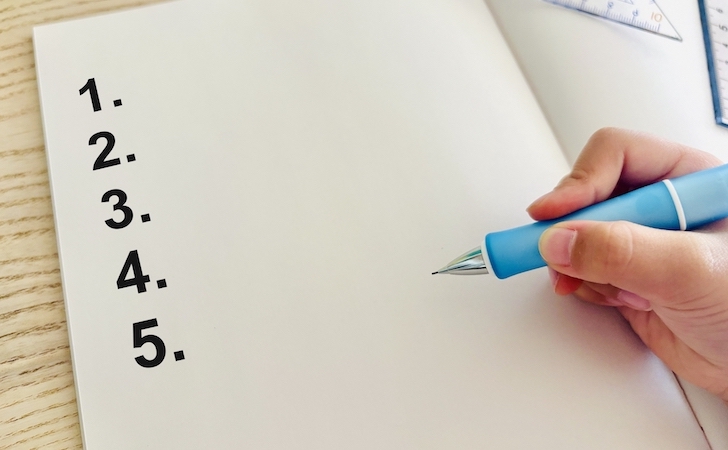
次に、交通事故による行政罰の流れについて解説します。
処分決定までの流れ
交通事故における行政処分は、警察による事故処理と手続きを経て決定されます。
そのため、処分決定までの期間は、事故の状況や手続きの複雑さによって大きく異なります。
処分決定までの流れを簡単にまとめると以下のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.事故発生 | 事故の状況を記録し、警察に届け出る |
| 2.警察による捜査 | 警察が事故の原因や責任の所在を調査する |
| 3.警察による違反・事故の精査 | 警察が事実確認を元に違反点数を検討する |
| 4.公安委員会での意見徴収 | 免許取消の場合、公安委員会から処分がある 意見徴収の場が設けられ、意見を述べることが可能 |
| 5.行政罰の決定 | 免許停止や取消などの処分が決まる |
軽微な事故の場合は、1~2カ月で処分が決定されるケースが多いですが、人身事故など複雑なケースでは、半年以上かかることもあります。
通知の受け取り方
行政処分が決定すると、運転免許センターなどから文書で通知が届きます。
通知には、処分内容(免許停止期間、点数、罰金など)が記載されています。
通知は書留郵便で送付されることが一般的です。
通知が届かない場合でも処分は有効であるため、必ず運転免許センターなどに問い合わせて確認しましょう。
通知を受け取らなかったことで、更なるペナルティを受ける可能性もあります。
また、通知書には、異議申し立ての方法なども記載されている場合があります。
処分内容に納得いかない場合は、期限内に所定の手続きにしたがって異議申し立てをおこなうことが可能です。
なお、免許停止処分を受けた場合、その期間中に運転すると無免許運転となり、刑事罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となります。
交通事故による行政罰が軽減されるケース

行政罰は刑事処分と異なり、実施機関の裁量が広く認められているものではありません。
そのため、「反省している」「被害者と示談が成立している」などの事情だけでは、処分が軽減されるのは難しいでしょう。
ただし、免許停止・取消に関しては、軽減や猶予といった制度が存在します。
軽減・猶予の制度が適用されれば、免許停止期間や欠格期間が短縮される可能性があります。
この制度を適用してもらうためには、以下のいずれかの条件に該当し「危険性が低い」と判断されることが必要です。
「危険性が低い」とは、「違反傾向がない」ことを意味します。
- 交通事故の被害状況、またはドライバーの過失の程度が軽微
- 災害や急病人の搬送など、やむを得ない状況での交通違反
- 他者から強制されて違反行為をおこなうなど、やむを得ない事情があった
- 健康状態や年齢など、被害者の事情により重大な結果が生じた
- 被害者が加害者の家族や親戚
- その他、加害者に危険性が低い事情があり、改善が期待できる場合
行政処分を軽減してもらいたい場合には、公安委員会から意見聴取の呼出状が届いた際に必ず出席し、自身に危険性がないことや事故のやむを得ない事情を説明することが重要です。
ただし、処分の軽減は特別な事情があると認められた人のみ受けられるものであり、主張すれば必ず軽減されるものではないことを理解しておいてください。
出典:運転免許の効力の停止等の処分量定の特例及び軽減の基準について|警察庁
交通事故を起こした際に取るべき行動

交通事故を起こしてしまったら、パニックになるのも無理はありません。
しかし、冷静な対応が自身や事故相手、周囲の道路利用者の安全を左右し、今後の行政罰や損害賠償請求にも大きく影響します。
まずは、以下の流れを踏まえて行動しましょう。
事故発生直後に取るべき行動
事故直後は、まず自分の安全を確保することが最優先です。
道路の状況によっては、二次災害の危険性もあります。
安全な場所に移動し、ケガの有無を確認しましょう。
そして、以下の行動を心がけてください。
| 行動 | 詳細 |
|---|---|
| 安全確認 | 相手と自分のケガの有無を確認し、必要であれば救急車を呼びましょう。周囲の安全も確認し、二次災害を防ぎます。 |
| 事故状況の確認 | 事故の状況を冷静に観察し、メモを取ったり、写真や動画を撮影したりしましょう。ただし、危険な状態での撮影は避けましょう。 |
| 目撃者の確保 | 事故を目撃した人がいれば、連絡先を聞き、証言を確保しましょう。 |
| 車両の位置の確認 | 車両の位置を移動させる場合は、警察の指示を仰ぎましょう。勝手に移動させると、事故状況の証拠隠滅と見なされる可能性があります。 |
| 冷静を保つ | 相手と感情的に言い争うことは避け、冷静に対応しましょう。 |
負傷者の救護
交通事故による負傷者がいれば、すぐに救護しましょう。
周囲の人に応援を頼むとともに、119番通報(消防署への救急車の要請)やAEDの手配を依頼します。
また、
- 負傷者に応急救護処置をおこなう
- 負傷者を安全な場所に移動させる
- 負傷者を病院に搬送する
といったことが必要になる場合もあります。
「軽傷だから救護は必要ない」と判断してその場を立ち去れば、ひき逃げと見なされ、処罰の対象になります。
必ず負傷者を救護するようにしましょう。
警察への届け出と事故後の手続き
交通事故が発生したら、必ず警察に届け出ましょう。
人身事故の場合はもちろん、物損事故であっても届け出は必要です。
届け出を怠ると、罰則が科せられる可能性があります。
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 110番通報 | 事故(人身事故、物損事故ともに)が発生したら、すぐに110番通報をおこないましょう。警察署にも連絡し、事故の届け出をおこないましょう。 |
| 事故状況の報告 | 警察官に事故の状況を正確に報告しましょう。写真や動画があれば提示しましょう。 |
| 現場検証 | 警察官による現場検証に協力しましょう。 |
| 事故証明書の取得 | 事故証明書は、保険会社への連絡や損害賠償請求などに必要になりますので、必ず取得しましょう。 |
| 治療 | ケガをした場合は、すぐに病院で治療を受け、診断書を発行してもらいましょう。 |
保険会社への連絡と対応
警察への届け出が終わったら、次は自分の保険会社に連絡しましょう。
事故状況を詳しく説明し、指示にしたがって対応しましょう。
保険会社は事故処理のプロフェッショナルなので、彼らのアドバイスにしたがうことが重要です。
| 対応 | 詳細 |
|---|---|
| 事故状況の報告 | 事故の状況を正確に報告しましょう。また、事故報告書を受け取れるように、現場検証に来た警察官に担当警察署と電話番号を聞き、保険会社へ伝えましょう。 |
| 示談交渉の依頼 | 必要に応じて、保険会社に示談交渉を依頼しましょう。 |
弁護士への相談
法律の知識がないと適切な対応が難しい場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
行政処分に関する手続きや被害者との示談交渉、刑事裁判など、弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けながら、円滑に問題解決を進めることが可能です。
特に、人身事故や物損事故、ひき逃げなど、重大な事故を起こしてしまった場合は、弁護士への相談が強く推奨されます。
専門家の力を借りることで、精神的な負担を軽減し、最善の解決策を見つけられるでしょう。
まとめ:交通事故を起こさないように、日頃から安全運転を心がけよう

交通事故は、加害者だけでなく被害者にも大きな影響を与える重大な事件です。
事故を起こしてしまった場合、行政罰だけでなく、刑事罰や民事責任を問われる可能性もあります。
事故を起こさないようにするためには、日頃から安全運転を意識することが重要です。
ぜひ本記事で学んだ知識を活かし、安全運転に努めてください。
なお、社内の交通安全意識の向上には、安全運転教育の実施が効果的です。
JAFメディアワークスでは、JAFが長年培ってきた交通安全の知見とノウハウを凝縮したeラーニング教材「JAF交通安全トレーニング」を提供しています。
以下の資料ではJAFトレの活用事例や安全運転教育の効果を最大化する方法について解説しているので、ぜひ社内の交通安全意識の向上に役立ててください。
若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因



















