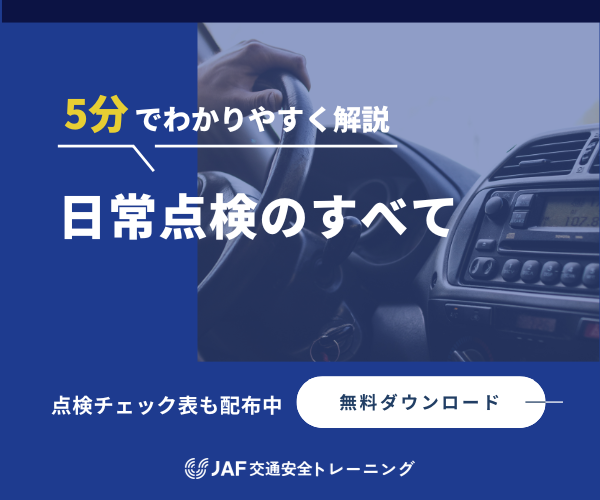オートパイロット(自動運転)とは、飛行機や船、自動車などの乗り物を人の手を介さずに自動で運転する技術のことです。
自動車におけるオートパイロット技術も日々進歩しており、完全な自動運転こそ実現はしていないものの、その技術を活かした車両は日常生活でも利用されています。
本記事では、自動車のオートパイロットシステムの詳細や普及によるメリット、日本における現状などについて解説します。
\ 今すぐ使えるチェックシート付 /
目次
自動車におけるオートパイロット(自動運転)とは

自動車におけるオートパイロットとは、ドライバーではなくシステムが運転操作に関わる判断や操作の代わりにおこなって、車両を走らせることを指します。
ハンドル操作やアクセル・ブレーキ操作など、一部の操作をサポートするシステムもオートパイロットに含まれており、アメリカのSAE(自動車技術開)が示す基準を基に「レベル0」から「レベル5」までの6段階でレベル分けがされています。
各レベルの概要は以下の通りです。
| レベル | 内容 | 運転操作の主体 |
|---|---|---|
| レベル0 | すべドライバーが操作をおこなう状態 | ドライバー |
| レベル1 | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが部分的に自動化された状態 | ドライバー |
| レベル2 | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作の両方が部分的に自動化された状態 | ドライバー |
| レベル3 | システムがすべての運転タスクを実施するがシステムの介入・要求に対してドライバーが適切に対応することが必要な状態 | システム |
| レベル4 | 特定条件下においてシステムがすべての運転タスクを実施する状態 | システム |
| レベル5 | システムがすべての運転タスクを実施する状態 | システム |
参照:国土交通省「自動運転車両の呼称」
日本においては、2021年3月にレベル3車両が一般向けに販売開始されており、レベル4についても公道以外での運用が、少数ながら開始されています。
自動運転の各レベルでできること

自動運転の各レベルでできることの詳細を解説しますので、自動運転レベルについて、詳しく知りたい方は参考にしてください。
レベル1
レベル1では、アクセル・ブレーキ操作もしくはハンドル操作のどちらかをシステムがサポートが可能です。
具体的なシステムとしては、前を走る車両に追従するシステム「ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)」や衝突被害軽減ブレーキなどがあります。
レベル2
レベル2では、アクセル・ブレーキ操作とハンドル操作の両方をサポート可能です。
具体的には、レベル1で用いられているシステムを同時に使用する、といった内容です。
一口にレベル2といっても、初期と後期のシステムでは性能が異なり、性能が高いレベル2搭載車両であれば、特定条件下でハンドルから手を離せる「ハンズオフ(ハンズフリー)」運転が可能となります。
レベル2における運転操作の主体はあくまでドライバーのため、運転席から離れることはできませんが、運転にかかる負担やストレスをある程度の軽減することが可能です。
レベル3
レベル3では特定条件下においてのみ、システム側にすべての運転操作を任せることが可能です。
しかし、TORと呼ばれるシステム側からの運転交代要求が出された場合は、即座に運転を代わる必要があるため、走行中に運転席から離れることはできません。
レベル3は自動運転のスタートとも言える状態であり、自動運転システム作動時であれば運転中の監視義務を免れること(アイズフリー運転)が可能です。
レベル4
レベル4は、レベル3の上位互換とも言える状態で、より広い範囲での自動運転が可能となります。
自動運転が対応できる範囲を逸脱した場合であっても、システム側が自動で車両を停止させるなど、ドライバーによる操作を不要とする高度な運転が可能です。
以上のように、条件さえあえばドライバーによる操作がほとんど必要ないことから「ドライバーフリー」と呼ばれることもあります。
レベル5
レベル5は、あらゆる条件下においてもすべてシステム側が運転をおこなってくれる状態です。
レベル4でも自動運転は可能ですが、路面状況や天候、乗車人数など条件によっては、ドライバーが運転しなければなりません。
その点、レベル5はあらゆる条件下でもすべてシステム側が運転をおこなってくれるため、タクシー利用に近い感覚で移動することが可能となります。
2030年代の実現をめどに研究が進められていますが、まだまだ課題が多いのが現状です。
【追加】オートパイロットのシステムに使われている技術

オートパイロットシステムは、ドライバーが運転時におこなっている認知や予測、操作などを、さまざまな技術を組み合わせることで代行しています。
ここでは、オートパイロットのシステムに使われている技術について解説します。
【追加】位置の特定・周辺の認識をする技術
一つ目は、車両の位置の特定や周辺を認識する技術です。
具体的には、以下のような技術が用いられています。
| 位置特定技術 | ・車両の現在位置を特定する技術 ・代表的なものはカーナビゲーションに使われているGPS ・現在では複数の技術を活用して、より正確な車両位置を特定するのが主流となっている ・誤差数センチレベルの測位を実現するQZSSや、高精度3次元地図を構築するSLAMなどの技術が活用されている |
| 認識技術 | ・カメラやセンサーなどを使って周辺環境を正確に認識する技術 ・現在はLiDAR(ライダー)と呼ばれるレーザー照射によって対象物との距離・位置・形状を高い精度で測定する技術に注目が集まっている |
| 通信技術 | ・道路工事や渋滞などの情報をリアルタイムで受信したり、自分の車の状況を他車両に発信したりするための技術 ・膨大な量のデータを高速通信する必要があるため、「5G」をはじめとした通信技術が必要とされている |
【追加】状況の分析・判断をおこなう技術
二つ目は、状況の分析・判断をおこなうための技術です。
具体的には、以下のような技術が用いられています。
| AI技術 | ・AI技術は人間に代わり、信号や標識、路面標示に合わせた対応をしたり、障害物や歩行者を避けたりなど、認識した物体の識別・操作の決定を行う際に活用される技術 ・オートパイロットにおいて中心となる機能 ・マシンラーニング(機械学習)・ディープラーニング(深層学習)など、AIの学習方法が大きく進展したことが自動運転の実現・発展に大きな影響を与えている |
| 予測技術 | ・周囲に車両や歩行者の動きや道路状況、天候などの条件から危険を予測してする技術 ・「前方車両との距離が近い」「激しい雨が降っている」など、危険につながる状況を察知した際にAIと連動をおこなう |
| プランニング技術 | ・渋滞や信号の状況に合わせて走行ルートの調整や決定をおこなう技術 ・目的地までの最適なルート設定だけでなく、経由地があった場合に適切なルートを導き出す性能が求められる |
【追加】ドライバーの行動を確認・対応する技術
三つ目は、ドライバーの行動を確認・対応する技術です。
従来の自動車運転ではドライバーが直接操作していた部分を、オートパイロットにおいてはシステムが自動でおこなう必要があります。
そのため、オートパイロットではシステムが搭乗者の意思や状態を確認し、必要な動作をおこなうことが求められます。
例えば、レベル3オートパイロットでの、システムが搭乗者が居眠りをしていないか確認し、居眠りをしている場合は自動で停車する機能などです。
この技術が発展することで、将来的には搭乗者の姿勢や動きに応じて、車内における安全性を高めたり、要望をくみ取ったりする機能へつながることが期待されています。
オートパイロット普及によるメリット

オートパイロットが普及することで得られるメリットを個人・社会それぞれの視点から解説します。
個人のメリット
オートパイロット普及による個人のメリットは、これまで運転に使っていた時間を自由に使えるようになる点です。
レベル5のオートパイロットが実現した場合、ドライバーはタクシーにおける乗客と同じような状態になります。
運転席そのものが不要となるため、従来以上に車内のレイアウトを自由に変えることが可能です。
その結果、仕事や読書など、好きなように時間を使用できるようになるでしょう。
また、公共交通機関が十分ではない土地では、運転に不安があっても車を使わざるを得ないケースも少なくありません。
自動車でなければ行けない場所にも、安心・安全に移動できるのは、運転に不安を抱える方には大きなメリットです。
社会のメリット
オートパイロットの普及によって、社会が得られるメリットは「安全な道路交通の実現」です。
国土交通省が2022年に発表した資料によると、交通事故による死亡事故発生件数の95%がドライバーの違反に起因しています。
オートパイロットは原則として道路交通法にのっとって運転するため、ドライバーの違反を原因とした事故は減少すると考えられます。
また、事故原因の一つでもある飲酒を原因とした事故も減少が予想されるため、総じて交通事故の大幅な減少に期待できるでしょう。
参照:国土交通省「自動運転に関する昨今の国内・国際基準の動向」
日本におけるオートパイロット普及の現状

日本におけるオートパイロットの普及状況は以下の通りです。
| 自動運転レベル | 普及の状況 |
|---|---|
| レベル1 | 現在製造されている車両にはほとんど搭載されている |
| レベル2 | 国内主要メーカー続々と搭載車両を製造しており今後も広がる見込み |
| レベル3 | ホンダが世界初自動運転レベル3搭載車「レジェンド」を発売したが本格的な普及はこれから |
| レベル4 | 2023年4月の法改正により走行が可能となった。それを受けて一部地域では実証をかねた運用がされている |
| レベル5 | 関連企業により開発が進められている |
現状、日本においてある程度普及していると言えるのは、レベル2までの車両です。
レベル3搭載車については、ホンダが2021年3月に「レジェンド」のリース販売をおこないましたが100台限定でした。
他メーカーについても、2024年9月現在ではレベル3搭載車は販売していないため、本格的な普及はこれからと言えるでしょう。
レベル4については、2023年4月に法改正によって走行が解禁されたばかりです。
これを受けて、福井県永平寺町の自動運転移動サービス「ZEN drive」や、神奈川県相模原市内にある物流拠点「GLP ALFALINK相模原」内を走行する車両「BOLDLY」などが運行を開始しています。
日本におけるオートパイロットレベル4の現状

2023年4月に「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、日本におけるレベル4自動運転が解禁されました。
レベル4のオートパイロットを利用できるのは、許可を得た事業者のみとなっており、事前に公安委員会による審査を受ける必要があります。
また、許可を得た事業者は以下のルールを遵守した上で運行しなければなりません。
| ・特定自動運行計画の遵守 ・特定自動運行業務従事者に対する教育 ・特定自動運行主任者・現場措置業務実施者の指定 ・遠隔監視装置を管理する場所に備え付ける措置 ・特定自動運行主任者を配置する措置 ・特定自動運行において交通事故があった場合の措置 ・「特定自動運行中」である旨を見やすい箇所に表示をする措置 ・運行記録の保存措置 |
これらのルールを違反した場合、許可の取り消しや刑事罰などが科される可能性があります。
【追加】オートパイロットレベル4の普及により期待できる効果

オートパイロットレベル4が普及すると、現在において社会問題となっている課題の改善につながります。
以下は、オートパイロットレベル4の普及により期待される効果の一例です。
- 交通事故の削減
- 渋滞の緩和
- 地方における公共交通網の維持
- 運送業などにおけるドライバー不足の解消
特に交通事故の削減や、減少傾向にある地方の公共交通網の維持は、健康や生活に大きく関わる部分であるため、非常に大きなメリットと言えるでしょう。
まとめ:オートパイロットレベル4はまだ普及していないのが現状

オートパイロットとは、ドライバーではなくシステムが運転操作に関わる判断や操作のすべてを代わりにおこなって、車両を走らせる技術のことです。
オートパイロット技術は日々進歩しており、日本ではレベル2のオートパイロットが搭載されている車両が広がりを見せています。
レベル3やレベル4も、少しずつではありますがさまざまな形で利用・研究されており、個人の車や社用車として使える日も遠くはないでしょう。
オートパイロットは、安全な交通事故の削減につながるなど、社会的にも大きな意味のある技術です。
少しでも安心して暮らせる社会が実現するよう、オートパイロットの普及に期待しましょう。