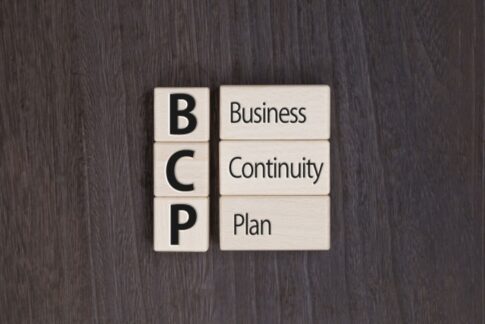政府は、2050年までにカーボンニュートラル達成(温室効果ガスの排出量と吸収量の差し引きを実質ゼロにする)を目指すことを宣言しています。
そこで本記事では、社用車の脱炭素化について、国内外の動向やメリット・デメリット、導入の際の課題と解決策について解説します。
明日からの具体的なアクションプランを描けるよう、必要な情報を網羅的かつわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
出典:更なる省エネ・非化石転換・DRの促進に向けた政策について|経済産業省
\ これを見ればすべて解決!/
目次
そもそも「脱炭素」とは

脱炭素とは、地球温暖化の主な原因とされる二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの排出量を、実質ゼロにすることを目指す取り組みです。
具体的には、化石燃料の使用を減らし、太陽光や風力といった再生可能エネルギーの利用を増やすことで、排出量を削減します。
どうしても削減しきれない排出量については、森林の保護・育成などによって吸収量を増やすことで相殺し、社会全体として排出量を「実質ゼロ(カーボンニュートラル)」にすることを目指します。
この世界的な目標達成に向け、企業も積極的な行動が必須です。
2025年に社用車の脱炭素を義務化する法律はない

2025年7月時点で、社用車の脱炭素(EV化など)を直接的に義務付ける法律や規制はありません。
では、なぜ「2025年」という年が重要視されているのでしょうか。
それは、多くの企業が、環境目標の中間年として2025年を設定しているためです。
例えば、ある企業は「2025年度に2013年度比で30%削減」といった目標を掲げています。
法的な強制力はなくとも、こうした企業の自主的な取り組みが社会全体の潮流となり、「2025年までに何らかの対策を講じなければならない」という気運が高まっているのです。
つまり、法規制の有無に関わらず、社会的な要請や企業の競争力維持の観点から、脱炭素化への対応は避けて通れない課題となっています。
なぜ社用車の脱炭素化が急務なのか?国内外の最新動向

社用車の脱炭素化は、単なる環境貢献活動ではありません。
今や企業の存続に関わる重要な経営課題として認識されています。
その背景には、世界的な規制強化の流れと、日本が国として掲げる高い目標があります。
マクロな視点から国内外の動向を理解することで、自社の取り組みの必要性を経営層へも説明しやすくなるでしょう。
世界の潮流:2035年に向けた欧州の動きと環境規制の強化
世界の環境規制をリードしているのが欧州連合(EU)です。
2022年10月、EUでは、2035年までにハイブリッド車(HV)を含むガソリン車の新車販売を事実上禁止する方針を決定しました。
この決定は、世界の自動車メーカーに大きな影響を与えています。
トヨタやフォルクスワーゲンなどのグローバル企業は、EV(電気自動車)の開発・生産へ大きく舵を切らざるを得なくなりました。
日本企業もこの潮流と無関係ではありません。
海外との取引やサプライチェーンを考えれば、欧州の厳しい環境基準に対応していくことが、今後の事業継続において不可欠となります。
日本の目標:「2050年カーボンニュートラル」と企業の責任
日本政府も、2020年に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。
これは、2050年までに温室効果ガスの排出を、全体としてゼロにすることを目指すものです。
さらに、その中間目標として「2030年度に2013年度比で46%削減」という非常に高い目標を掲げています。
そのため、企業が保有する社用車をガソリン車からEVなどに切り替えていくことは、単なる努力目標ではなく、社会の一員としての責任であると言えるでしょう。
出典:2050年カーボンニュートラルの実現に向けて|環境省/日本のNDC(国が決定する貢献)|環境省
社用車の脱炭素化を進めるメリット・デメリット

社用車をEV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)に切り替えることは、脱炭素化における最も効果的な手段です。
走行中にCO2を排出しないため、環境への貢献度が非常に高いのが特徴です。
また、脱炭素に積極的に取り組む姿勢は、顧客や取引先、投資家からの評価を高め、企業のブランドイメージ向上にもつながります。
経済的なメリットも大きく、割安な夜間電力を活用すれば、ガソリン価格の変動に影響されることもなく、燃料費を大幅に削減できます。
ただし、車両本体価格がガソリン車に比べて高額であることや、充電設備の設置が必要になる点がデメリットです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・CO2排出量を大幅に削減 ・企業イメージの向上 ・燃料費・維持費の削減 | ・車両の購入価格が高い ・充電インフラの整備が必要 ・航続距離や充電時間に課題 |
なお、社用車をEVにするメリットは、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
また、以下の記事では水素を燃料とする電気自動車「FCEV(FCV)」について解説しています。
こちらもぜひ、ご覧ください。
社用車の脱炭素化への課題と対策:コスト・インフラ・運用

EV導入を検討する際、多くの担当者様が直面するのが「コスト」「インフラ」「運用」という3つの大きな壁です。
「車両価格が高い」「充電設備はどうすれば良いのか」「日々の業務に支障は出ないか」といった不安は尽きません。
しかし、これらの課題には、それぞれ有効な解決策があります。
以下では、社用車の脱炭素化への課題に対する、具体的な解決策を解説します。
導入へのハードルを一つひとつクリアしていきましょう。
コスト|補助金や税制優遇をフル活用しよう
EV導入の最大の障壁である初期コストは、国の手厚い支援策を活用することで大幅に軽減できます。
代表的な制度を理解し、賢く利用しましょう。
| 支援策の種類 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| CEV補助金 | クリーンエネルギー車購入時に国から支給される補助金で、車種や性能によって金額が変動する | 予算の上限があり、申請期間が定められているため、常に最新情報の確認が必要 |
| グリーン化特例 | 燃費性能の良い車に対し、翌年度の自動車税(種別割)が軽減される | EVは概ね75%軽減の対象となる |
| 環境性能割 | 車の購入時にかかる税金で、燃費性能に応じて税率が変動する | EVは非課税 |
| エコカー減税 | 燃費性能の良い車に対し、新規登録時と初回車検時の自動車重量税が免税・減税される | EVは新規登録時・初回車検時ともに免税 |
インフラ|自社に最適な充電設備の選び方と設置手順
「充電はどうすれば良いのか?」という課題には、自社の事業所に充電設備を設置することが基本的な解決策となります。
充電器には主に「普通充電器」と「急速充電器」の2種類があり、用途に応じて選ぶことが重要です。
| 充電器の種類 | 特徴 | 充電時間(目安) | 設置費用(目安) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 普通充電器(AC) | 比較的コストパフォーマンスが高く、電力契約の変更が不要な場合も多い | 6〜12時間 | 約10万円〜 | 夜間など、駐車時間が長い場合の充電(基礎充電) |
| 急速充電器(DC) | 短時間で充電可能だが、設置費用が高く、高圧電力の契約が必要 | 30分〜1時間 | 約100万円〜 | 外出先での継ぎ足し充電、緊急時の充電 |
多くの企業では、終業後に駐車している間に充電が完了する「普通充電器」がコストと運用のバランスに優れています。
設置までの基本的な流れは以下の通りです。
- 設置場所の選定と調査:駐車場のレイアウトや電源からの距離を確認
- 施工業者へ相談・見積もり:複数の業者から見積もりを取り、比較検討
- 電力会社への申請:必要に応じて電力契約の変更や増設工事を申請
- 補助金の申請:充電設備にも利用できる補助金があるため、事前に確認・申請
- 設置工事の実施:専門業者による工事を実施
- 運用開始:利用ルールなどを定め、従業員へ周知
また、自社での設置が難しい場合は、リース会社が充電器の設置まで含めたプランを提供している場合や、外部の充電ネットワークと法人契約を結ぶといった選択肢もあります。
運用|航続距離の不安解消と安全な運用のポイント
「営業先で電池が切れたらどうしよう」「充電の管理が煩雑になりそう」などの運用面の不安は、適切な対策で解消できます。
まず、航続距離については、自社の車両が1日に走行する平均距離を把握し、それを十分に満たす車種を選ぶことが基本です。
次に、日々の運用を円滑に進めるためのポイントをまとめました。
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 充電のタイミング管理 | ・帰社後の夜間充電を基本ルールとする ・テレマティクスで充電状況を一元管理する |
| 外出先での充電 | ・充電スポット検索アプリを導入する ・主要な充電ネットワークの法人カードを契約する |
| 電気料金の最適化 | ・深夜電力が割安になる料金プランへ変更する ・AIを活用し、電力需要を予測して最適な時間に充電するシステムを導入する |
| 事故リスクへの対応 | ・EV特有の静音性や加速性能に起因する事故リスクを学ぶ ・交通安全教育を実施する |
特に見落とされがちなのが、安全運転教育です。
EVはガソリン車と運転感覚が異なるため、ドライバーがその特性を正しく理解し、安全に運転するための教育が不可欠です。
企業向けの研修や交通安全に関する教材を活用するなどして、従業員の安全意識とリスク管理能力を高めることは、企業の重要な責任と言えるでしょう。
まとめ:計画的に社用車の脱炭素化を進めよう

社用車の脱炭素化は、もはや単なるコスト削減や義務ではありません。
計画的に取り組みを進めることで、環境、社会、そして経済のすべてにおいてプラスの効果を生み出す「未来への投資」です。
まずは自社の車両利用状況の把握からはじめ、この記事を参考に、着実な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
社用車の脱炭素化を進めるには、安全運転管理者を中心とした推進体制を整えることが重要です。
JAFメディアワークスでは、安全運転管理者の仕事内容や選任方法についてまとめた資料「安全運転管理者の解説本」を提供しています。
社用車の管理・運用を進める上で、ぜひ参考にしてください。
\ これを見ればすべて解決!/