最近話題の「走行距離課税」、それは車で走った距離によって課税されるという新しい税金の形態です。
しかし、
- どういった背景から導入が議論されているのか
- 具体的にいつから始まるのか
- 実際に課税されると自分の生活にはどのような影響があるのか
など、その全貌はまだまだ不透明です。
この記事では、走行距離課税の基本的な仕組みから導入の背景、海外の事例、メリット・デメリットまでを徹底解説します。
これからの車の運用を考える上で欠かせない情報を、ぜひこの記事で入手してください。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /
走行距離課税とは
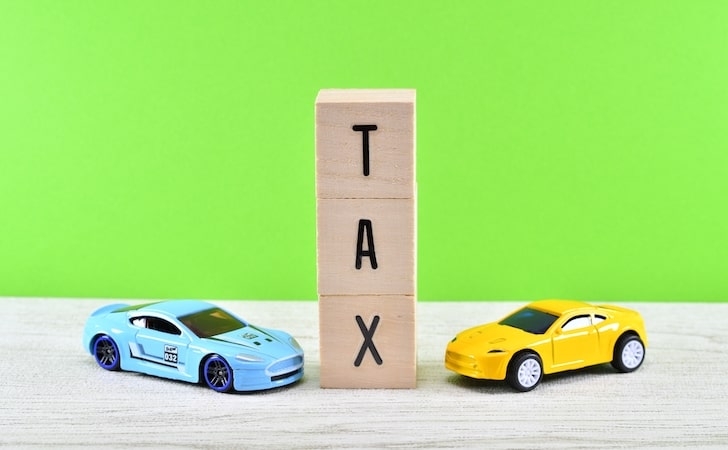
走行距離課税とは、自動車が走行した距離に応じて課税される新しい税金の形態です。
従来の自動車税や自動車重量税とは異なり、車両や所有そのものではなく、使用量(走行距離)に応じて税金が課される点が大きな特徴です。
この制度が導入されると、走行距離が長いほど税負担が増え、走行距離が短いほど税負担が軽減されることになります。
そのため、車の利用頻度が少ないドライバーにとっては、税負担を抑えられる可能性があります。
走行距離課税が議論されている背景
走行距離課税が議論される背景には、いくつかの要因があります。
具体的には以下の通りです。
| 背景 | 詳細 |
|---|---|
| 道路整備費の確保 | 道路の維持・管理には多額の費用がかかります。走行距離に応じて課税することで、道路の利用頻度に応じた負担を求めることが可能になり、道路整備費の安定的な確保につながると期待されています。 |
| 公平性の確保 | 従来の自動車税や自動車重量税は、車の所有に対して課税されるため、走行距離が短いドライバーにとっては不公平感がありました。走行距離課税は、車の利用実態に応じて課税されるため、より公平な税制であると考えられています。 |
| 環境負荷の軽減 | 車の利用を抑制し、公共交通機関の利用を促進することで、環境負荷の軽減につながる可能性があります。 |
以上の背景から、走行距離課税は今後の自動車税制のあり方を検討する上で、重要な選択肢の一つとして議論されています。
走行距離課税の仕組み
走行距離課税を導入する上で、正確な走行距離の把握が不可欠です。
そのために、以下のような仕組みが検討されています。
| 仕組み | 詳細 |
|---|---|
| 車載器の設置 | 専用の車載器を設置し、走行距離を計測する方法です。車載器には、GPS機能や通信機能が搭載されており、走行距離データを自動的に送信できます。 |
| オドメーターの活用 | 車両に搭載されているオドメーター(走行距離計)の数値を定期的に申告する方法です。ただし、改ざんのリスクがあるため、ほかの方法と組み合わせて利用されることが考えられます。 |
以上の技術を活用することで、走行距離を正確に把握し、公平な課税を実現することが可能になります。
ただし、プライバシーへの配慮や、システムの導入・維持コストなどが課題として挙げられます。
日本での導入時期や具体的な税率・税額は未定
日本で走行距離課税の導入が具体的に検討され始めたのは、2018年頃からです。
しかし、本格的に注目を集めるようになったのは、2022年10月に鈴木俊一財務相が参議院予算委員会でEVに対する走行距離課税の導入について言及したことがきっかけです。
現状、具体的な導入時期や税率・税額などは未定ですが、国土交通省や財務省を中心に、さまざまな検討が進められています。
海外における走行距離課税の例

走行距離課税は、すでに海外の一部の国や地域で導入されています。
ニュージーランド
世界で最も早く走行距離課税(RUC: Road User Charges)を導入したのが、ニュージーランドです。
「道路利用車料」として知られており、対象は税金がかけられていないディーゼル車や、総重量が3.5トンを超える大型車両です。
RUC制度では、走行距離記録装置または自動車の距離計を用いて、実際に走行した距離を基に料金が計算されます。
料金は車両のタイプとその積載重量に応じて設定されており、1,000km 単位で事前にライセンスを購入するか、専用車載器でRUCライセンスを管理する仕組みです。
ニュージーランドにおけるこの制度は、道路の使用頻度に応じて利用者が負担するという公平な仕組みを実現しており、道路インフラの維持費を効率的にまかなうモデルとして定着しています。
※参考:2.欧州における走行距離課金の導入及び検討状況│公益財団法人高速道路調査会
アメリカ(オレゴン州)
アメリカのオレゴン州では、2度の実証実験ののち2015年に「OReGO」というプログラムで、走行距離に応じて課税するシステムを導入しています。
参加者は、GPS追跡装置または走行距離計を搭載した車両を使用して走行距離を記録し、走行距離に応じて税金を支払います。
このプログラムは、ガソリン税収の減少に対応するために導入されました。
※参考:令和4年度高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた研究開発・実証事業(CASE 等による産業構造変化を見据えた国内技術動向調査)調査報告書(公表用)│経済産業省
ドイツ
ドイツでは、2005年からトラックを対象とした走行距離課税を導入しています。
この課税は、道路の維持管理費をまかなうために導入されました。
課税対象となるのは12トン以上のトラックで、GPSを利用して走行距離を記録し、課税額を算出します。
2015年10月からは、対象車両が重量 7.5 トン以上に拡大されました。
このシステムは、道路の維持管理費の確保に貢献している一方で、物流コストの増加につながっているという指摘もあります。
※参考:2.欧州における走行距離課金の導入及び検討状況│公益財団法人高速道路調査会
走行距離課税のメリット

走行距離課税の導入は、一見すると負担増のように感じられますが、実はメリットも存在します。
ガソリン車とエコカーの不公平感が解消される
現在の自動車関連税制では、ガソリン車や大排気量車に税負担が集中し、エコカー(電気自動車やハイブリッド車など)が優遇される傾向があります。
これは、エコカーの普及を促進するための政策的な措置ですが、公平とは言えないという声もあります。
走行距離課税が導入されれば、動力源の種類に関わらず、実際に道路を利用した距離に応じて課税されるため、ガソリン車とエコカーの税負担の不均衡が是正されると考える方もいるようです。
走行距離の短い人が得をする
現在の自動車税は、車の種類や排気量によって一律に課税されるため、年間走行距離が短い人にとっては「あまり車を利用しなくても税金を支払わなければならない」という不満がありました。
走行距離課税が導入されれば、走行距離が短い人は税負担が軽減されるため、これまで不公平だと感じていた人にとってはメリットになり得るという考え方もあります。
例えば、週末に近所の買い物にしか車を使わない人や、ほとんど車に乗らない人などは、税負担が軽くなる可能性があります。
排気量が大きい車は減税になる可能性がある
現行の自動車税は排気量に応じて税額が上がります。
しかし、走行距離課税が導入された場合、排気量の大きい車でも、走行距離が短ければ税金が安くなるケースもあり得るでしょう。
必ずしもすべてのケースで減税となるわけではありませんが、走行距離が短い場合は、現行の自動車税よりも税負担が軽くなる可能性があります。
走行距離課税のデメリット

一方で、走行距離課税を導入すると、以下のようなデメリットが生じます。
物流に大きな影響を与え、物価が高騰する
走行距離課税が導入された場合、懸念されるのが物流業界への影響です。
商品の輸送コストが増加し、その結果、物価が高騰する可能性があります。
特に、長距離輸送を必要とする地域では、その影響はより顕著です。
物流コストの上昇は、最終的には消費者が負担することになり、家計を圧迫する要因となり得ます。
地方在住者への負担が増える
地方は都市部に比べると公共交通機関が発達していない地域が多く、生活のためには自動車の利用が不可欠です。
そのため、走行距離が長くなる傾向にあり、走行距離課税が導入された場合、都市部と比較して地方在住者の負担が大きくなることが懸念されます。
これは、地方経済の活性化を妨げる要因にもなりかねません。
ガソリン税に走行距離課税が加わる可能性がある
現在、自動車には自動車税やガソリン税など、さまざまな税金が課せられています。
走行距離課税が導入されると、ガソリン車を利用する人にとっては、ガソリン税と走行距離課税の二重課税になる可能性があります。
さらに、ガソリンを購入する際に消費税がかかることを考慮すると、三重課税です。
このような多重課税によって、自動車ユーザーの負担がさらに大きくなる可能性があります。
カーシェアリングやレンタカーの値上げにつながる
走行距離課税は、自動車を所有していないカーシェアリングやレンタカーの利用者にも影響を及ぼす可能性があります。
これらのサービスを提供する事業者は走行距離に応じて課税されるため、そのコストを利用料金に転嫁する可能性があります。
その結果、カーシェアリングやレンタカーの利用料金が値上げされ、手軽に利用できなくなるかもしれません。
バスやタクシーの値上げにつながる
公共交通機関であるバスやタクシーの値上げが懸念される点も、走行距離課税のデメリットです。
走行距離に応じて課税されるため、そのコストを運賃に転嫁することが想定されます。
その結果、バスやタクシーの運賃が値上げされ、公共交通機関の利用を抑制する可能性があります。
プライバシー侵害のリスクがある
走行距離課税を計算するには、GPSや車載器などを用いて走行距離を把握する必要があります。
これらの技術は個人の移動履歴を詳細に記録することが可能であり、プライバシー侵害のリスクが懸念されます。
収集されたデータが適切に管理されず、漏洩や不正利用された場合、個人の生活が監視されるような状況になりかねません。
個人情報の保護に関する厳格なルールと、監視体制の構築が不可欠です。
まとめ:走行距離課税の導入には多くの課題がある

走行距離課税は、ガソリン税に代わる新たな税制として導入が検討されています。
ガソリン車とエコカーの税負担の公平性を是正し、走行距離の短い人が恩恵を受ける可能性がある一方で、物流コストの上昇や地方在住者への負担増など、多くの課題も抱えています。
導入時期や料金体系など、具体的な制度設計はまだ不透明な部分が多いですが、導入されれば自動車の利用頻度や生活スタイルに大きな変化をもたらす可能性は否定できません。
私たち一人ひとりの生活に深く関わるトピックなので、走行距離課税について理解を深め、今後の議論の行方を見守っていきましょう。
なお、JAFメディアワークスでは、企業の交通安全教育用のeラーニング教材「JAF交通安全トレーニング」を提供しています。
従業員の交通安全意識の向上に、ぜひご活用ください。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /


















