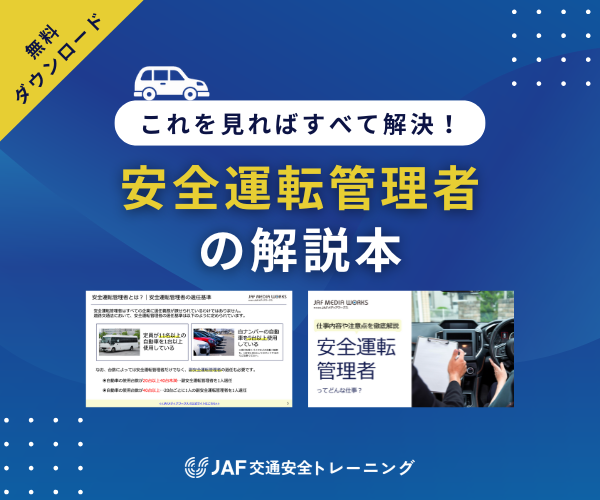運送業界で初めて運行管理者を任された担当者や、ドライバーとの兼任を検討している中小企業の経営者の中には、「運行管理者は運転してはいけない」と勘違いされてしまう方が少なくないようです。
結論からいえば「運行管理者でも運転手との兼任は可能」であるものの、そのためには運行管理体制の条件を満たす必要があります。
複雑に見える制度を分かりやすく整理することで、自社の安全管理体制のアップデートに繋げましょう。
この記事では、運転手と運行管理者の兼任が許可される一例から、不在時のリスクや対策、最新の法令を踏まえて網羅的に解説していきます。
\ これを見ればすべて解決!/
目次
運行管理者と運転者の関係

運行管理者は、営業所ごとに配置が義務付けられた、いわば自動車運送事業の安全マネジメント責任者として、点呼や運行指示、労務管理などを担う立場の人を指します。
運行管理者と安全運転管理者の違いについてはこちらの記事をご覧ください。
一方、運転者は実際にハンドルを握り、荷物や乗客を運ぶ最前線のプレイヤーです。
両者は立場こそ違いますが、安全運行という共通のゴールを共有しており、現場でのコミュニケーションと役割分担が極めて重要となります。
しかし、国土交通省の告示では「運行中は少なくとも1名の運行管理者が運転業務に従事せず、管理に専念できる状態を確保する」ことが求められており、これが「運行管理者は運転してはいけない」と誤解される原因になっているようです。
実は、条文を正しく読み解けば、一定条件下では兼任可能であることが分かるのですが、読み解くのは簡単ではありません。
まずは両者の役割を再認識した上で、法律上求められる配置基準を整理し、なぜ運行管理者が運転禁止と受け取られるのかを紐解いてみましょう。
運行管理者は運転してはいけないと誤解される理由とは?
まずは、誤解が生まれた理由について考察してみましょう。
今から遡ること18年前、平成19年(2007年)当時の貨物自動車運送事業輸送安全規則では、
運行管理者が不在等のため業務を行うことができない場合には、代務者を予め定める等により、運行業務を確実に行わせること
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二十条 第三項(平成19年3月30日改正によって削除)
といった条文が存在していました。
これは、運行管理者が営業所に常駐する義務を定めた条文でしたが、平成19年の通達改正以降、この条文は削除されています。
これによって「運行管理者は運転してはいけない(事実上できない)」と認知し続けている方も多く、当時の法律を知る人の中で誤解が広がったという説が有力なようです。
記事執筆時現在、貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送事業輸送安全規則に「運行管理者は運転してはならない」といった旨が明記された条文は存在しません。
ただし、運行管理者が運転手との兼任を認められるためには、常時、運行管理ができる体制の確保がなされているかが大きな課題となります。
一方、旅客自動車運送事業に対する運行管理制度において、乗合バス、貸切バス事業者に関しては「車両運行中少なくとも一人の運行管理者が、事業用自動車の運転業務に従事せずに、乗務員に対し必要な指示等を行える体制を整備しなければならない」といった文言が通達されているので、注意が必要です。
運行管理者の役割と業務

運行管理者の業務は多岐に渡ります。
単に点呼を取るだけではなく、運行計画の作成、社内安全教育の施行、アルコールチェック、健康状態の確認、休憩・休息時間の管理、事故発生時の初動対応など、現場の安全とコンプライアンスを守る最後の砦とも言えるのが運行管理者です。
そんな運行管理者自身がプレイヤーとしてハンドルを握ってしまうと、点呼や運行状況の監視、緊急対応といった本来の業務を同時に遂行できなくなる恐れがあります。
さらに、事故や遅延などのトラブル発生時には、運転中の管理者が即座に指示を出せない状況に陥ってしまう可能性も。
運行管理者の業務を適切に遂行するためには、長時間における運転と同時並行することは物理的に難しいケースが多く、慎重に常時の管理体制構築をおこなう必要があります。
参考:貨物自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方 |関東運輸局
運行管理者の常時選任と責任
貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条では、営業所の事業用車両の運行中、少なくとも1名の運行管理者を常時選任することを義務付けています。
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員(特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、貨物自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。
ここでいう「常時選任」とは単に会社に居るだけでなく、事業規模によって必要な人数の運行管理者が、指示系統を即時に機能させられる状態を指します。
運行管理者がドライバーとして現場に出てしまうと、この条件を満たせない可能性が高まります。
運行管理者に対する行政処分の多くは「管理者不在による点呼未実施」や「酒気帯び確認漏れ」といった形で摘発されており、その責任は運行管理者本人だけでなく事業者全体に及んでしまいます。
最悪の場合、事業停止や車両使用停止など、経営に直結する重い処分が下されるため、兼任を検討する際は、運行管理補助者を営業所に置くなど、まず運行管理者の常時選任条件をどう満たすかが最大の論点となるでしょう。
運行管理者とドライバーの兼任が可能な条件

それでは運行管理者と運転手の兼任が可能となる常時選任条件とはどのようなものになるのでしょうか?
ポイントとなるのは、「常時選任」がクリアできる体制を用意すれば、運行管理者が運転業務を兼任すること自体は法律上禁じられていないという点です。
ここでは、国土交通省の通達や監査事例を基に、兼任が認められる代表的なケースと注意点を整理してみましょう。
ただし、事業の種類、営業所の規模や車両台数、人員構成によって最適解が異なるため、自社の実態に当てはめて検討することが重要です。
兼任が許可される場合の要件
兼任が許可される要件を満たす代表例は、次の通りです。
- 運行管理補助者の選任
基礎講習を受講した補助者を選任し、運行管理者が不在でも点呼や運行指示が遂行できる体制を整えること。 - IT点呼の活用
IT点呼を導入し、運行管理者が遠隔地から点呼や酒気帯び確認を実施できる仕組みを構築すること。 - 運行管理者の乗務時間を調整
運行管理者本人の乗務時間を1日のうち限定的な時間帯に絞り、ほかの時間帯は常駐状態を確保するシフト設計を行うこと。
いずれの場合も、監査時に体制を証明できるエビデンス(点呼記録・システムログ等)が必要となりますので、記録や証明書の保存を忘れないようにしましょう。
| 要件 | 具体的な措置例 | 証明書類 |
|---|---|---|
| 補助者の選任 | 基礎講習修了者を最低1名配置 | 修了証写し・選任届 |
| IT点呼 | 国交省認定システムの導入 | システムログ・操作マニュアル |
| 乗務時間調整 | 運行管理者の乗務時間を 日中2h以内に限定 | 勤務表・乗務記録 |
これらは一例ですが、他にも、運行管理者を必要最低選任数より1名以上多く選任することで、運行管理者同士での点呼やアルコールチェックなどをおこなうことが可能になります。
兼任時の業務一覧とリスク

運行管理者がドライバーを兼ねる場合、自分自身への点呼・アルコールチェックは、他の運行管理者もしくは補助者が対面または遠隔で実施し、その記録を残す必要があります。
また長時間労働規制に抵触しないよう、運転時間・管理時間の両方を正確に勤怠管理することが求められます。
- 自己点呼は不可(他の運行管理者もしくは補助者による対面点呼が必須)
- 乗務前後の酒気帯び確認と記録保管
- 運行中緊急連絡時の応答体制確立
- 労働時間・休息期間の二重管理
- 点呼簿・乗務記録の整合性チェック強化
これらを怠れば、過労運転や点呼違反となる可能性があり、その場合即座に行政処分が科され業務に支障が生じてしまいます。
さらに、行政処分は公表されてしまうため、社会的制裁を負うリスクも存在します。
リスクが大きいことを把握した上で、運行管理体制の構築は慎重に判断する必要があります。
まとめ:兼任は可能だが運行管理に無理は禁物
この記事では、運行管理者が運転してはいけないという噂について検証し、兼任可能な条件とは何かを解説しました。
現在、貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送事業輸送安全規則に「運行管理者は運転してはならない」といった旨が明記された条文は存在しないものの、運行管理者が、指示系統を即時に機能させられる状態を構築することが兼任には必要不可欠です。
これを満たせないまま運行をおこなえば、事業停止や車両使用停止などの行政処分が下され、社会的制裁を負うことも十分にありえます。
運行管理者と運転手の兼任は可能ですが、無理のない体制で運行をおこなうことが大切です。
JAF交通安全トレーニングでは、交通ルールや運転に関する知識などはもちろん、適切な運行計画の考え方などといった実践的な教材を配信しており、eラーニング形式で毎月学習することができます。
従業員の運転行動や安全に対する意識を向上させたいとお考えの方は、JAF交通安全トレーニングの利用を検討してみてください。
\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /