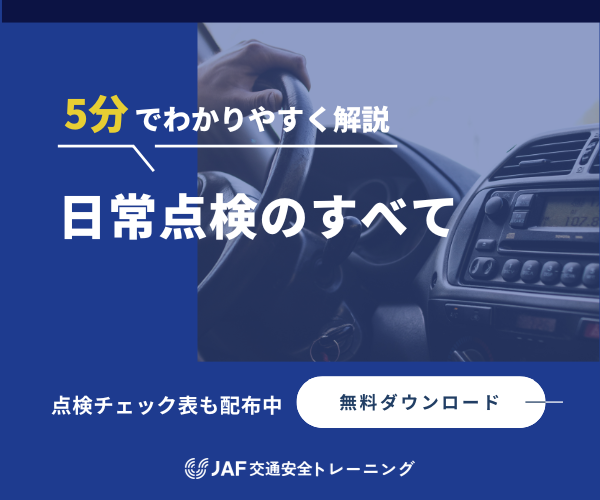法律とは、国民の意見に基づいて定められた「国のルール」と言えます。
しかし、そのルールは未来永劫不変という訳ではなく、時代の流れとともに常識も移り変わり、新しい技術の登場や社会問題に対応できるよう変わっていく必要があります。
それが「法改正」です。
より良い社会を作るため、今年も数多くの法改正がなされる予定です。
そこでこの記事では、2025年に予定されている自動車業界に関係する法改正の内容とその影響について解説していきます。
\ これを見ればすべて解決!/
目次
2025年問題と法改正

「少子高齢化」の一途にある現代です。
2025年は、いわゆる「団塊の世代」800万人が75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者とされる超高齢化社会を迎えています(75歳以上の人口が全人口の約18%になると推計:厚生労働省)。
団塊の世代とは、第一次ベビーブーム(1947年~1949年)に生まれた世代を指しますが、日本経済においては、高度経済成長やバブル景気を経験し、国の成長を支えてきました。
しかし、団塊の世代が後期高齢者となり、超高齢化社会を迎えることによって、「医療・介護の需要急増」「労働力不足」「社会保障費増大」といった諸問題が日本社会に大きな影響を及ぼすとされ、これらは「2025年問題」とも呼ばれます。
自動車業界でも、「人手不足」「高齢化」は喫緊の課題です。
これら2025年問題に代表されるような課題を解決するためにも、現代の働き方や生活環境に沿ったルールづくりが求められており、今年も様々な法改正が施行される予定です。
2025年に予定されている道路交通法の改正

道路交通法とは、簡単に言うと道路を使用する上でのルールをまとめた法律です。
ルールのない無秩序な状態では、人々は思うがままに道路を使い、やがて事故が起きて人が死傷してしまいます。
この法律は、道路における交通の安全と円滑を確保し、交通事故の防止を目的としています。
警察庁が管轄し、道路を利用するすべての人(運転者・歩行者・自転車利用者など)に適用されます。
企業においても、従業員の安全や社会的信用のため、道路交通法を遵守しなくてはいけません。
ここでは、2025年に法改正される道路交通法を解説します。
マイナ免許証の運用開始|3/24〜

2025年3月24日から、運転免許証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ免許証」の申請受付が開始されます。
運転免許取得時や更新時において、免許情報をマイナンバーカードのICチップへ記録することで、「運転免許証」と「マイナンバーカード」の役割を「マイナ免許証」1枚で果たします。
ただし、これは免許取得時・更新時にかかわらず、強制ではなく希望制となり、免許証の持ち方を以下の3つから選ぶことができます。
- マイナ免許証のみを保有する
- 従来の運転免許証のみを保有する
- 従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を保有する
従来通り、免許証のみで使うこともできますが、発行にともなう手数料が変わります。
| 新規取得 | 更新 | |
|---|---|---|
| マイナ免許証 | 1,550円(-500円) | 2,100円(-400円) |
| 従来の免許証 | 2,350円(+300円) | 2,850円(+350円) |
| 両方持つ場合 | 2,450円(+400円) | 2,950円(+450円) |
()内は従来の更新手数料との差異
このように、マイナ免許証のみの保有を選ぶことで発行手数料の割引といったメリットがあります。
また、住所・氏名の変更手続きがワンストップ化されるので、従来のように市区町村役場と警察署の2カ所に行く必要がなく、市区町村への届け出1回で完結します。
さらに、講習区分が「優良運転者」と「一般運転者」に限っては、免許更新時講習がオンラインで受講可能となり、手数料もグンと安くなります。
これまで更新時講習は対面のみでおこなっていましたが、自宅などの好きな場所、好きな時間にオンラインで受講することができます。
オンライン受講後、運転免許センター等に来場し、視力検査等の更新手続きをして終了となります。
| 優良 | 一般 | 違反 | 初回 | |
|---|---|---|---|---|
| 対面講習 | 500円 | 800円 | 1,400円 | 1,400円 |
| オンライン講習 | 200円 | 200円 | – | – |
出典:令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)|警察庁
普通MT免許のカリキュラム変更|4/1〜

4月1日に道路交通法施行規則の一部が改正され、指定自動車教習所(教習所)における「普通自動車第一種運転免許」「普通自動車第二種運転免許」のMT(マニュアルトランスミッション)免許について取得方法が変更されます。
今後、MT免許を取得するためには、実技教習をAT(オートマ)車でおこない、まずはAT車の卒業検定を受講・合格認定を受ける必要があります。
合格後、MT車による限定解除講習(追加4時間)を実施し、MT車の技能審査を受ける流れになります。
もし、MT車の技能審査が不合格だった場合には、MT車の補習を受講して再審査を受けることもできますし、AT車の卒業検定にはすでに合格していることから、MT免許の取得を一旦諦めAT限定免許取得に向けて学科試験へ向かうこともできます。
※ただし、カリキュラムの詳細が決まっていない部分もあり、4月1日以降も従来のMT免許教習が受講可能な教習所があるようです(複数の教習所に電話取材で聞き取り:記事執筆時点)。
この法改正にいたった背景には、日本自動車販売協会連合会の統計による、現在の新車販売に占めるAT車率が98%を超えていることや、普通免許受験者約158万人のうち109万人と約70%の人がAT限定を受験している(2023年)ことが影響したのではないかと考えられます。
このように、ニーズの変化に沿った法改正と言えそうです。
出典:道路交通法施行規則等の改正に伴う運用上の留意事項について|警察庁
軽貨物自動車安全管理者の選任と講習受講の義務化|4月〜

ここ数年、EC(電子商取引)市場の拡大により宅急便の取り扱い個数が増加しています。総務省の調べでは、どの世代においてもインターネットショッピングの利用率が70%~80%前後あるといった推計が出ています。
この配達需要の拡大により、軽自動車による配送事業参入が増え、この市場を支えてくれている一方で、事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が増加し、2016年~2022年にかけては、保有台数1万台あたりの事故件数が5割増となっています。
この状況を踏まえ、国土交通省は、4月から貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正をおこないます。
新制度の概要は大きく5つです。
- 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けられます。また、選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出をおこないます。
- 業務記録の作成・保存
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存が義務付けられます。
- 事故記録の作成・保存
貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録を作成し、これらの記録を3年間保存することが義務付けられます。
- 国土交通大臣への事故報告
貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故など一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告が義務付けられます。
- 特定の運転者への指導・監督及び適性診断
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことが義務付けられます。
補足として、新規事業者は必ず受講する必要がありますが、既存事業者には2年間の猶予期間が与えられます。
それでも、2027年3月までに全事業者が安全管理者を選任しなければ、事業が継続できなくなります。
また、届出後は2年ごとに講習受講を伴う更新手続きが必要となります。
出典:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正|国土交通省
道路運送車両法の目玉改正「車検制度」の見直し|4/1〜

道路運送車両法とは、自動車の「自動車の安全確保」「環境保護」「車両の適正管理」について規定している法律です。
主な目的としては、以下の3つが挙げられます。
- 自動車について所有権の公証をおこなう
- 自動車の安全性の確保と公害の防止、整備技術の向上により整備事業の発展に貢献する
- 自動車の流通会社を発展させ、公共の福祉に寄与すること
道路運送車両法について、2025年4月1日に法改正が予定されている新規則があります。
それが、「車検を受けられる期間の延長」です。
法改正前は、継続検査(車検)を受ける場合、自動車検査証(車検証)の有効期限が満了する日の「1カ月前」から受検が可能となっていました。
法改正後は、車検証の有効期限満了日の「2カ月前」から車検を受けられるようになります。
現状、車検の需要が毎年年度末に集中しているため、自動車ユーザーが整備や車検の予約を取りづらく、自動車整備士も残業・休日出勤に追われるという労働問題が生じています。
国土交通省の統計によると、1カ月の平均車検台数約281万台に対し、3月単月は約389万台と約1.4倍です(2019年から2023年までの5年間における平均)。
このような状況から、年度末の車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方改善のため、法改正にいたったという経緯があります。
来年以降、車検は混雑する年度末を避けて、余裕を持った予約・受検ができるようになります。
出典:来年4月より、車検を受けられる期間が延びます|国土交通省
まとめ:法改正を正しく理解して味方につけよう
本記事では、2025年に予定されている自動車業界に関する法改正の内容とその影響について解説していきました。
法改正と聞くと、一見複雑で難しい印象があるかもしれませんが、「マイナ免許証」などは生活に深く関わり、知っておくことで日常生活の役に立つこともあります。
法改正は社会や価値観の変化に対応し、人々がより良い生活が送れる環境を作るという目的があり、特に、今回紹介した「道路交通法」「道路運送車両法」の改正は、自動車業界の働き方改革という見方もできます。
この改正の内容を正しく理解して適切に行動することで、企業としても安全や生産性向上につなげることができるでしょう。
JAF交通安全トレーニングでは、新しい法律を題材にした教材など、交通安全に関するe-ラーニングを多数用意しています。
長年、交通環境改善に取り組んできたJAFの「知識」「技術」がふんだんに盛り込まれた実践的な視点の教材ですので、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因