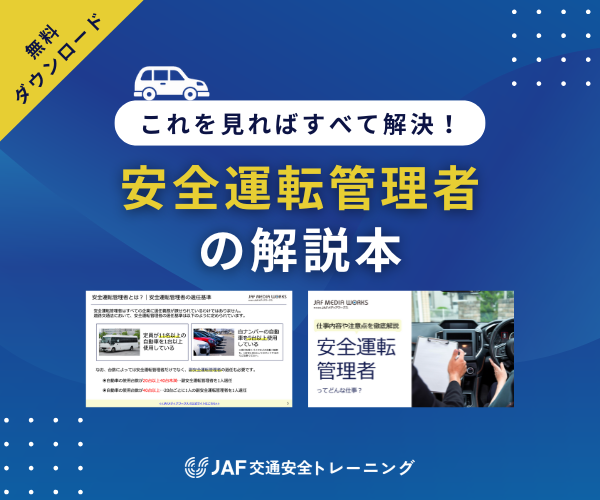安全運転管理者は、企業が安全運転を徹底する上で不可欠な役職です。
一方で、企業によっては運行管理者と呼ばれる役職があることをご存じでしょうか。
安全運転管理者と運行管理者は一見するとよく似ていますが、実は明確な違いがあります。
本記事では、安全運転管理者と運行管理者の配置基準や、業務の違いなどについて解説します。
安全運転を推進する体制を整えるためにも、それぞれの役割について正確に理解しましょう。
\ これを見ればすべて解決!/
目次
運行管理者と安全運転管理者の違い

まずは運行管理者と安全運転管理者の違いについて確認しましょう。
ここでは、それぞれの定義について解説します。
運行管理者とは
運行管理者は企業の安全管理をおこなう役職であり、緑ナンバーの自動車が管理対象です。
そのため、運行管理者は大型バス・タクシー・トラックなどの事業用自動車を持つ運送業の営業所に配置されます。
運行管理者の主な業務は以下のとおりです。
- シフトや乗務記録の管理
- 従業員の健康状態や酒気帯びの確認
- 休憩・睡眠施設の管理
- 安全運転の指導・監督
以上のように、運行管理者の業務は多岐に渡ります。
なお、運行管理者は企業の事業によって「貨物」と「旅客」の2種類に分かれます。
両者は配置基準が異なっており、貨物の場合だと運行管理者を営業所ごとに配置しなければなりません。
安全運転管理者とは
安全運転管理者は、運行管理者と同様に企業の安全運転を指導・管理し、従業員や一般の人々の安全を守る役職です。
しかし、運行管理者が事業用自動車を対象としているのに対し、安全運転管理者は白ナンバー(自家用車)を管理対象としています。
なお、安全運転管理者は以下のような業務を担います。
- 運運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
- アルコール検知器を使った酒気帯び確認
- 酒気帯び確認後の記録と保存、アルコール検知器の常時有効保持
- 運転日誌の備え付けと記録
- 運転者に対する安全運転指導
参照元:道路交通法施行規則第九条の十/安全運転管理者の業務の拡充等 警察庁
安全運転管理者の業務内容は、おおむね運行管理者と同じです。
運行管理者の配置基準

ここでは運行管理者の配置基準について解説します。
安全運転管理者とはさまざまな点で異なるので、混同しないように注意しましょう。
運行管理者が必要な企業
運行管理者が必要な企業は以下のとおりです。
| 一般旅客自動車運送事業 | バスやタクシーなど |
| 一般貨物自動車運送事業 | トラック |
先述したように、旅客・貨物を問わず、運送業であれば運行管理者は配置しなければなりません。
運行管理者の資格要件
運行管理者の資格要件は以下のとおりです。
- 実務経験が5年以上に加え、5回以上の所定講習を受講している
- 運行管理者試験に合格している
参照元:運行管理者について|国土交通省
運行管理者試験に合格すれば、運行管理者資格者証を取得できます。
自社の事業種に合わせて旅客・貨物のいずれかの運行管理者資格者証を取得しましょう。
なお、運行管理者試験は基礎講習の受講に加え、1年以上の実務経験がなければ受験できません。
運行管理者の選任基準
運行管理者は、事業種や営業所にある車両の台数によって選任すべき人数が異なります。
営業所ごとの選任基準の違いは以下のとおりです。
| 事業種 | 選任義務が発生する営業所 | 選任すべき運行管理者の人数 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス) | 事業用自動車19両以下の運行を管理する営業所 | 2人 ※車両数が4両以下であり、地方運輸局長が運行の安全の確保に支障がないと認めた場合は1人 |
| 事業用自動車20両以上99両以下の運行を管理する営業所 | 車両数÷20+1人 ※1未満の端数は切り捨て | |
| 事業用自動車100両以上の運行を管理する営業所 | (車両数-100)÷30+6人 ※1未満の端数は切り捨て | |
| 特定旅客自動車運送事業 | 乗車定員11人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員10人以下の事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所 | 車両数÷40+1人 ※1未満の端数は切り捨て |
| 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス) | 定員11人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所および、定員10人以下の事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所 | 車両数÷40+1人 ※1未満の端数は切り捨て |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー) | 事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所 | 車両数÷40+1人 ※1未満の端数は切り捨て |
| 一般貨物自動車運送事業(トラック) | 事業用自動車の運行を管理する営業所 | 車両数÷30+1人以上 ※1未満の端数は切り捨て ※車両数が5両未満であり、地方運輸局長が運行の安全の確保に支障がないと認めた場合はこの限りではない |
なお、複数の運行管理者を選任する営業所の場合、運行管理者の業務を統括する統括運行管理者を選任する必要があります。
安全運転管理者の選任基準

ここでは安全運転管理者の配置基準について解説します。
運行管理者とは違う点が多いため、正確に把握しましょう。
安全運転管理者が必要な企業
安全運転管理者の選任基準は以下のとおりです。
- 乗車定員数が11人以上の自動車を1台以上使用している場合
- その他の自動車を5台以上使用している場合
参照元:道路交通法施行規則第九条の八
さらに使用する自動車の台数に応じて、副安全運転管理者も選任しなければなりません。
- 自動車の使用数が20台以上40台未満…副安全運転管理者を1人選任
- 自動車の使用数が40台以上…20台ごとに1人の副安全運転管理者を1人選任
参照元:道路交通法施行規則第九条の十一
安全運転管理者の資格要件
安全運転管理者の業務は運行管理者と類似していますが、資格要件が異なります。
安全運転管理者の資格要件は以下のとおりです。
| 安全運転管理者 | ・20歳以上(副安全運転管理者を選任するなら30歳以上) ・2年以上運転管理の実務経験がある者、自動車運転管理に関してこれらの者と同等以上の能力があると公安委員会が認定した者のいずれか ・過去2年以内に公安委員会より解任命令を受けたことがない ・過去2年以内に一定の違反行為をしたことがない |
| 副安全運転管理者 | ・20歳以上 ・1年以上の運転管理の実務経験あるいは3年以上の運転経験がある者、自動車運転管理に関してこれらの者と同等以上の能力があると公安委員会が認定した者のいずれか ・過去2年以内に公安委員会より解任命令を受けたことがない ・過去2年以内に一定の違反行為をしたことがない |
原則として安全運転管理者は運転管理の実務経験が2年以上なければなりません。
しかし、2年以上の実務経験と同等の能力があると公安委員会が判断できる従業員なら、選任が認められる場合があります。
運行管理者を選任する際の注意点
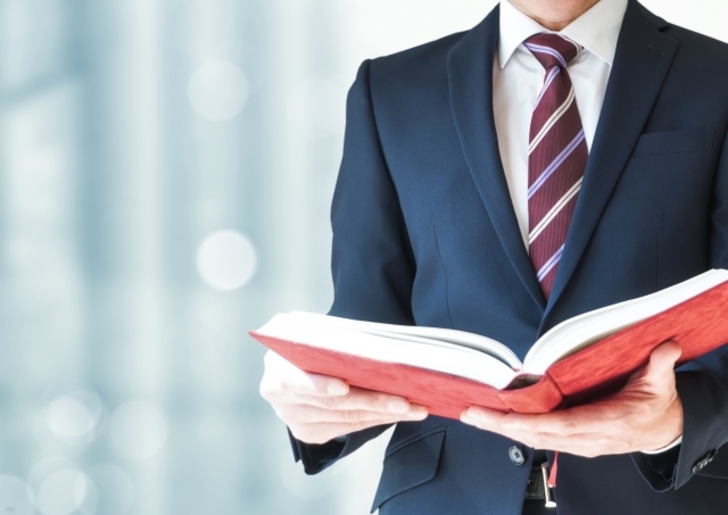
運行管理者を選任する際は、いくつかの注意点を意識しなければなりません。
運行管理者を選任する際は、必ずチェックしましょう。
兼任できる業務に制限がある
運行管理者は業務の都合上、兼任できる業務に制限があります。
特に、ドライバーとしての業務は点呼や安全管理業務に影響を及ぼす可能性が高いため、原則として兼任はできません。
他の業務との兼任を前提して選任するなら、複数の運行管理者を選任したり、補助者を設置したりする必要があります。
違反時に講習を受講しなければならない
運行管理者は、重大な交通事故や法令違反が発生した際に特別講習を受けなければなりません。
これは、本人ではなく営業所、事業所で発生した事故や違反が対象です。
特別講習は、事故や法令違反が発生してから1年以内(やむを得ない事情がある際は1年6カ月以内)に受講するように定められています。
さらに、特別講習に加え基礎(一般)講習を受講する義務も発生します。
講習は重要ですが、日常的な業務に加えて受講しなければなりません。
業務に支障をきたさないように注意しましょう。
業務負担が大きくなりやすい
運行管理者は業務が多岐に渡るため、負担が大きくなりやすい傾向があります。
運行管理者の業務はドライバーの健康状態や車両の管理など、安全運転の順守に必要なものばかりです。
いずれも重い責任が伴う業務である上に、点呼業務などのように早朝や深夜におこなうケースも珍しくありません。
また、運行管理者は現場のドライバー・経営陣・取引先の板挟みになりやすい立場です。
人間関係で悩んだり、さまざまな立場の利害関係を調整に苦心したりする場面も想定されます。
運行管理者を選任する際は、過度な負担がかからないように、業務をサポートできる体制を整えることが重要です。
安全運転管理者を選任する際の注意点

安全運転管理者にも、選任する上での注意点があります。
スムーズに業務を遂行するためにも、必ずチェックしましょう。
法定講習を受けなければならない
安全運転管理者は運行管理者と同様に法定講習を受けなければなりません。
安全運転管理者の法定講習は年に1回必ず受講するものであり、公安委員会が実施します。
失念することがないように、事前に講習の日程を確認しましょう。
なお、法定講習は会場講習とオンライン講習のいずれかを選択できます。
業務の都合で外出が難しい際は、オンライン講習の受講がおすすめです。
必要なケースと不要なケースが区別しにくい
安全運転管理者の選任基準は、事業所にある自動車の台数などによって決められます。
しかし、選任基準は企業全体ではなく、事業所ごとに適用される点には注意が必要です。
同じ企業でも、事業所が所有する自動車の台数が異なれば、選任義務の有無は変わります。
そのため、事業所ごとの自動車の台数は適切に把握しなければなりません。
なお、安全運転管理者を選任基準や台数の数え方は以下のとおりです。
- 乗車定員数が11人以上の自動車が1台以上
- 自家用自動車やトラックが5台以上
- 大型・普通自動二輪車は1台=0.5台で換算
参照元:道路交通法施行規則第九条の九
カーリース・レンタル・カーシェアなどで車両を利用している場合でも、事業所が使用する自動車としてカウントする必要があります。
運行管理者の義務違反に対する罰則

道路運送法では、運行管理者が義務違反をおこなった場合の罰則が設けられています。
ここでは、運行管理者の義務違反における罰則について解説します。
選任義務違反
選任義務違反とは、運行管理者の選任義務があるにもかかわらず、企業が運行管理者を選任していない場合に課される罰則です。
バスやタクシーなどを運行する「旅客運送業」の場合は100万円以下の罰金、荷物の配送などをおこなう「貨物運送業」の場合は150万円以下の罰金が科されます。
また、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づき、営業停止処分が科される可能性があります。
※参考:貨物自動車運送事業法第七十四条の一 | e-Gov 法令検索
※参考:貨物自動車運送事業法第三十三条 | e-Gov 法令検索
選任解任届出義務違反
選任解任届出義務違反とは、運行管理者を選任または解任した際に、国へ所定の届出を行わなかった場合に科される罰則です。
具体的な罰則の内容は、旅客運送業・貨物運送業いずれも100万円以下の罰金です。
主に以下のようなケースが、選任解任届出義務違反にあたります。
- 選任時に届出を出さなかった
- 解任時に届出を出さなかった
- 運行管理者の変更から所定の期限内に届出をおこなわなかった
なお、届出を提出する期限は、旅客運送業か貨物運送業かで異なるため注意が必要です。
| 事業の種類 | 提出期限 |
|---|---|
| 旅客自動車運送事業者 | 変更発生日から15日以内 |
| 貨物自動車運送事業者 | 変更発生日から7日以内 |
返納命令違反
返納命令違反とは、国から運行管理者資格者証の返納を命じられたにもかかわらず、それに従わなかった場合に科される罰則であり、50万円以下の罰金が科されます。
運行管理者に対する返納命令は以下のような場合に出されます。
- 運行管理者が飲酒運転をおこなった
- 運行管理者が実際に業務をおこなっていない企業に対し名義を貸した
返納命令が出された場合は、速やかに返納手続きをおこないましょう。
安全運転管理者の義務違反に対する罰則

安全運転管理者も運行管理者と同様に、義務を怠ったり命令を無視したりする企業には罰則が発生します。
ここでは、安全運転管理者における違反時の罰則について解説します。
選任義務違反
安全運転管理者も運行管理者と同じく、安全運転管理者の選任が必要であるにもかかわらず事業者が選任しない場合は選任義務違反となります。
以前は選任義務違反に対する罰則は5万円以下の罰金でしたが、2022年10月の道路交通法改正にともない50万円以下の罰金へ引き上げられています。(令和4年10月1日施行)
解任命令違反
解任命令違反とは、公安委員会から安全運転管理者を解任するよう命じられても従わなかった場合に発生する罰則で、50万円以下の罰金が科されます。
公安委員会からの解任命令は、以下のような事態が生じた際に発令されます。
- 安全運転管理者が適切に職務を遂行できないと公安委員会が判断した
- 法令違反をはじめとした不適切な管理状況が明らかになった
解任命令に従わずに選任状態を継続した場合や、解任命令に反して同一人物を再び安全運転管理者に選任した場合も、解任命令違反となり罰則の対象です。
選任解任届出義務違反
選任解任届出義務違反は、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任・解任した際に、公安委員会に届出をしなかった場合に科される罰則です。
具体的な罰則内容としては、5万円以下の罰金が科せされます。
なお、届出の提出期限は選任または解任の日から15日以内となっており、提出方法には、窓口へ提出や郵送、オンライン申請などがあります。
提出期限を過ぎてしまうことがないよう、選任や解任が生じた際は、速やかに所轄の警察署を経由して公安委員会に届け出ましょう。
(参考:道路交通法第七十四条の三第五項)
是正措置命令違反
是正措置命令違反は、公安委員会からの是正措置命令に従わなかった場合に科される罰則で、50万円以下の罰金が科されます。
2022年10月の道路交通法の改正では、従業員の交通安全が確保できていないと判断した場合、公安委員会は車両の使用者に対して是正措置命令を発することができるようになりました。
以下に、是正措置命令が下されるケースを一部紹介します。
- 安全運転管理者に、夜間・長距離運転時の交替ドライバーを配置する権限を与えていなかったことが原因で、ドライバーが過労による居眠り運転して交通事故が発生した場合
- アルコール検知器を必要数揃えることを怠ったことで、アルコールチェックが適切に行われなかった結果、酒気帯び運転が発生した場合
公安委員会から是正措置命令が出された際は、速やかに対応するとともに、今現在の環境が従業員の安全を確保できるものであるかどうか確認しましょう。
(参考:道路交通法第七十四条の三第七項、道路交通法第七十四条の三第八項)
(参考:道路交通法に基づく自動車の使用者に対する是正措置命令等の基準について(通達)
まとめ:運行管理者と安全運転管理者の違いを正確に把握しよう

運行管理者と安全運転管理者は業務内容が類似していますが、管理対象となる車両の種類や選任基準などが異なります。
自社の状況が、運行管理者・安全運転管理者のいずれに該当するかは選任する際に必ず確認しましょう。
また、管理する自動車の台数や種類などによって、選任する運行管理者・安全運転管理者の人数も変わります。
正確な知識で選任するようにしましょう。
従業員への安全運転教育に課題を感じている担当者は、JAFトレにご相談ください。
\ これを見ればすべて解決!/