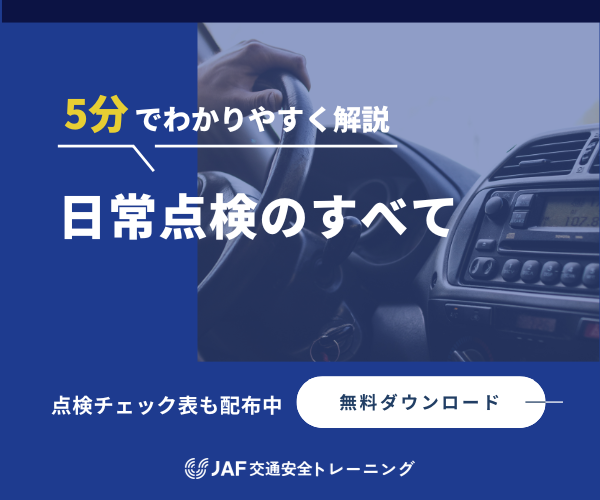社用車は、会社が購入し管理する資産のひとつです。
業務を遂行する目的のために使用され、個人が私的に利用したい時には、事前に会社へ相談や申請をおこなった上で使用許諾を得る必要があります。
この記事では、社用車の私的な利用ケースの一例を紹介することに加え、無断での私的利用を防止する対応策などを紹介していきます。
若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因
目次
社用車の私的利用が引き起こすトラブルとは

社用車の私的利用をおこなってもただちに違法とはなりません。
基本的には、企業の就業規則や車両管理規定によってその可否が判断されるため、社用車を所有する企業ごとに対応が分かれます。
規定内で利用を認めている企業もあれば、一切禁止とする企業もあります。
しかし、本来の目的以外で社用車を使用したり、許諾を受けずに無断で私的利用をおこなう従業員がいることも珍しくなく、悪質な場合には懲戒処分の対象となる可能性や、違法性をはらむ可能性もあります。
ここでは、社用車の私的利用によってどのようなトラブルが生じるのか、また私的利用がおこなわれるのはどんなケースがあるのか、一例を交えながら紹介していきます。
私的利用時に事故!企業の責任範囲・リスクは?
社員が社用車を私的に利用した時に、交通事故を起こしたり巻き込まれてしまった場合、社用車を所有する企業は「使用者責任」や「運行供用者責任」を問われる可能性があります。
民法715条「使用者責任」
社員が他人に損害を発生させた場合、社員が所属する会社も被害者に対して損害賠償責任を負わなければならない
自動車損害賠償保障法3条「運行供用者責任」
自動車の運行によって利益を得ることができる立場にある者は、その運行によって損害を発生させた場合、生じた損害に対して賠償責任を負わなければならない
これは社用車を利用していることから、その状況が業務内・業務外であるかにかかわらず、適用される可能性があります。
事故を起こした従業員だけでなく、会社側にも雇用主としての責任が発生するからです。
ただし、従業員が車両管理規程に違反していた場合は、その限りではありません。
法的責任の範囲は、車両管理規程の内容や事故の経緯なども考慮され、責任の所在も一律ではありません。
業務内はもちろん、無断での私的利用時など、あらゆるケースで起こり得る交通事故を想定し、車両管理規程の内容を明確にしておくことが必要です。
当然、車を運転する時間や移動距離に比例して事故を起こす確率は高まるため、社用車を管理する企業には事後処理対応に人員を割かれるリスクなどが増すことになります。
また、業務中の運転とは異なり、家族や友人を乗せたりするプライベートの感覚の中で社用車を利用することよって、安全運転への意識が薄れる可能性もあります。
管理者はそのようなリスクも想定した上で、私的利用の許可について検討するべきです。
引用:民法715条「使用者責任」|e-GOV法令検索
引用:自動車損害賠償保障法3条「運行供用者責任」|e-GOV法令検索
事故や横領などのリスク
従業員が会社から使用許諾を得ず、勝手に業務外使用をおこなった場合、業務上横領罪などの刑事責任や、懲戒処分などの民事責任を問われる可能性があります。
さらに事故を起こしてしまえば、契約内容によっては自動車保険などが適用されない可能性もあり、賠償責任が個人に重くのしかかることも考えられます。
また、私的利用時のガソリン代や高速道路利用代を会社経費として申告することや、私的利用時に会社のETCカードで高速利用した際などにはETCカードの不正利用にあたり、刑法253条「業務上横領罪」が適用されることも。
刑法第253条「業務上横領罪」
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、会社は社用車の管理体制を整え、従業員へ社用車利用ルールの周知徹底・モラル向上を図ることが必要となります。
私的利用が企業に与える法的責任と損害賠償の可能性
業務中に加え、業務以外でも社用車を私的使用すれば、車の使用機会が増える分、おのずと交通事故に遭う可能性が高まります。
本来、従業員が業務中に交通事故を起こした場合は、企業側と従業員側の双方に責任が問われます。
その際、企業側は民法における使用者責任(第715条)と自動車損害賠償保障法の運行供用者責任(第3条)、従業員側は利用状況に応じた刑事上の責任を負うのが一般的です。
一方、従業員が社用車を私的利用している際に交通事故が発生すると、企業と従業員のどちらが責任を負うべきかという問題が発生します。
もしも私的利用が無断であった場合は、企業側にはいずれの責任も負う必要がないと判断される可能性は高いですが、状況によって、企業にも責任が少なからずあったと判断されれば、従業員だけでなく企業も事故の責任を負わなければなりません。
社用車を個人使用する場合は、企業の法的責任の発生リスクがあることを理解しておきましょう。
企業のブランドイメージを毀損する可能性
社用車を私的に利用することは、所有企業の規定内に収まる方法であればただちに法律を犯すものではありません。
しかし、それが所有企業に無断で使用したケースであったり、著しく公序良俗に反するような利用方法であった場合には話が変わってきます。
特に、社用車に企業ロゴなどが表示されている場合には、私的利用中に企業のブランドイメージを毀損したりといった事態も考えられます。
万が一、事故を起こして事後処理などがもたつけば、会社の信頼性低下に繋がる可能性もあります。
そのようなトラブルを防止するためには、社用車の車両管理規定をしっかりと定めましょう。
それらのリスクを理解した上で、企業側が社用車の私的利用を従業員に認める場合には、適用範囲の策定や万が一の場合の責任の所在を明確にしておくことが重要です。
社用車私的利用の背景と従業員の行動例

社用車の私的利用といっても、会社の業態や車種などによって理由はさまざまです。
ここでは従業員が私的に利用する背景や行動例の一例を紹介していきます。
アウト?セーフ?社用車を私的利用するケースを紹介
いわゆる「寄り道」をおこなうのが私的利用の最も代表的なケースです。
一方、所定休日や法定休日など、会社が休みの日に社用車を個人使用するケースもあります。
たとえば、
- 翌日、自宅から直行で取引先へ訪問するために、終業後そのまま社用車帰路で、個人的な買い物などの私用をおこなった
- 出張先への交通手段として利用したが、夕食を取ろうにも宿泊先近くにコンビニやスーパーなどがないことが判明し、社用車を足代わりに使わざるを得なかった
- 月曜日の朝一番から業務利用するため金曜日の終業後に自宅まで乗って帰り、休日中に引っ越しや買い物などに個人利用した
いずれも、会社の車両使用規約に沿って利用すれば問題ありません。
しかし、無断での使用が発覚した場合には、規約に基づき、懲戒処分が下されることも考えられます。
会社は無断での社用車私的利用を確認しやすい環境づくりを
企業が特に懸念すべきは、「無断での私的利用」がおこなわれやすい環境となっていないか、またその状況が放置されていないかどうかです。
無断での私的利用がバレにくい環境を放置すれば、無断利用が常習化することも考えられます。
社用車の私的利用自体は、会社ごとの車両使用規則に則って利用すれば何も問題はありませんが、無断での私的利用となると話は別です。
無断利用をしてもバレにくい環境を放置することで、先述したリスクは広がる一方となるため、早めの対策をおこないましょう。
社用車管理施策の一例としては、
- 運行記録表における走行距離や給油記録などをもとに、不必要な走行がされていないか使用者本人を含めない2段階以上のチェック体制をつくる
- GPS機能付きのドライブレコーダーなどを設置し、走行データのログを自動収集し管理者が閲覧できるものとする
- 社用車に関するルールの策定・再検討をおこない、定期的な周知徹底を施す
など、プライベートと業務利用の境目を明白にし、運行記録を会社にしっかり管理されていることを意識させるようなリスク回避策が効果的です。
社用車に特化した適切な利用ルールの必要性

社用車に予約管理システムを導入し、いま誰が社用車を使用しているのか、「見える化」をおこない、事前に予約をしなければ乗れない仕組みをつくることで、無断利用を防止する効果が期待できます。
さらに、車両管理規則の策定と、それに違反した場合のリスクについて周知徹底をおこなうべきです。
実際に車を運転する従業員が、事前にリスクを想定できれば、危険運転の抑制や適正な判断などにつながります。
また、事故やトラブルが起きた際の責任範囲を明確にしましょう。
事故発生時の現場担当者の対応方法や、管理者の対応範囲が明確になると、不測のトラブルにも落ち着いた対処が可能です。
ドライブレコーダーやGPSシステムの導入と管理
最近では、GPSシステムが搭載されたドライブレコーダーやGPSトラッカーなどの管理機器を車両に取り付ける企業が多くなっています。
これらを導入することで、走行距離や走行ルート、走行時刻、滞在時間なども表示可能となり、社用車の管理が楽になります。
ただし、GPSシステムによって位置情報が管理されていることで、私的利用を許可した時間の社員のプライバシーを侵害してしまう可能性も考えられます。
社用車の車両使用規定や私的利用承諾書などに、GPSシステムでの管理目的を盛り込んだ上で、運行管理者だけに閲覧権限を付与されることなど配慮についての説明をおこない、社員の理解を得ることが必要です。
アルコールチェックや交通安全教育の実施
社用車の私的利用時に怖いのは、重大な交通違反がおこなわれる可能性です。
たとえば、飲酒運転がそれに該当します。
社用車の利用時には、乗車前のアルコールチェックを必ず義務付けるなど、従業員の規律意識の向上を図りましょう。
私的利用を許可している時間内において、万が一従業員が飲酒運転をおこなってしまった場合、企業側にも管理責任が追求されることは免れません。
飲酒運転をはじめとして重大な交通違反が私的利用時におこなわれないよう、普段から社員への交通安全教育を徹底することも防止策として有効となります。
まとめ|社用車の私的利用には多くのリスクが存在する
企業ごとの車両使用規定に則り、正しく利用すれば違法とはならない社用車の私的利用。
しかし、社員が社用車を私的利用時に交通事故を起こしたり巻き込まれてしまった場合、社用車を所有する企業には「使用者責任」や「運行供用者責任」が問われる可能性があり、使用者である社員は状況に応じた刑事罰などに問われる可能性もあります。
さらにそれが無断使用であった場合、事故やトラブルが発生しなくとも、会社の財産を私的に利用したとして、業務上横領罪などの刑事責任や、懲戒処分などの民事責任を問われる可能性もあり、私的利用は違法行為につながる可能性をはらんでいるといえるでしょう。
企業は、さまざまなケースに対応できるよう、就業規則や車両使用規則の策定をしっかりとおこない、備えておくことが必要になります。
さらに私的利用時のトラブルを防止するためには、普段からの社員への交通安全教育が必要不可欠です。
JAF交通安全トレーニングでは、社用車を利用する際のトラブルを未然に防ぐための、道交法や交通ルールを学べるe-ラーニングコンテンツが充実しています。
「飲酒の影響が翌日まで続くのかどうか」や「SNS時代の企業ドライバーに向けた注意喚起」など、社用車の私的利用時の意識向上に役立つ教材も数多く配信されていますので、万が一のトラブルを防ぐため、さらに社員の交通安全意識の向上を図るために活用を検討してみましょう。
\ これを見ればすべて解決!/